
(本記事は、伊藤 俊一氏の著書『Q&Aみなし配当のすべて』=ロギカ書房、2020年7月31日刊=の中から一部を抜粋・編集しています)
Q4―8 混合配当とみなし配当該当性に係る公表裁決
- 混合配当とみなし配当該当性に係る公表裁決について実務上のポイントは何か教えてください。
Answerーーーー
下記になります。
【解説】
- 【(受取配当等の益金不算入)請求人が子会社から受けた利益剰余金を配当原資とする剰余金の配当及び資本剰余金を配当原資とする剰余金の配当は、その全額が資本の払戻しによるものに該当するとした事例】(平24―08―15公表裁決)
〔ポイント〕
請求人は、請求人の子会社からの利益剰余金を原資とする剰余金の配当及び資本剰余金を原資とする剰余金の配当について、会社法上別々の法律行為として成立しているのであるから、利益剰余金を原資とする剰余金の配当は法人税法第23条《受取配当等の益金不算入》第1項第1号の剰余金の配当に、資本剰余金を原資とする剰余金の配当は同法第24条《配当等の額とみなす金額》第1項第3 号の資本の払戻しによるものにそれぞれ該当する旨、また、当該剰余金の配当の全額を同号に規定する資本の払戻しによるものとして取り扱うと、法人税法施行令第23条《所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等》第1項第3号の「払戻し等に係る株式の総数」に、利益剰余金を原資とする剰余金の配当の対象となった種類株式数が含まれるため、種類株式ごとの対応が図れないこととなる点からも当該剰余金の配当の全額が資本の払戻しによるものに該当しない旨主張する。
しかしながら、当該子会社は、剰余金の配当の原資となる利益剰余金及び資本剰余金を同一の効力発生日に同時に減少して剰余金の配当を行っているから、当該剰余金の配当は、その全額が資本剰余金の額の減少に伴うものに該当し、法人税法第24条第1項第3号に規定する資本の払戻しとして同条が適用されることとなる。
また、上記「払戻し等に係る株式の総数」の「払戻し等」には同号の資本の払戻しが含まれ、当該剰余金の配当の全額が資本の払戻しによるものに該当するから、当該子会社から当該剰余金の配当の支払を受けた株主が所有する当該子会社発行済株式の総数が上記「払戻し等に係る株式の総数」となる。
(実務上のポイント)
利益剰余金を原資とする配当と資本剰余金を原資とする配当を同日に行った場合、租税法においては、利益剰余金の配当と資本剰余金の配当の合計額を資本の払戻しとして取り扱い、その合計金額を資本金等の額からなる部分の金額と利益積立金額からなる部分の金額とに区分するという課税実務上において、不明確である点につき論点となったものです。
本裁決に従えば、混合配当が行われたときは、①資本剰余金の減少分は資本金等の額と利益積立金額との比例的減少、②含み益部分は利益積立金額の減少という結果になります。同時配当(混合配当)についてはQ1-30の裁判例もあわせてご参照ください。
Q4―9 和解金の支払いが剰余金の分配と認められ資本等取引に該当するとされた公表裁決
- 和解金の支払が剰余金の分配と認められ資本等取引に該当に係る公表裁決について実務上のポイントは何か教えてください。
Answerーーーー
下記になります。
【解説】
- 【(和解金(剰余金の分配と認定した事例))和解金の支払が剰余金の分配と認められ資本等取引に該当するとして損金の額に算入できないとした事例】(平23―07―05公表裁決)
〔ポイント〕
この事例は、訴訟上の和解に基づき請求人が支払った和解金の性格について、訴訟の経緯、対立点及び和解において請求人が当該和解金を支払うに至った経過並びに和解調書の和解条項内容及び請求人の会計処理の事実から認定したものである。
請求人は、本件和解(訴訟上の和解)は、原告ら(L及びNら)の請求内容(出資持分の払戻請求及び退職金の支払請求)を認めた内容の和解ではなく、多様な意味合いを包含した金額面での和解であり、本件和解金からLの退職金を控除した金員(本件金員)は、経営上当然の経済行為に基づく支払金という性格を意味しており、出資持分があることを根拠として支払ったものではないから、本件金員の額からLの出資額などを控除した額(本件特別損失額)は本件事業年度の損金の額に計上できる旨主張する。
しかしながら、本件訴訟の経緯、対立点及び和解において請求人が本件和解金を支払うに至った経過並びに和解調書の和解条項内容及び請求人の会計処理の事実についてみると、請求人は、原告らに出資持分の払戻請求権相当の権利を認めるなど、本件和解金を支払うことで請求人と原告らの債権債務関係を消滅させたものと推認されることから、本件金員からNの退職金相当額を差し引いた金員は、出資者たる地位に基づき支払われた金員であるといえ、当該金員から請求人が資本金勘定から減額したLの出資金相当額などを控除した金員は、剰余金の分配に当たると認められるので、法人税法第22条《各事業年度の所得金額の計算》第5項に規定する資本等取引に該当する。
また、平成8年3月期に請求人がNに対する役員退職金として支出した金員相当額が本件和解金の計算に含められた経緯等から判断すると、当該退職金相当額については、請求人が真に支払を受けた者に代わって仮払金・立替金の類として支払ったものであると考えるのが自然である。
したがって、本件特別損失額は、法人税法第22条第3項の規定により本件事業年度の損金の額に算入することはできない。
(参考判決・裁決)
平成20年1月23日裁決(裁決事例集No.75・78頁)
(実務上のポイント)
本件では出資者が2人います。出資払戻しは資本金等の減額扱いとなりますが、和解契約の経緯における事実認定から出資者2人のうち1人に支払った退職金につき損金不算入としたものです。
和解契約書等を作成する場合、名目は解決金といったものにしても、それを当局がどのように判断するのか考慮してのエビデンスの整理が必要です。例えば、その和解に至った経緯、なぜその金額になったかということについての疎明資料は必須です。
Q4―10 担保権実行の適法性とみなし配当の非課税所得該当性に係る裁判例
- 担保権実行の適法性とみなし配当の非課税所得該当性に係る裁判例について実務上のポイントは何か教えてください。
Answerーーーー
下記になります。
【解説】
- 【担保権実行の適法性とみなし配当の非課税所得該当性】東京高等裁判所平成22年(行コ)第4号所得税更正処分等取消請求控訴事件(棄却)(上告)国側当事者・国(浦和税務署長)平成22年6月23日判決【税務訴訟資料 第260号―99(順号11455)】
※上告棄却
〔ポイント〕
当裁判所も、控訴人の請求は理由がないと判断する。その理由は、次のとおり付加訂正するほかは、原判決のとおりであるから、これを引用する。
控訴人は、担保権実行当時の本件株式の適正時価(客観的な交換価値)は、9045万0528円(1株2248円)であると主張する。
しかし、平成16年1月15日当時は、控訴人自身が上記評価の問題点を指摘してその評価を争い、1株1万2624円であるとの主張をしたことから、A社において、弁護士や税務署とも相談の上、財産評価基本通達に則ってその客観的時価を再評価した結果が1 株5599円であったことが認められる。
そうすると、担保権実行の際の1株の評価額5145円は、上記客観的時価と著しく乖離しているとはいえない。
したがって、株式発行法人が自己株式を時価と著しく乖離した価額で取得した場合における所得税法上の適法な取扱いいかんを問題とするまでもなく、本件株式の客観的な時価総額が2億0701万4220円と著しく乖離した金額であることを前提とする控訴人の主張は採用することができず、みなし配当額の算定に違法はない。
本件担保権の実行と同時に、何らの特別の手続を要することなくA社の源泉徴収義務が成立し、控訴人はA社に対し、その源泉徴収税額と同額の債務を負うことになるが、それは、担保権実行当時存在していた債務ではなく、担保権実行の結果、控訴人が負担するべき所得税法25条1項5号によるみなし配当に対する所得税の一部について、A社が所得税法181条1項によって源泉徴収義務を負ったために発生したものである。
その課税関係から発生する債務を考慮して所得税法9条1項10号の非課税扱いを認めるならば、担保権実行の際には積極財産を有し課税することが可能で、納税資力があったにもかかわらず、課税関係発生と同時に発生する債務を考慮して、その課税を免れることができるという結果が生ずることになる。
しかし、所得税法9条1項10号は、資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難な場合における強制換価手続による資産の譲渡の場合は、その資産の所有者が納税資力がないため実際問題として課税することが困難であることなどから課税しないこととしたものである。
そのため、同号は、納税資力があったにもかかわらず課税関係発生と同時に発生する債務を考慮して、その課税を免れるなどということを想定しておらず、これを認めるならば、立法趣旨に反することは明らかである。
※参考までに下級審の判決を挙げておきます。
- さいたま地方裁判所平成20年(行ウ)第6号所得税更正処分等取消請求事件(棄却)(控訴)国側当事者・国(浦和税務署長)平成21年11月25日判決【税務訴訟資料 第259号―214(順号11327)】
(ポイント)
本件は、原告の平成16年分所得税の確定申告に対し、みなし配当所得の申告漏れがあるとして更正処分等がなされたところ、原告が、みなし配当所得は生じておらず、また、仮に同所得が生じていたとしても、当該所得は非課税所得に該当するから各処分は違法であると主張して、更正処分等の取消しを求めた事案である。
所得税法25条1項5号に規定する「金銭その他の資産の交付を受けた場合」には、金銭その他の資産の交付のみならず、同様の経済的成果をもたらす債務の消滅等があった場合も含むと解するのが相当である。
そして、所得税は、現実に発生した経済的成果を課税対象とするものであるから、同成果の発生の前提となる私法上の行為に瑕疵がある場合であっても、これによる経済的成果が発生し、存続していると認められる以上、同経済的成果を対象に課税することは適法になし得るところである。
原告は、A社の株主であるところ、同社から2億円を借り入れるに際し同社株式を担保に供していたが、原告が借入れの返済を怠ったため、A社は担保権を実行することとし、自己の株式である本件株式を合計2億0701万4220円と評価し原告に提案した。原告は、A社による担保権の実行に同意していたものと認められる。
A社は、2億0701万4220円から同社の資本等の金額のうち本件株式に対応する部分の金額(2011万8000円)を差し引いた1億8689万6220円について源泉徴収を行い、2億0701万4220円から源泉徴収額を差し引いた残金を借入れに対する弁済に充てたということができる。
そうすると、原告は、本件担保権の実行により2億0701万4220円を得たのであり、同金額から上記2011万8000円を差し引いた1億8689万6220円が原告のみなし配当にかかる所得として課税対象になるというべきである。
原告は、収入金額は本件株式の客観的な価額に基づいて算定されるべきであったと主張する。しかし、所得税の課税の対象となる原告が受けた経済的成果は、本件株式の客観的時価に基づいて算出されるものではなく、取引において現実に前提とされた価額に基づいて算出されるものというべきであるから、原告が担保権の実行により得た収入を、A社が行った算定額を前提として算出することは適法である。
所得税法9条1項10号及び同法施行令26条の趣旨にかんがみると、資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合とは、当該資産の譲渡時に、債務者の債務超過の状態が著しく、その者の信用、才能等を活用しても、現にその債務の全部を弁済するための資金を調達することができないのみならず、近い将来においても調達することができないと認められる場合をいうと解すべきである。所得税基本通達9―12の2においても同様に解されている。
認定事実によれば、本件みなし配当所得は、資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であり、かつ、国税通則法2 条10号に規定する強制換価手続の執行が避けられないと認められる場合における資産の譲渡による所得で、その譲渡に係る対価が当該債務の弁済に充てられたものには該当せず、所得税法9条1項10号の規定する非課税所得には当たらない。
(実務上のポイント)
本件はみなし配当とは直接関係ありません。本案件は「自己が有する株式」は金銭債権の回収として取得したものであっても、会社法上、及び法人税法上はそれを「資産」と判示したものです。
私法との関係で所得税法上、課税対象となり得るか議論が残るところです。例えば、個人株主が、会社から借金をしていて、債務免除を受けた場合、みなし配当の所得税法第25条第1項の規定は適用されるか、といった論点です。
Q4―11 相続開始時に特例有限会社の出資持分であった場合に係る裁判例
- 相続開始時に特例有限会社の出資持分であった場合に係る裁判例について実務上のポイントは何か教えてください。
Answerーーーー
下記になります。
【解説】
- 【みなし配当課税/相続開始時に有限会社の出資持分であった場合】東京高等裁判所平成22年(行コ)第144号誤納金返還請求控訴事件(棄却)(上告)国側当事者・国平成22年9月9日判決
〔ポイント〕
会社法施行により特例有限会社として存続している控訴人A社は、株主乙及び丙がそれぞれ相続により取得した出資持分を、自己の株式として取得するに当たり対価を交付したことに関して、税務署職員から説明を受け、配当等とみなされる部分について源泉所得税を納付した。
本件は、A社が、措置法9条の7に規定する特例(相続財産に係る株式をその発行した上場会社等以外の株式会社に譲渡した場合にはみなし配当所得としない旨の特例)の適用があるとして、源泉所得税の還付等を求めた事案である。
当裁判所も、控訴人の請求は理由がないと判断するが、その理由は、控訴人の当審における主張に対する判断を加えるほかは、原判決の「事実及び理由」欄の「第3 当裁判所の判断」の1 から4までに記載のとおりであるからこれを引用する。
措置法9条の7第1項は、「相続税額に係る課税価格(中略)の計算の基礎に算入された(中略)上場会社等以外の株式会社(中略)の発行した株式をその発行した当該非上場会社に譲渡した場合」であることを同項の適用要件として明記しているものであり、その文理からは、「譲渡した」株式が、「相続税額に係る課税価格(中略)の計算の基礎に算入された」時点、すなわち相続開始時点において、「株式会社(中略)の発行した株式」として存在したことを要件としていることは明らかというべきである。
したがって、本件特例の文理からは複数の解釈が可能であり、上記要件の存在を一義的に読み取ることはできないとの控訴人の主張は採用することができない。
国税庁のホームページに掲載されている質疑応答事例は、納税者からの照会に対して回答した事例等のうち、他の納税者の参考となるものを税目別に掲載しているにすぎないものと認められるのであり、国税庁のホームページの質疑応答事例において、「会社法施行日前に相続した有限会社の出資持分を会社法施行日以後にその会社に譲渡した場合のみなし配当」との標題の下、照会要旨と回答要旨が掲載されているからといって、そのことが、本件特例の文理が一義的に明確でないことの根拠となると認めることはできない。
税務署の職員が、自己株式売買に本件特例の適用があるとの助言を行ったものと認めるに足りる証拠はなく、また、措置法9条の7 第1項について、上記のとおり解釈すべきことは、本件特例新設の経過措置に関する附則の規定と直接関係するものではない。
※上告棄却・不受理
※参考までに下級審の判決を挙げておきます。
- 東京地方裁判所平成21年(行ウ)第278号誤納金返還請求事件(棄却)(控訴)国側当事者・国平成22年3月30日判決
〔ポイント〕
本件は、会社法施行により特例有限会社として存続している原告が、株主乙及び丙がそれぞれ相続により取得した出資持分を、自己の株式として取得するに当たり対価を交付したことに関して、日本橋税務署職員から、上記対価が原告の資本金等の額のうち交付の基因となった株式に対応する部分の金額を超えるため、その超える部分の金額に係る金銭が、所得税法25条1 項により同法24条1項に規定する剰余金の配当等とみなされる一方、租税特別措置法9条の7に規定する特例(相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例)の適用はないとして、その配当等とみなされる部分について所得税を徴収して国に納付しなければならない旨の説明を受けたことから、配当所得に係る源泉徴収による所得税として合計1192万8000円を納付した。
しかし、原告は本件自己株式売買には本件特例の適用があると主張し、各納付に係る金員につき、原告には源泉徴収義務がなく、法律上の原因を欠く納付であったとして、被告に対し、国税通則法56条及び58条1項に基づき還付及び還付加算金の支払を求めている事案である。
措置法9条の7第1項は「相続税額に係る課税価格の計算の基礎に算入された上場会社等以外の株式会社の発行した株式をその発行した当該非上場会社に譲渡した場合」であることを同項の適用要件と明記しているところ、その文理からは、「譲渡した」株式が「相続税額に係る課税価格の計算の基礎に算入された」時点において、「株式会社の発行した株式」として存在したことを所与の要件としていることは明らかである。
相続人が被相続人の財産を取得するのは相続開始時(被相続人の死亡時)である(民法882条、896条本文)ことも併せかんがみると、相続により取得した財産が「相続税額に係る課税価格の計算の基礎に算入され」る時期は、相続開始時であることは明らかであると解される。
これを本件についてみるに、亡乙及び丙は、非上場会社である原告の株式を原告に譲渡したものの、本件相続の開始した平成16年12月9日当時、原告は、有限会社であって、譲渡された株式も、いまだ原告の出資持分にすぎず、原告の発行した株式ではなかったため、譲渡の対象となった株式が、その取得の基因となった相続の開始の時点において、当該非上場会社の発行した株式として存在し、当該株式として「相続税額に係る課税価格の計算の基礎に算入され」たとはいえないから、本件自己株式売買につき措置法9条の7第1項は適用されないというべきである。
実質的な利益衡量の視点から、会社法整備法の施行日の後に相続が開始した事例に関しては、本件特例が適用される一方で、同法の施行日前に相続が開始した事例に関しては、たとえ同法の施行後に自己株式取得がされたとしても、本件特例が適用されないというのは不均衡であるとする原告の主張は、措置法の規定の文理に反してその定めの及ばない場合にまで本件特例の適用範囲を拡大すべき旨を主張するものであって、解釈論の範疇を超えて立法論の領域に属するものといわざるを得ず、措置法の規定の解釈論として所論を採用することはできない。
Q4―12 自己株式の購入価額に係る適正価額とみなし配当に係る公表裁決
- 自己株式の購入価額に係る適正価額とみなし配当に係る公表裁決について実務上のポイントは何か教えてください。
Answerーーーー
下記になります。
【解説】
- 【源泉徴収義務(みなし配当))自己株式の購入価額は適正な価額であるから、資本等の金額のうち取得株式に対応する部分を超える部分については、みなし配当が生じるとした事例】(平21―03―03裁決)【裁決事例集第77集194頁】
〔ポイント〕
請求人は、請求人が取得した自己株式の取得価額について、税法上の適正価額(時価)に比して高額であり、当該高額な部分は本件株式の取得の対価ではなく、請求人にとっては売主に対する寄附金であり、売主にとっては法人からの贈与であるから一時所得になり、みなし配当部分はないから、原処分庁の行った納税告知処分等は違法であると主張する。
しかしながら、その自己株式の取得価額は、①第三者間における合意に基づく売買として成立したものであること、②平成16年当時の請求人の株式の純資産価額は、取得価額より若干低い程度であったこと及び③その自己株式の購入の約1か月前に関連会社から自己株式をおおむね同額で購入していることから、正常な取引に基づく時価、すなわち適正価額と認められ、当該高額な部分はなく請求人の主張は採用できない。
(実務上のポイント)
配当可能利益の制限が会社法であります(会社法461)。違法配当になったとしても、それにより金銭等の交付を受けた者と違法配当に合意した取締役等に、会社に対する賠償責任を負わせているのみであり(会社法462)、自己株式の取得自体は有効のままとされています11。
11 葉玉匡美「会社法であそぼ。」(ブログ)平成17年11月25日違法配当。
Q4―13 事業協同組合員の死亡脱退の払戻請求権とみなし配当に係る裁判例
- 事業協同組合員の死亡脱退の払戻請求権とみなし配当に係る裁判例について実務上のポイントは何か教えてください。
Answerーーーー
下記になります。
【解説】
- 【みなし配当に係る源泉徴収/事業協同組合員の死亡脱退の払戻請求権】東京高等裁判所平成20年(行コ)第285号源泉徴収に係る所得税の納税告知及び不納付加算税の賦課決定取消請求控訴事件(棄却)(確定)国側当事者・国(麹町税務署長)平成20年11月27日判決
〔ポイント〕
・中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合の組合員が死亡した場合の持分の払戻請求権の取扱い
・脱退組合員の持分の定め(原審判決引用)
・組合員の持分の意義(原審判決引用)
・払戻額を制限することができる範囲(原審判決引用)
・控訴人組合の定款を見るに、除名以外の事由によって脱退する組合員は、払戻対象金額を出資口数に応じて算定した金額の持分の払戻請求権を、また、除名により脱退する組合員はその半額の持分払戻請求権を、それぞれ脱退によって当然に取得し、協同組合の財産的基礎を堅実にするために総会決議によって減額される余地はあるものの、その場合でも払込済出資額等より少ない額に減額されることはないと解すべきであるとされた事例(原審判決引用)
中小企業等協同組合法の規定及び控訴人組合の定款によれば、控訴人組合においては、組合員の死亡により、原則として、脱退後の事業年度末日における払戻対象金額を出資口数に応じて算定した金額の持分の払戻請求権が当然に発生し、払込済出資額等以上の額の部分は、総会決議により減額されることがあることをいわば一部解除条件として、死亡した組合員がこれを取得するというべきであるとされた事例(原審判決引用)
死亡により成立する権利が死亡した者にいったん帰属することはあり得ない旨の控訴人組合の主張が、持分払戻請求権は組合員の死亡によって発生する権利であって、およそ死亡によって組合員にいったん帰属することが法律上あり得ないということはできない上、実質的にみても、持分払戻請求権は組合員が有していた持分がいわば金銭に転化したものであって、同一性が認められるから、持分払戻請求権が死亡した組合員にいったん帰属すると解すべきことには合理性が認められるとして排斥された事例(原審判決引用)
控訴人組合の定款により、組合員が死亡した場合、相続人は、死亡した組合員の地位を承継することができ、相続人が組合員の地位を承継しない選択をして初めて脱退の効力が生じるのであるから、払戻請求権は相続人固有の権利である旨の控訴人組合の主張が、控訴人組合の定款の規定ぶりからも明らかなように、中小企業等協同組合法19条1項2号(法定脱退)の規定により組合員の死亡によっていったん脱退の効果が生じることを前提とした上で、組合員である相続人が、被相続人たる組合員の死亡後に加入の申出をした場合に、遡ってその相続人が相続開始の時に組合員となったと「みなす」にすぎないとして排斥された事例(原審判決引用)
控訴人組合の定款は持分払戻額の上限額を定めただけであって、総会決議により初めて具体的な払戻請求権が確定したのであり、その時点において死亡した組合員は権利帰属主体たり得ないから、死亡した組合員の所得として観念することは不可能であるとの控訴人組合の主張が、控訴人組合の定款が持分払戻請求権の上限額を定めたものであるとしても、総会決議により持分払戻請求権を全く剥奪したり、限度額を下回るものとすることは許されないと解すべきであって、脱退者が、その持分払戻請求権を取得すると解すべきであるとして排斥された事例(原審判決引用)
持分払戻請求権は脱退後の事業年度の末日を基準として定められるものであること等から、組合員が死亡した年の事業年度が終了するまでは持分払戻請求権は未だ発生も確定もしていないとの控訴人組合の主張が、実体法上は、一部解除条件付きではあるものの、脱退後の事業年度末日における払戻対象額を出資口数に応じて算定した金額の持分の払戻請求権の発生が確定したといえるとして排斥された事例(原審判決引用)
持分払戻請求権は少なくとも事業年度が終了するまでは確定せず、法律上行使することは不可能であるから、所得税法36条1 項(収入金額)のいういわゆる「権利確定主義」の「確定」の要件を充たしていないとの控訴人組合の主張が、組合員の死亡脱退に伴う持分払戻請求権は、組合員の死亡によって組合員の所得として発生するのであって、組合員が死亡した年の所得として認識されることになることは明らかであり、また、実質的にも、組合に対して、控訴人組合のいうような不可能を強いることにはならないとして排斥された事例(原審判決引用)
控訴人組合において、組合員の死亡による脱退に伴う持分の払戻請求権は、組合員が死亡した時点で確定的に発生し、死亡した組合員に帰属するというべきであるから、その出資金超過額は死亡した組合員の所得となるというべきであるとされた事例(原審判決引用)
中小企業等協同組合法の定めの下での、組合員の持分、あるいはその払戻請求権が、これらの所得税法又は相続税基本通達にいう退職手当金、功労金及びこれらに準ずる給与あるいは賞与、俸給又は給与等に、直接に該当すると解することはできず、いわば組合の純資産に対して組合員が当然に持つべき「分け前」であり、組合員の基本的な権利として位置づけられる性質を有するものであって、実質的にみても、これを雇用契約等から生じる退職手当金、賞与、給与等と同一に扱うべき理由はないとされた事例(原審判決引用)。
本件各賦課決定処分について、組合員死亡時において、持分払戻請求権は支払金額も支払時期も未確定であり、権利確定主義は一定の算定基準となるべき事業年度末すら到来していない時点に適用されないなどとの控訴人組合の主張が、控訴人組合がこれと異なる認識を有していたとしても、国税通則法67条1項ただし書き(不納付加算税)の「正当な理由があると認められる場合」に該当するともいえないとして排斥された事例(原審判決引用)
本件の関連法律に関する解釈は一義的に明確でないところ、その解釈及び行政上の取扱いを一般に国民に対して周知していない状態で、源泉徴収を履行しなければならないとするのには無理があり、源泉徴収に係る所得税を法定納付期限までに納付しなかったことについては正当な理由があるとの控訴人組合の主張が、中小企業等協同組合法の規定から、事業協同組合の組合員が死亡したときは、その組合員が脱退して持分払戻請求権を取得すると解した上で、その払戻金のうち出資金を超える部分については、組合員の所得として所得税が課せられると解することが、法律上、一義的に明確でないとまでいうことはできず、また、その解釈及び行政上の取扱いが一般に国民に対して周知されていないとしても、そのことから直ちに源泉徴収に係る所得税を法定納付期限までに納付しなかったことについて正当な理由があるということはできないとして排斥された事例
※下記が下級審の判断となります。
- 東京地方裁判所平成19年(行ウ)第277号源泉徴収に係る所得税の納税告知及び不納付加算税の賦課決定取消請求事件(棄却)(控訴)国側当事者・国(麹町税務署長)平成20年7月15日判決
〔ポイント〕
・中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合の組合員が死亡した場合の取扱い
・脱退組合員の持分の定め
・組合員の持分の意義
・脱退組合員に対する持分払戻額を制限できる範囲
・中小企業等協同組合法の規定及び原告組合の定款によれば、原告組合においては、組合員の死亡により、原則として、脱退後の事業年度末日における払戻対象金額を出資口数に応じて算定した金額の持分の払戻請求権が当然に発生し、払込済出資額等以上の部分は、総会決議により減額されることがあることをいわば一部解除条件として、死亡した組合員がこれを取得するというべきであるとされた事例
・死亡により成立する権利が死亡した者にいったん帰属することはあり得ないとの原告組合の主張が、持分払戻請求権は組合員の死亡によって発生する権利であって、およそ死亡によって組合員にいったん帰属することが法律上あり得ないということはできない上、実質的にみても、持分払戻請求権は組合員が有していた持分がいわば金銭に転化したものであって、同一性が認められるから、持分払戻請求権が死亡した組合員にいったん帰属すると解すべきことには合理性が認められるとして排斥された事例
・原告組合の定款により、組合員が死亡した場合、相続人は、死亡した組合員の地位を承継することができ、相続人が組合員の地位を承継しない選択をして初めて脱退の効力が生じるのであるから、払戻請求権は相続人固有の権利であるとの原告組合の主張が、原告組合の定款の規定ぶりからも明らかなように、中小企業等協同組合法19条1項2号(法定脱退)の規定により組合員の死亡によっていったん脱退の効果が生じることを前提とした上で、組合員である相続人が、被相続人たる組合員の死亡後に加入の申出をした場合、遡ってその相続人が相続開始の時に組合員となったと「みなす」にすぎないとして排斥された事例
・原告組合の定款は持分払戻額の上限額を定めただけであって、総会決議により初めて具体的な持分払戻請求権が確定したのであり、その時点において死亡した組合員は権利帰属主体たり得ないから、死亡した組合員の所得として観念することは不可能であるとの原告組合の主張が、原告組合の定款が持分払戻請求権の上限額を定めたものであるとしても、総会決議により持分払戻請求権を全く剥奪したり、限度額を下回るものとすることは許されないと解すべきであって、脱退者が、その持分払戻請求権を取得すると解すべきであるとして排斥された事例
・持分払戻請求権は脱退後の事業年度の末日を基準として定められるものであること等から、組合員が死亡した年の事業年度が終了するまでは持分払戻請求権は未だ発生も確定もしていないとの原告組合の主張が、実定法上は、一部解除条件付きではあるものの、脱退後の事業年度末日における払戻対象額を出資口数に応じて算定した金額の払戻請求権の発生が確定したといえるとして排斥された事例
・持分払戻請求権は少なくとも事業年度が終了するまでは確定せず、法律上行使することは不可能であるから、所得税法36条1 項(収入金額)のいういわゆる「権利確定主義」の「確定」の要件を充たしていないとの原告組合の主張が、権利確定主義は、当該所得が1 つの権利義務の主体のどの年の所得として認識されるべきであるかという所得の年度帰属の問題であるところ、組合員の死亡脱退に伴う持分払戻請求権は、組合員の死亡によって組合員の所得として発生するのであって、組合員が死亡した年の所得として認識されることになることは明らかであるとして排斥された事例
・出資持分の払戻しは、組合員が生前組合活動に貢献してきた代償としての死亡退職金や賞与に類似する性格を持つから、死亡後3 年以内の支給が確定した死亡退職金、賞与や、支給期が到来していない給料等と同様に、相続財産として扱われるべきであり、所得税を課すべきでないとの原告組合の主張が、中小企業等協同組合法の定めの下での、組合員の持分、あるいはその払戻請求権は、所得税法9条1項15号(非課税所得)又は相続税基本通達3―32(被相続人の死亡後確定した賞与)、3―33(支給期の到来していない給与)にいう退職手当金、功労金及びこれらに準ずる給与あるいは賞与、俸給又は給与等に直接に該当すると解することはできず、いわば組合員の基本的な権利として位置づけられる性質を有するものであるとして排斥された事例
(実務上のポイント)
当該案件の基本的な考え方は持分あり医療法人と同じです。ここでは権利確定主義について考えます。権利確定主義と実現主義について、平成5年11月25日最高裁判決の検討を通じて整理してみます。
当該判決の権利確定主義は、以下について特徴があります。原則としては、法的な権利関係を基準として考えるべきものですが、当該判決においては、「取引の経済的実態からみて合理的なものとみられる収益計上の基準の中から、当該法人が特定の基準を選択し、継続してその基準によって収益を計上している場合には、」そのような処理も是認すべきとして、処理基準について、取引の経済的実態も考慮して、一定の幅を持たせていることに留意する必要があるという論者もおります。
当該判決の権利確定主義は、法律的基準だけに基づいて判断する純粋の権利確定主義とは異なるが、販売という事実ではなく、対価として収入すべき権利に着目している点で、権利確定主義の基本的考え方は堅持しているといえます。
経済的整理と法的整理を分類された見解といえます。「選択」と「継続」で実質判断します。
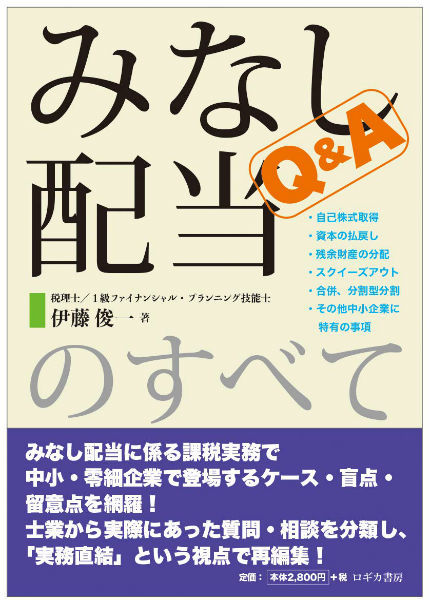
※画像をクリックするとAmazonに飛びます



















