
(本記事は、伊藤 俊一氏の著書『Q&Aみなし配当のすべて』=ロギカ書房、2020年7月31日刊=の中から一部を抜粋・編集しています)
Q4―1 判例・裁判例・裁決での焦点
- 過去の判例・裁判例・裁決では何が焦点になっているか、教えてください。
Answerーーーー
下記になります。
【解説】
株主等の拠出部分と法人稼得利益との峻別という、法人税法の考え方を整理したものが現行法のみなし配当課税です。しかし、配当を認識するという次元の議論で、法人から株主への利益移転(配当)をどのように規律するのかという、初歩的問題が論点になっていることが多いという特徴があります。
この結果、論点は
①そもそもみなし配当に該当するか(付随して資本金等の額と利益積立金額の峻別)
②(①の補助論点として)源泉徴収義務は発生するか
に収斂されます。
過去の判例・裁判例・裁決では、①みなし配当該当性について広く解釈される傾向にあります。これは他の租税法における論点でも全く同様に言えますが、経済的実質に着目し、その本質からみなし配当該当性を認定するアプローチを指します。
しかし、実質主義課税の原則は事実上の類推解釈を許容する恐れがあるため、近年の裁判例では射程が極めて小さくなっていると考えます。租税法の解釈原理は第一に文理であることは判例、学説、実務通説でも明らかであり、その事実上の逸脱に近いものである実質主義課税の原則は、古くから批判が多いものでした。そういった批判を反映してか、最近の判例ではその傾向が減少していることは筆者も望ましい傾向であると考えております。
Q4―2 判例・裁判例・裁決から示唆されるポイント
- 過去の判例・裁判例・裁決から示唆される実務上のポイントは何か教えてください。
Answerーーーー
下記になります。
【解説】
過去の判例・裁判例・裁決については、前章までで述べたみなし配当の解釈について、経済的実質にそって、広く解釈していることが共通点として挙げられます。
本書に挙げたようなみなし配当事由はもちろんのこと、その経済的実質を常に考慮し、みなし配当事由に該当するかどうかを実質的アプローチで検証する必要性はあります。それもできるだけ広く解釈することが実務上のポイントでしょう。
法人税基本通達1―5―4 は「法人が剰余金の分配又は利益の処分により配当又は分配したものだけではなく、株主等に対し、その出資者たる地位に基づいて供与した一切の経済的利益を含むものとする」とあります。
東京地裁平成23年5月31日判決では、裁判所の判断として「株主等の地位に基いて供与された利益」について、「株主に対し、取引上の債権債務関係など他の原因がないにもかかわらず供与されたものであればこれを満たすと解するのが相当である」と判示しています。
これは経済的利益の移転を配当と認定する要件として非常に広範囲に認定されるおそれがあることを示す意味で留意すべき判示といえます。
完全支配関係であれば、損益認識は繰り延べられますが、それ以外の同族関係者間の取引については、損益取引であるみなし配当認定がなされる可能性はつきまといます。
法人税法第23条に規定する「配当等の額」は、内国法人からの配当のみが益金不算入となり、外国法人からの受取配当金は益金算入となります。
これに対して法人税法第24条に規定する「みなし配当」には外国法人から受けるものについても益金不算入です。
Q4―3 過去の判例・裁判例・裁決から示唆される今後の動向について実務上のポイント
- 過去の判例・裁判例・裁決から示唆される今後の動向について実務上のポイントは何か教えてください。
Answerーーーー
下記になります。
【解説】
2点挙げます。
1点目は外国法人からの払戻しです。
一部の実務家、研究者においては、発行法人による資本金等の計算を前提に精緻に作られた制度は、外国法人からの払戻しを規律するには執行上の問題を抱えていると指摘されてきました。
2点目は残余財産分配です。
清算中事業年度において役員退職金支給する場合があり、単に金額が過大であれば損金不算入の問題として処理されます。しかし、オーナー役員の場合で、解散後相当期間を経過してから支払いが行われた場合、当該支払いの実質が役員退職金ではなく残余財産の分配と認定される可能性もあります。
Q4―4 外国子会社の残余財産の分配に係るみなし配当の額の計算における資本金の額は、確定決算において資本金として計上された金額を意味すると解するとする公表裁決
- 外国子会社の残余財産の分配に係るみなし配当の額の計算における資本金の額は、確定決算において資本金として計上された金額を意味すると解するとする公表裁決について実務上のポイントは何か教えてください。
Answerーーーー
下記になります。
【解説】
- 【受取配当金の益金不算入の特例 残余財産の分配に係るみなし配当の額の計算における資本金の額は、確定決算において資本金として計上された金額を意味すると解するのが相当であるとした事例】(平28―03―25公表裁決)(TAINZ コード J102―3―11)
〔ポイント〕
本事例は、外国子会社の残余財産の分配に係るみなし配当の額の計算における資本金の額は、確定決算において資本金として計上された金額を意味すると解するのが相当であるとしたものである。
《要旨》
請求人は、外国の子会社(本件子会社)の残余財産の分配に係るみなし配当の額の計算において、法人税法施行令第23条《所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等》第1 項第3 号でいう直前資本金額等は、請求人が本件子会社に払い込んだ米ドルで表示された金額に基づき算定すべきである旨主張する。
しかしながら、直前資本金額等とは、残余財産の分配を行った法人の当該分配の直前の資本金等の額をいうものであるところ、資本金の額については、法人税法に資本金等として払い込まれた額又は法人の財務諸表に表示された額のいずれをいうのかを判断するための明確な定義が置かれていないことから、会社法における資本金の額、すなわち、確定決算において資本金として計上された金額を意味すると解するのが相当であり、本件における直前資本金額等は、本件子会社の貸借対照表に資本金として計上された人民元で表示された金額に基づき算定するのが相当である。
Q4―5 平成22年7月6日の生保年金二重課税事件を踏まえたあとのみなし配当に関する裁判例
- 平成22年7月6日の生保年金二重課税事件を踏まえたあとのみなし配当に関する裁判例について実務上のポイントは何か教えてください。
Answerーーーー
下記になります。
【解説】
- 【相続税と所得税の二重課税/清算手続結了前の株式の相続と清算後のみなし配当】大阪地方裁判所平成24年(行ウ)第292号通知処分取消請求事件(棄却)(控訴)国側当事者・国(阿倍野税務署長)平成27年4月14日判決
〔ポイント〕
原告らは、相続により取得したA株式(破産手続中のA社に係るもの)の株主として受領した残余財産分配金に係る所得のうち資本金の額を除いた分を所得税法25条1項3号のみなし配当金として配当所得の金額に計上して平成22年分所得税の確定申告をした。
本件は、原告らが、上記みなし配当金に係る所得は原告らが相続により取得した上記株式の基本権である残余財産分配金を受ける権利が実現したものの一部にすぎず、同法9条1項16号の規定(非課税規定)により所得税を課されないとして、更正の請求をしたところ、更正をすべき理由がない旨の通知処分を受けた事案である。
所得税法9条1項柱書の規定によれば、16号にいう「相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの」とは、相続等により取得し又は取得したものとみなされる財産そのものを指すのではなく、当該財産の取得によりその者に帰属する所得を指すものと解される。そして、当該財産の取得によりその者に帰属する所得とは、当該財産の取得の時における価額に相当する経済的価値にほかならず、これは相続税又は贈与税の課税対象となるものであるから、同号の趣旨は、相続税又は贈与税の課税対象となる経済的価値に対しては所得税を課さないこととして、同一の経済的価値に対する相続税又は贈与税と所得税との二重課税を排除したものであると解される(平成22年最判参照)。
原告らは相続税の申告において、A株式の資本金に相当する金額を「有価証券」として申告するほかに、「その他の財産」(未収入金)として本件各分配金の見込み額のうち資本金の額を超える部分を申告していたことが認められる。
しかしながら、A社は相続開始当時、未だ破産手続が行われており、清算手続の開始前であって、債務も確定されておらず、残余財産の有無やその額も確定していなかったことからすれば、残余財産分配請求権を基礎とする本件各分配金に係る債権が既に具体的に発生していたということはできない。
原告らが相続により取得したA株式の評価を本件各分配金の見込み額としたことは、相続時におけるA株式の時価を客観的に評価する上で、清算による残余財産分配見込金の推計をすることとし、具体的には、清算手続開始後に見込まれる不動産の売却等に係る収入や固定資産税の納付等に係る支出及び清算所得に対する税額などを加減算して計算した結果にすぎず、かかる事実をもって、原告らが未だ具体的には発生していない本件各分配金に相当する経済的価値を相続によって取得したということはできない。
そうすると、原告らが相続によって取得したのはあくまで株式というべきであり、本件各分配金に相当する経済的価値を相続によって取得したということはできない。
所得税法25条1項3号のみなし配当課税は、株主等が法人の清算によってそれまで当該法人に留保されていた利益を残余財産の分配として受けたことを課税対象とするのであるから、当該法人の株式を相続人が相続した場合における株式についての相続税の課税とは課税対象を異にするものであるし、また、上記みなし配当課税は法人に留保されていた利益の分配を原因として実現した経済的利益を課税の原因とするものであるから、上記みなし配当課税の対象となる経済的利益は、非課税規定にいう相続等を原因として取得したものということはではない。
したがって、清算手続結了前の株式を相続した場合に当該株式について相続税を課すことと、清算後に生じる留保利益の分配を原因としてみなし配当課税をすることが、非課税規定によって禁止される二重課税に当たるということはできない。
(実務上のポイント)
平成22年7月6日の生保年金二重課税事件が射程内です。
資産の価値は「将来キャッシュフローの割引現在価値の総和」と観念するファイナンスの視点が理解に有益です。
当該判決では①元本部分と②運用益部分から構成されており、相続税の課税対象は①元本部分、所得税の課税対象は②運用益部分と結論付けています。
そして①元本部分は相続税が課税済みであることで所得税法9 条1項15号(現16号)により所得税が非課税であると示しました。
Q4―6 従業員持株会からの自己株式による代物弁済に係るみなし配当該当性に係る裁判例
- 従業員持株会からの自己株式による代物弁済に係るみなし配当該当性に係る裁判例について実務上のポイントは何か教えてください。
Answerーーーー
下記になります。
【解説】
- 【みなし配当に係る源泉徴収義務/従業員持株会からの自己株式による代物弁済】大阪高等裁判所平成23年(行コ)第65号所得税納税告知処分取消等請求控訴事件(棄却)(上告・上告受理申立て)国側当事者・国(処分行政庁 東税務署長)平成24年2月16日【訟務月報58巻11号3876頁】
〔ポイント〕
本件は、株式会社である控訴人A社が、その従業員持株会A持株会から貸付金321億2973万5400円につき、A社の発行済株式793万3268株により代物弁済を受けたところ、処分行政庁から、当該代物弁済により消滅した債権のうち、取得した株式に対応する資本等の金額を超える部分281億4184万0242円は「みなし配当」に該当し、A社には所得税法181条1 項に基づく源泉徴収義務があるとされて納税告知処分等を受けたため、これらの処分の取消しを求めたのであって、原審はA社の請求を棄却したため、これを不服として控訴したという事案である。
所得税法25条1項に定めるみなし配当の趣旨は、形式的には法人の利益配当ではないが、資本の払戻し、法人の解散による残余財産の分配等の方法で、実質的に利益配当に相当する法人利益の株主等への帰属が認められる行為が行われたときに、その経済的実質に着目して配当とみなして株主等に課税するところにあるというべきである。
この趣旨に鑑みると、同柱書きにいう「金銭その他の資産の交付を受けた場合」とは、金銭その他の資産が実際に交付された場合だけでなく、同様の経済的利益をもたらす債務の消滅等があった場合も含むと解するのが相当である。
所得税法181条1項の源泉徴収義務者の規定は、文理上、「配当等の支払」をする者が源泉徴収義務者となるという趣旨であり、それ以上に「配当等」と「支払」を分けた上、「支払」とは、源泉徴収義務者自身が株主等に対して負う支払債務を消滅させる場合に限られると解する根拠は、見当たらない。
他方、所得税法25条1項の趣旨によれば、みなし配当に該当する場合において、「配当等の支払」とみるべきものは、同法25条1 項によって配当等とみなされる、株主等に経済的利得を帰属させる行為であり、本件代物弁済が株主等に経済的利得を帰属させる行為である以上、同法181条1項にいう「配当等の支払」に当たるというべきである。
A社は、自己の株式を時価を超える取引で取得する場合には、時価を超える部分については、取引の対価すなわち「配当の額とみなす金額」に当たらないと主張するが、所得税法25条1 項柱書きには「配当等の額とみなす金額」を算定するに当たり、取得の対象とされた自己株式のうち、会社の利益積立金又は商法上の利益剰余金に対応する額(時価相当額)に限定されることを窺わせる文言はないから、上記主張は理由がない。
A社は、未配分株式のみならず、配分済株式についても、民法上の組合を前提としたパススルー課税の取扱いがされていないと主張するが、本件持株会が「名義人受領の配当所得の調書」あるいは「信託の計算書」のいずれを提出していたかによって、民法上の組合を前提としたパススルー課税の取扱いがされるかどうかとは直接結びつかないから、A社の主張には理由がない(A社の従業員が昭和63年12月26日、税務相談の際に本件持株会が管理信託の方法を採用することを告げていたことは認められず、このことを前提として東税務署長から誤った指導を受けたとはいえない。)。
従業員持株会の法的性格を確定するに当たっては、当該持株会の運営実態等に照らして、当事者の意思を合理的に解釈することになるが、本件持株会においては、未配分株式及び配分済株式の取扱い等によれば、本件持株会が民法上の組合であることを前提とした運営がされていたと認められ、A社の主張は理由がない。
※上告棄却・不受理
(実務上のポイント)
高裁判示では「実質的に利益配当に相当する法人利益の株主等への帰属が認められる行為」及び「現実に交付された「金銭等の額」等に基づいて、みなし配当の額を計算することを予定しているというべきである」があります。高裁では地裁から一転して文理解釈を強調していることが見て取れます。対価性を有する部分とその他の部分に区分することを認めなかったわけです。
たとえ交付された金銭等の額が株式の時価と乖離している状況でも、現実に交付された金銭等の額を用いてみなし配当額の計算をすべきと判示したことになります。
もっとも、高裁が所得税法第25条第1 項において「実質的に利益配当に相当する法人利益の株主等への帰属が認められる行為が行われたとき」を想定しているので、原告の主張に対して反論できる余地はあったように思えるという見解もあるようです。
Q4―7 所得税、相続税の二重課税とみなし配当該当性に係る公表裁決
- 所得税、相続税の二重課税とみなし配当該当性に係る公表裁決について実務上のポイントは何か教えてください。
Answerーーーー
下記になります。
【解説】
- 【(非課税所得(相続等により取得するもの))相続によって取得した株式の発行会社から交付を受けた残余財産分配金のうち、剰余金の配当とみなされる金銭は、非課税所得には該当しないとした事例】(平24―11―14公表裁決)
〔ポイント〕
本事例は、破産手続中であった株式会社の株式を相続により取得し、当該株式に係る分配見込額を時価として相続税の課税対象とされたものについて、その後、当該株式の発行会社から交付を受けた残余財産分配金のうち剰余金の配当とみなされる金銭は、所得税法第9 条《非課税所得》第1 項第16号の非課税所得には該当しないとしたものである。
請求人らは、各みなし配当金(請求人らが相続によって取得した株式の発行会社から交付を受けた残余財産分配金のうち、剰余金の配当とみなされる金銭)は、所得税法第9 条《非課税所得》第1 項第16号の非課税所得に該当する旨主張する。
しかしながら、①上記規定にいう「相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの」とは、相続を直接の原因として相続人の下で実現した所得に限られ、相続後に相続とは別の原因で相続人の下で実現した所得は該当しないと解するのが相当であるところ、本件において、各みなし配当金を取得したことによって請求人らに帰属した所得は、相続後3年以上の期間が経過してから、相続とは別の事由、すなわち、上記会社の清算手続において、債務を完済し、残余財産が最終的に確定したことによって、初めて請求人らの下で実現したものであり、また、相続の開始時には各みなし配当金の支払原因となる具体的な残余財産分配請求権は確定的に発生していなかったから、相続を直接の原因として実現があったものとできないことや、②上記各みなし配当金が「相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの」に該当するためには、各みなし配当金の額に相当する経済的価値が、相続開始時における上記株式の価値に相当する経済的価値と同一のものと評価できることが必要となるところ、上記会社については、相続の開始後に収支及び資産の状況に種々の変動があり、当該変動後の最終的な清算価値を具現化した残余財産分配金の額に相当する経済的価値は、当該変動前の清算価値に基づいて評価された上記株式の価額に相当する経済的価値と同一と評価できないことからすれば、上記各みなし配当金が「相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの」に該当すると認めることはできない。
(参考判決・裁決)
最高裁平成22年7月6日第三小法廷判決(民集64巻5号1277頁)
(実務上のポイント)
二重課税の射程の論点です。
相続人が所得税法第60条第1項により取得費を引き継いだ相続財産を譲渡した場合、相続財産を譲渡した場合の譲渡所得課税が問題となります。
この点、被相続人の保有期間中に生じた未実現の増加益については相続税が課されるため、相続人の保有期間中に生じた増加益に対してのみ所得税を課すべきという見解もあります。
下級審裁判例では「所得税法は、被相続人の保有期間中に…(筆者中略)…発生し蓄積された資産の増加益について…(筆者中略)…相続人に対する相続税の課税対象となることを予定していると解される」(東京地判平成25年7月26日)とあります。なお、平成23年度税制改正で当該論点につきましては、確認的規定として所得税法第67条第4 項を設けました。
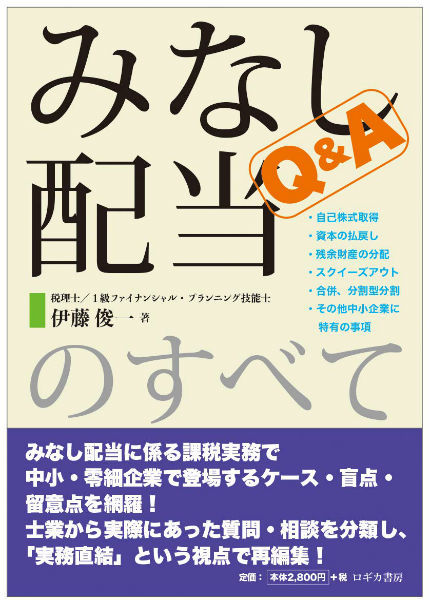
※画像をクリックするとAmazonに飛びます
- ”みなし配当”とは?経営者が知っておくべき基本を解説
- 知らないと恥ずかしい「みなし配当の計算方法」
- 経営者が知っておくべき社員の退社・脱退とみなし配当にかかわる考え方
- みなし配当にかかわる裁判では何が焦点になる?判例の傾向を紹介
- 判例から学ぶみなし配当の事例6選 相続の参考になる?




















