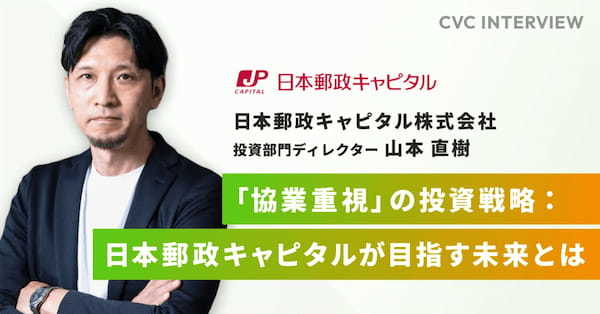
日本最大級の事業アセットを持つ日本郵政グループのCVC(コーポレート・ベンチャー・キャピタル)、日本郵政キャピタル株式会社。今回のCVCインタビューでは、同社の投資部門ディレクターを務める山本直樹さんにお話を伺いました!
このインタビューでは、山本さんが食品メーカーから日本郵政グループに転身し、現在のCVC投資の最前線に立つまでのキャリアや、日本郵政キャピタルが「協業重視」の投資に注力する背景についてお話しいただきました。
2024年4月時点で、90社を超える国内外のスタートアップ企業へ出資しており、グループの幅広い事業アセットを活かした独自の協業創出モデルで、スタートアップとのシナジーをどのように産み出しているのか、その取り組みを追います。
| STARTUP LOGでは、VC/CVC・投資家のみなさまの活動紹介を行い、スタートアップ関係者にとって有益な情報提供をさらに拡充していきます。 ご興味を持っていただけたら、フォローやシェアをお願いします! |
山本直樹さんのキャリアパス
ーまず山本さんのキャリアについてお伺いできますか?
私が大学を卒業して新卒で入ったのは、実はこの業界とは関係のない食品メーカーでした。そこでは営業企画やマーケティング、業務統括など様々な業務を経験しました。同社の支社にいた当時は業務部門のヘッドという形で業務に携わっていましたが、単純にバックヤード業務だけでなく支社全体のマネジメントや営業企画等も行う司令塔のような役割で、支社を全国ナンバーワンに導きました。
その後、日本郵政が民営化して半年後くらいのタイミングの2008年に日本郵便に入社しました。日本郵便では郵便事業や物販事業の営業推進、事業開発などを担当し、日本郵政キャピタルに異動する前は、主に新規事業の開発に注力していました。現在は投資案件のリーダーや協業創出、マーケティングリーダーなどを担当しています。
ー食品メーカーから日本郵便への転職、また日本郵政キャピタルへの異動の経緯を教えてください。
食品メーカーから転職する際は、他の世界も見てみたいという知的好奇心が勝っていました。ちょうど日本郵政が民営化するというタイミングで、官から民へ変わるという大きな変革期でもあったので、今までにない新しい経験ができるのではないかという期待をもって入社しました。
日本郵政キャピタルへは、当時の社長や専務と面識があったことから声をかけていただきました。今は日本郵便から日本郵政キャピタルに完全移籍しています。日本郵政キャピタルは、仕事の幅が広く日本郵政グループだけではなく「日本全体を良くし得る」という点に魅力を感じ、完全移籍することを決めました。
ーキャピタリストとしての知識はもともとお持ちだったのですか?
キャピタリストとしての知識という点では、入社当初はBSやPLが読める程度のレベルでした。入社後に様々な本を読んだり、社内外のいろいろな方とコミュニケーションを取ったりして知識を身につけていきました。手を動かしながら情報をキャッチアップしていったという感じです。

日本郵政キャピタルの設立背景と目的
ーCVCの設立背景と目的について教えてください。
設立当初は、新たな収益を求めた投資会社の色合いが強かったですが、約3〜4年前から完全に「協業重視の投資」をするCVCへと軌道修正しました。現在は「育てるCVC」として、多数の協業を産み出すCVCとなっています。
当社は、事業部起点で活動をしています。社内では「インナーマーケ」と呼んでいますが、事業会社やグループ子会社などに対して定期的に課題をヒアリングしたり、当社の活動を発信したりしています。事業部としての課題だけでなく、キーマンの課題や困りごとを起点としてスタートアップをソーシングするので、事業部やキーマンの課題にフィットしたスタートアップを紹介できます。
ー現在の目的はどのようなものでしょうか?
現在は、当社の出資により日本郵政グループの既存事業へどのような付加価値がもたらされるか、又は新規事業の種となり得るかが重要です。もちろん、一定の財務リターンも必要ですが、戦略リターンは常に議論となります。
日本郵政グループは日本郵政という持株会社の下に日本郵便、ゆうちょ銀行、かんぽ生命保険という主要事業会社があり、更にその下にも多数の子会社があります。例えば福利厚生やバックオフィスBPOを提供する子会社、物流のマテハン機器や車両を保守・メンテナンスする子会社、石油を供給する子会社、コールセンターを運営する子会社など、外から見ただけでは想像できない幅広い事業アセットを持っています。そういった事業アセットとスタートアップの技術やサービスを掛け合わせてどのような協業を創出していくかが当社のミッションです。
投資戦略と判断基準
ー投資先の判断基準について、どのような点を重視していますか?
ステージごとに判断基準が異なります。私の判断基準では、シードやアーリーでは、サービスが顧客ニーズとマッチするか、市場が伸びているか、独自性があるかといった点と、経営者自身の人柄及び一緒に協業を進めていく意欲があるか等を重視します。ミドルやレイターになると、財務指標もしっかりと見ていきます。
ー具体的な投資プロセスについて教えてください。
当社は基本的に個人で動くのではなく、チームで動いています。新しい出資先候補のお話をいただいたら、リーダー・協業担当・ファイナンス担当の3人1組で面談を行い、様々な視点から評価を行っています。
面談後、事業部等とも引合わせをして、事業部等も「面白いから検討する」という反応であれば詳細なDDに進みます。チーム内でDDを行い、問題なさそうであれば、投資委員会に付議します。投資委員会では途中でスタートアップの経営陣からのプレゼンも受けつつ、担当者が投資委員へプレゼンを行います。
その後、法務と財務でプロフェッショナルDDを約1ヶ月かけて実施し、その結果も踏まえ、問題がなければ最後に取締役会で決議し、承認されれば投資実行となります。投資プロセスだけで約3ヶ月かかるというイメージです。
ーこのプロセスはシード、レイターどちらでも同じですか?
その通りです。どのステージでも同じプロセスで進めます。
ーシードの割合が増えている背景は何でしょうか?
ミドルやレイターだけに限定していると、シードやアーリーで良い技術やサービスを持つスタートアップを見逃してしまう可能性があります。そういった企業もしっかりと幅広く検討し、グループに何らかの戦略リターンを還元していきたいという意図があります。また、ミドルやレイターは投資倍率が低くなりがちなので、シードやアーリーもポートフォリオに混ぜることで、最終的な財務リターンも確保したいという狙いもあります。
ーシードではリード投資が多いのでしょうか?
協業や事業成長の可能性に応じて金額やリード/フォローの立場を決めていきます。
ー成長が期待できる企業をどのように見極めていますか?
キャピタリストにもそれぞれの得意分野があります。案件に応じてその領域に強いメンバーを担当にして検討チームを組成し、プロとしての目利きにより成長を見極めています。
スタートアップへの支援
ースタートアップへの支援について特徴的な点を教えてください。
CVCに対してスタートアップが最も期待するのは協業だと思います。出資前に企図した協業を、出資後に事業部等を巻き込み、確実に進めていくことが重要です。
そのために当社は「ステアリングコミッティ」と呼ぶ仕組みを導入しています。事業部等とスタートアップと当社の三者で、少なくとも月に1回はミーティングを設定し、当社がハンドリングしながら双方のNEXTアクションを明確にして、次のステアリングコミッティにつなげていきます。
その他にも、出資先のニーズに応じて、財務面でのサポートや事業戦略の解像度を高める支援なども行っています。
ー協業の具体例として、スタートアップの営業支援なども行っていますか?
はい。たとえば、ACROVEさんが提供するECサイト横断分析ツール「ACROVE FORCE」とは、物流需要がECの成長に比例して拡大するという構造に着目し、当社グループと共同で顧客への提案活動(営業)を展開するスキームを構築しました。この取り組みにより、双方にとって実効性のある協業モデルが実現しています。
さらに、そのスキームを応用し、shizaiさん(梱包資材の最適化プラットフォーム)とは相互送客の形での連携を進めており、出資後間もないにもかかわらず、すでに具体的な成果が出始めています。
ー多くのCVCが協業に苦労している中で、協業が実際に機能している理由は何でしょうか?
インフォーマルコミュニケーション(懇親会)もうまく使い、泥臭くやっています。協業には信頼関係と継続的なコミュニケーションが不可欠であり、当社は潤滑油として双方の立場に立ち、ステアリングコミッティの場などで丁寧な仲介役を担っています。 日本郵政グループは社員約37万人を擁する大規模組織であり、新たな取り組みを進めるには調整や連携が必要な場面も少なくありません。そうした中で、関係者と丁寧に対話を重ね、実行フェーズまで着実に導いていくノウハウと体制を築いてきたことが、当社の強みとなっています。
重点投資領域と200億円ファンド
ー重点的に投資されている領域はありますか?
先ほども説明したように、当社は幅広い事業アセットを持っていて、外からは想像できないような事業も多く行っています。そのため、グループの事業アセットに相性が良く、スタートアップの成長支援にも繋がるのであれば、特に投資領域は絞っていません。
実際に出資したスタートアップを見ても、物流・製造現場の作業を自動化する「Mujin」さん、建設業界のマッチングプラットフォームを展開する「助太刀」さん、スポーツ業界のインフラを目指す「Ascenders」さん、テクノロジーで無人運営を可能にした民泊施設の運営を行う「matsuri technologies」さんなど、非常に多種多様です。外から見ただけでは想像できない協業が生まれる可能性があるので、まずは気軽に相談してほしいと思います。
ー昨年200億円のファンドを組成された背景や目的を教えてください。
2024年3月に総額200億円のファンドを組成しました。GPは日本郵政キャピタル、LPは日本郵政です。
ファンド設立の理由は、投資を活性化するためです。ファンド化によりバルク(一括)で評価できるようになったことから投資案件の柔軟性も高まり、また、大きな金額の意思決定が早まりました。
ー2号ファンドの予定はありますか?
基本的にはそのような形にしていきたいと思っていますが、1号ファンド設立から間もないので、まずは足許で出資を優先しています。
ーセカンダリー投資についてはどのようにお考えですか?
セカンダリーもやっていますし、実際にセカンダリーで投資した案件もあります。投資方針とマッチすれば、拘りはありません。
投資実績と協業事例
ー特に印象的だったスタートアップや協業事例はありますか?
一つに絞るのは難しいですね。
いくつか例を挙げると、当社の出資先でエーアイスクエアさんというコールセンターの効率化に取組むスタートアップがいらっしゃいますが、日本郵政グループでは事業ごとにコールセンターを持っているため、一つのスタートアップでも複数個所で事例が生まれています。
また、助太刀さんが事業を行っている建設業界は、かんぽ生命保険の法人顧客と相性が良く、助太刀さんをうまく使った法人営業を行っています。これは外から見ると全く想像できない協業ですよね。
それぞれの案件に特徴があり、どれが特に良かったというよりは、協業の事例を増やすことの方が重要だと思います。
ー投資先スタートアップの出口戦略についてはどのようにお考えですか?
どちらかというとIPOが多いですね。当社は、協業がうまくいっていればIPO後も株式を保有し続けています。例えば、モンスターラボさんは、ある事業部でのソフトウェア開発が評判となり、他の事業部にも広がるという好循環が産まれています。そのため、現在でも保有し続けています。
今後の展望とメッセージ
ー今後の展望やビジョンについて教えてください。
当社は、いろいろな仕組みやノウハウが蓄積されてきたので、それらを活かしてさらに投資にアクセルをかけていきたいと考えています。
ー業界の課題や、御社が感じている課題はありますか?
業界の課題として、最近ではCVCの重要性が認識されつつあります。シードステージではVCが財務面をサポートし、成長していくためには協業を産み出せるCVCのサポートが重要だと思います。ただ、日本ではスタートアップが自力でスケールするにはまだまだ環境面での制約も多く、大企業が自らのアセットやネットワークを開放し、スタートアップとともに課題解決に取り組む姿勢が求められていると感じています。
そういった中で、「協業がうまくできなくて悩んでいる」といった声を他のCVCさんから聞きます。当社としては、当社のノウハウを他のCVCさんにも提供し、CVC全体が良くなることでスタートアップも発展し、日本が良くなるような世界観を作りたいと考えています。もし、当社の取組みに興味があるCVCさんがいらっしゃいましたら、是非お声がけください。
ー起業家やスタートアップへのメッセージをお願いします。
日本郵政グループは本当に幅広い事業アセットを持っているグループ企業ですので、想像していないことが起こる可能性は十分にあります。何が産まれるか分からないので、まずは、気軽にドアノックして欲しいと思います。
ー山本さん、本日は貴重なお話をありがとうございました!
山本さんが描く「協業重視の投資戦略」と、日本郵政グループの多様な事業アセットを活かしたスタートアップとの共創が、これからも日本のCVC業界とスタートアップエコシステム全体にとって大きな指針となることでしょう!





















