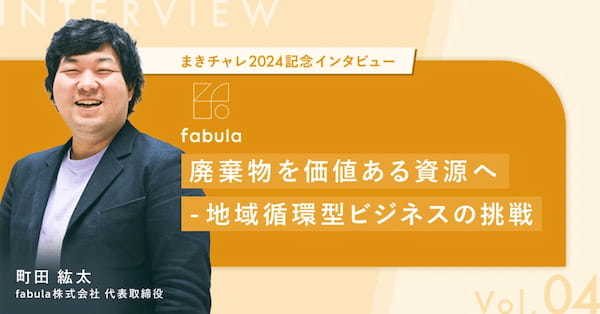
2024年11月、第3回牧之原市チャレンジビジネスコンテスト(以下、まきチャレ2024)の表彰式が開催されました。
まきチャレ2024は、牧之原市の「産業資源」と「観光資源」を活用して、自らの事業を地域と共に発展させるビジネスプランを全世界のスタートアップ企業から募集し、評価するビジネスコンテストです。
昨年に引き続き、第3回開催である今回もEXPACT代表の髙地が審査員として参画しました。
本記事では、まきチャレ2024で大和ハウス工業賞を受賞されたfabula株式会社の代表・町田氏に、企業の成り立ちやビジョン、まきチャレでの提案内容、今後の展望についてお話を伺いました。
起業の背景とfabulaの理念
ー本日は貴重なお時間をいただきありがとうございます。まずはじめに、町田さんのご経歴と、fabula株式会社の設立に至った背景についてお聞かせください。
町田: もともと私は大学時代に素材の研究をしていました。工学部社会基盤学科に所属し、「企業がやらない研究をしたい」という指導教官の言葉に共感し、独自の素材開発に取り組みました。卒業後、半年ほど経った2021年10月に起業しました。当初から、研究した素材の社会実装に関心があり、「自分でやれたら面白いのでは」と考えていたことが起業のきっかけです。
ー会社名「fabula」にはどのような意味が込められているのでしょうか?
町田: 「fabula」はラテン語で「物語」を意味します。我々が取り組んでいるのは、食品廃棄物をはじめとする未利用資源を新しい価値に変えることです。その過程に「ストーリー」を持たせ、ただのリサイクルやアップサイクルではなく、魅力的な製品を生み出したいという思いから命名しました。どんな素材がどのように生まれ変わるのか、どのような価値を持つのかといった点に焦点を当て、単なる資源の再利用ではなく、人々が共感し、感動するようなプロダクトを生み出すことを目指しています。
一般的に、静脈産業(リサイクル産業)はプロセスに注目されがちですが、私たちは「誰が使うか」「どのような製品になるか」という視点を大切にしています。単に「廃棄物を加工する」だけでなく、「使いたいと思えるものを作る」ことにこだわっています。

「ゴミから感動を生む」ビジョンと原体験
ー「ゴミから感動を作る」というビジョンにはどのような思いが込められていますか?
町田: 廃棄物を単なる”資源”ではなく、人々がワクワクする”プロダクト”に変えることを目指しています。重要なのは、「リサイクルされたから価値がある」のではなく、「この製品が欲しい」と思ってもらえること。リサイクルは手段であり、私たちは付加価値を生み出すことにこだわっています。例えば、紙ストローが環境に良いから使うのではなく、プラスチックストローより味が良いから使いたいと思えるように、純粋に魅力的な製品を作ることが大切だと考えています。
ー環境問題に関心を持つようになったきっかけはありますか?
町田: 幼少期にオランダに住んでいた際、小学校で3か月間かけて自由研究を行う機会がありました。その際に地球温暖化について調べ、環境問題に対する意識を持ち始めました。その後、大学では文系から理転し、土木系の研究へと進みました。その中で「企業ではやらない研究をしたい」という指導教官の言葉が強く心に残り、社会的な課題解決につながる研究を進めるようになりました。

fabulaの社会課題解決への挑戦
ー具体的にどのような社会課題の解決を目指しているのでしょうか?
町田: 私たちは「静脈産業の価値を最大化する」ことを目指しています。SDGsという概念がない社会であっても、政策や流行に依存するのではなく、持続可能な循環を生み出すことが重要です。私たちは、ゴミが単なる廃棄物ではなく、価値ある資源へと変わる世界を作りたいと考えています。
まきチャレ2024について
ーまきチャレ2024でご提案された「牧之原市の茶殻を有効活用したビジネスモデル」についてお聞かせください。
町田:牧之原市では、地域の廃棄物をどのように循環させるかが課題となっています。廃棄物は運搬コストもかかり、遠方に運ぶのは非効率です。そのため、地域内で付加価値のある製品作りまでを完結させることが重要だと考えました。具体的には、伊藤園から茶殻を買い取り、県内で加工、製品化し、販売する地域循環モデルを提案しました。これにより、廃棄物を地域内で最大限活用し、エネルギーコストを削減しつつ、地域経済に貢献することができます。
ー牧之原市で事業を行うことで、どのようなメリットがあるのでしょうか?
町田:茶殻には高い強度と耐水性があり、さらに香りが良いため、多用途での活用が可能です。現在、茶殻を使った建材が求められており、家具などに活用されています。
ー エントリーされたきっかけについて教えてください。
町田:まきチャレには、CFスタートアップパートナーズの出縄さんの紹介でエントリーしました。地域資源を活用したビジネスモデルを提案する場として、私たちの理念と合致すると感じたからです。
ーまきチャレのその後についてお聞かせください。
町田:まきチャレで提案したプロジェクトは現在、茶殻を活用する取り組みを進めている段階です。特に、新たな活用方法に注目しており、さまざまな可能性を模索しています。茶殻の有用性を広く知ってもらう機会にもなるため、今後、さらなる展開を目指していきたいと考えています。
ー他の地方でも同様の取り組みを行っていますか?
町田: はい。例えば、大阪万博では、使用する建材を関西圏内で加工し、地域内で循環させる取り組みを進めています。また、埼玉県では、強度のある白菜の切れ端を活用した製品開発にも取り組んでいます。それぞれの地域資源を活かしながら、廃棄物の有効活用を進めています。
ー地域での循環ビジネスは、東京では成り立ちにくいのでしょうか?
町田: 東京でも可能です。例えば、高級コーヒー店のコーヒーかすを使ってファン向けの製品を作るといった方法もあります。東京では地域循環の形が少し異なるだけで、十分に展開できます。fabulaは東京でもゴミのブランド化に取り組んでいます。単なるリサイクルではなく、このブランドの素材だからこそ価値があると認識されるような市場を作ることで、廃棄物の価値を最大化することを目指しています。

今後の展望と挑戦
ー今後、どのような展開を考えていますか?
町田: 私たちは、「ゴミから感動を作る」という会社のビジョンを実現するために、特にブランド構築と研究開発の二つの側面を重視しています。まず、ブランド構築においては、単なる素材メーカーではなく、「fabula」というブランドとしての認知度を高めていきたいと考えています。実際に使用してもらえる製品を着実に生み出しながら、「ゴミから感動を生む」というコンセプトを広め、単なるリサイクル事業ではなく、「価値を生む企業」としての存在感を確立していきたいと思っています。
また、研究開発にも力を入れ、より実用的な市場に適した製品を開発していきます。家具や雑貨だけでなく、大規模な市場で流通可能な建材市場への参入も視野に入れ、廃棄物を単なる再利用にとどめるのではなく、新たな価値を生み出す素材へと昇華させていきたいと考えています。これらの取り組みを通じて、より多くの人にfabulaの理念を伝え、廃棄されるものの価値創造を行っていきたいです。
ー事業パートナーとして求めている企業はどのような企業ですか?
町田: 例えば伊藤園のように、廃棄物を持っているが加工に至っていない起業、それを社内や市場で活用したいと考えている企業と協業したいです。
読者へのメッセージ
ー最後に、この記事を読む方々へメッセージをお願いします。
町田: 生活の中で「この製品はどこから来たのか?」と少しでも意識することで、物の見方が変わると思います。背景を知ることで、より豊かな消費ができるはずです。
fabulaとしても、皆さんの生活を彩るプロダクトを生み出していきますので、ぜひ注目していただければ嬉しいです。
〈企業概要〉
【会社名】fabula株式会社
【URL】https://fabulajp.com/
【設立日】2021年10⽉1⽇
【所在地】〒144-0045 東京都大田区南六郷三丁目10番16号六郷BASE
【代表者】代表取締役 町⽥ 紘太





















