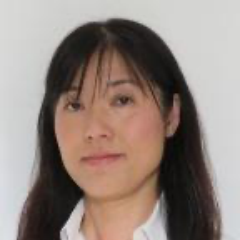2021年10月のマイナンバー保険証の本格運用から約2年が経過した。しかし、その間にマイナンバーカードにまつわるさまざまなトラブルが発生したことから、カードの利用をためらっている人もいるだろう。
その一方で、政府は2024年12月2日にマイナンバーカードと保険証を一本化させ、紙の健康保険証を廃止することを決定した。本稿では、これまでの経緯を振り返り、マイナンバーカードと保険証を一体化させた「マイナ保険証」のメリットとデメリット(注意点)を解説する。
目次
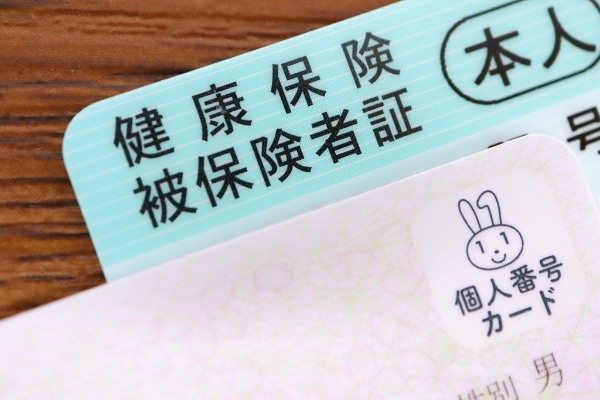
マイナ保険証とは?
マイナ保険証とは、マイナンバーカードに健康保険証機能を持たせたものである。医療機関で従来(紙)の健康保険証を提示する代わりに、受付に設置されたカードリーダーにマイナ保険証つまり、マイナンバーカードをかざし顔認証で受け付けする。
マイナンバーカードに健康保険証機能を持たせるには、以下のいずれかの方法で保険証利用の登録を行う必要がある。
(1)医療機関や薬局に置かれているカードリーダーで登録する
①カードリーダーにマイナンバーカードを置く
②顔認証か暗証番号のどちらかの方法で本人確認を行う(顔認証が便利)
③過去の診療やお薬情報などを医療機関・薬局に提供することを同意するかどうか選択する
④マイナンバーカードを健康保険証として利用する手続きを行う(「ボタンを押す」などの画面が表示される。カードリーダーの機種によって表示される画面は異なる)
⑤登録完了
(2)セブン銀行ATMで登録する
①マイナンバーカードと利用者証明用パスワードを用意する
②セブン銀行ATMの画面で「各種お取引き」を選択する
③「マイナンバーカードの健康保険証利用の申込み」を選択する
④利用規約に同意して「確認」ボタンを押す
⑤マイナンバーカードの裏面を上にしてカード読み取り口に挿入する
⑥利用者証明用パスワードを入力する
⑥登録完了。
(3)パソコンやスマホから「マイナポータル」にアクセスして登録する
※ここではスマホから登録する方法を紹介する
①マイナンバーカードと利用者証明用パスワード、「マイナポータルAP」アプリをインストールしたスマホを用意する(スマホはマイナンバーカード読み取り対応機種であること)
②マイナポータルAPを開き「健康保険証利用申込」を押す
③「ステップ1」の画面が開く。マイナポータルの利用者登録を行う場合はチェックを入れ、マイナポータル利用規約を確認して「同意して次へ進む」ボタンを押す
④「ステップ2」の画面が開くので「申し込む」ボタンを押す
⑤利用者証明用パスワードを入力する
⑥マイナンバーカードをスマホで読み取る
⑦読み取りが終われば登録完了
医療機関や薬局に行くたびに、カードリーダーにマイナ保険証をかざし、本人認証と過去の診療やお薬情報などを医療機関・薬局に提供するかどうかを選択すると保険証確認が完了する。
運用開始時にトラブルが相次いだ背景は?
患者がマイナ保険証を使うと、医療機関側は患者が加入している公的医療保険や自己負担割合の確認、かつ本人であることの確認がオンラインでできる。これをオンライン資格確認というが、これまでオンライン資格確認の際に別人の健康保険情報が登録されていたというトラブルが相次いで報道された。
その数は、オンライン資格確認の運用開始から2023年5月22日までの間で7,372件に及ぶ。そこで厚生労働省が翌5月23日付けで全保険者に対して点検を依頼したところ、1,109件の別人登録が確認された(2023年9月29日現在)。
本人の保険情報が登録されていても医療費の自己負担割合が誤登録されていたというトラブルもある。所得によって自己負担割合が1~3割となる高齢者に特に多いようだが、なかには6歳未満の幼児であるにもかかわらず、「高所得 現役並み」と表示されたケースもあるようだ。
自己負担割合の誤登録に関しては、全国保険医団体連合会が全国6万5,811の医療機関にアンケート調査を行い、現在までに978の医療機関で確認されている。ちなみにアンケートに回答した医療機関数は、約1割の7,070機関にすぎない。実際には、より多くのトラブルがあった可能性も考えられる。
マイナ保険証に限らず、マイナンバーカード自体の以下のようなトラブルも相次いでいる。
- 同姓同名の別人へのマイナンバーカード交付
- コンビニで別人や抹消済みの証明書を誤発行
- マイナポータルで別人の年金記録を閲覧できる
など
こうしたトラブルには、以下のような背景があった。
①オンライン資格確認時に別人の健康保険が登録されていたのは、被保険者が新たに健康保険組合に加入した際、手続の処理が正しく行われなかったために本来の被保険者以外の人物に情報が紐づけられてしまっていたことが原因だった。
②自己負担割合の誤登録も、役所の国民健康保険担当者が誤って入力したことが原因だった。
③コンビニでマイナンバーカードを使って証明書を発行した際の誤発行ミスは、民間企業が手がけたシステムに問題があった。
これらのトラブルに対し、政府が迅速に対応できなかった点は批判されるべきである。しかし、その後は健康保険組合などに対して登録済みデータの総点検と、被保険者の登録に関して情報の突き合わせを徹底するよう指示している。
マイナ保険証のデメリット
とかくデメリットが話題になりやすいマイナンバーカードやマイナ保険証であるが、具体的にはどのようなデメリットがあるのだろうか。主なデメリットを2つ紹介する。
1.利用できない医療機関もある
マイナ保険証は、医療機関や薬局がマイナンバーカードを読み取るためのオンライン資格確認システムを導入していなければ使えない。前述したようにすべての医療機関等は、オンライン資格確認システム導入を原則義務づけられた。しかし厚生労働省のデータによると2024年3月31日時点で同システムを申し込んだ医療機関等は91.2%、実際に参加している機関は90.5%となっている。
マイナ保険証の利用を希望しても実際には利用できない場合もあるということだ。
2.個人情報漏洩リスクは拭えない
マイナンバーカードを医療機関に持参することで紛失リスクが高くなるデメリットもある。マイナンバーカードでなくても診察カードの渡し忘れは少なくない。
マイナ保険証をカードリーダーに置いたまま、取り忘れるということが起こる可能性は充分考えられるだろう。患者側もカードリーダーからマイナ保険証を取ったかどうか意識せずに帰宅してしまいそのまま失念してしまう可能性も考えられる。紛失した場合、大切な個人情報を悪用される危険性は拭えない。
マイナ保険証のメリット
デメリットが目立つマイナ保険証。利用する際は、メリットとのバランスを考えて提示するかどうかを検討することも必要だ。そこで、マイナ保険証のメリットを整理しておこう。
医療費が割安
医療機関・調剤薬局などでのオンライン資格確認が原則義務化されている。患者は、マイナ保険証・紙の健康保険証にかかわらず「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」の窓口負担が必要だ。2024年4月現在、医療機関を利用した場合、初診時の窓口負担額はマイナ保険証利用で6円、紙の健康保険証利用で12円となっている(いずれも3割負担の場合)。
マイナ保険証を利用したほうが割安になる。
就職・転職・引越しをしてもずっと使える
例えば会社員の場合、健康保険証は会社で発行手続きをすることになる。そのため就職・転職をした際には、新たな就職先で健康保険証を発行してもらうことになる。また引っ越しや結婚して姓が変わったときには、住所や氏名の変更手続きが必要だ。しかし新しい健康保険証が届くのを待っている間に病気やケガで医療機関へ受診するケースもあるだろう。
そのような場合でも新しい健康保険証の発行を待たずにマイナ保険証で受診できるのは便利だ。
医療費が高額になっても自動的に窓口精算額を軽減できる
救急などで医療費が高くなりそうなときのメリットもある。公的医療保険に「高額療養費制度」があるが、マイナ保険証で受診することでこの手続きの手間が省ける。
高額療養費制度とは、1ヵ月の医療費窓口負担が一定額を超える場合にその超えた部分が還付される仕組み。事前に申請しておけば医療機関の会計で多額の支払いをしなくてよくなる「限定額適用認定証」がもらえる。
マイナ保険証で受診した場合、医療機関がシステム上で限定額適用認定資格を確認できるため、限定額適用認定証の提出も不要になるのだ。自動的に窓口での支払額が抑えられるのはありがたい。
過去の診療情報データにもとづいた診察・処方を受けられる
マイナ保険証を利用すると処方された薬の情報などが履歴として残るため、診察をする医師も患者の同意を得たうえで履歴を確認しながらより適切な診察・処方が期待できる。これは、医師・患者の両者にとって安心につながるだろう。
従来の健康保険証は2024年12月2日に廃止、その後はどうなる?
2023年6月9日に政府は、マイナンバー法等の一部改正法を公布し、そのなかで従来の紙の保険証を廃止することを決めた。2024年12月2日に施行され、この日以降は紙の保険証は発行されなくなる。
まだマイナンバーカードを所有していない人やマイナ保険証の利用に不安がある人は、今から対応を検討しておくのがおすすめだ。まず2024年12月2日に当改正法が施行された時点で発行済みの紙の保険証は、その後1年間は使用できる。
ただし健康保険証の有効期間がそれより早く到来する場合には、健康保険証に記載されている有効期間までとなる。また高齢者や子どもなどマイナンバーカードを発行できない事情がある人、紛失した人、更新中の人など、マイナンバーカード(マイナ保険証)を利用できない人は保険者(健康保険組合や協会けんぽ、自治体など)に申請して「資格確認証」を発行してもらうことが可能だ。
医療機関等の窓口では、マイナ保険証の代わりに資格確認書を提出すれば受診できる。資格確認書には、最長1年の範囲で有効期間が定められるため、注意が必要だ。
国がマイナ保険証を進めるワケ
マイナ保険証を導入してオンライン資格確認を推進することで、上述したメリット以外にも、患者がより良い医療を受けられたり、医療機関・薬局における事務負担を軽減できたりといったことが可能になる。
現在、医療費が増え続ける要因の一つとして薬剤費が挙げられるが、異なる医療機関で同じ薬を重複して処方されていたり、処方された薬を服用しないまま溜めていたりする患者は少なくない。患者にマイナ保険証を利用してもらい、医師や薬剤師が患者の同意のもとに医療情報を閲覧することで、適切な診療や薬の処方・服薬管理ができる。
また、人材不足の中、オンライン資格確認によって医療機関などの事務手続きにかかる手間が減らせることも期待される。オンライン資格確認の開始時にはトラブルが頻発したが、これからの超高齢化社会における医療体制を維持するうえで、マイナ保険証を導入する意義は決して小さくない。