
群馬県伊勢崎市にあるはぎわら社会保険労務士法人は2025年春、移転し、新たなオフィスでサービスをリスタートした。萩原寿行代表はもともとシステムエンジニア出身だが、ホームページには「企業の健全な成長をサポート」と掲げ、顧客企業数を徐々に拡大し、経営の舵取りを担っている。(TOP写真:2025年4月に移転し、内装も新しくなったはぎわら社会保険労務士法人の事務所)
目次
システムエンジニアから農業、そして社会保険労務士へ。合格率6~7%の難関試験を4年目で突破

大学の理系学部を卒業後、地元の群馬県に戻り、桐生市のシステムインテグレーター企業にシステムエンジニアとして就職した萩原代表。顧客企業のシステムプログラミングで、毎週のように国内外に出張する仕事を続けた。平日の出張の準備を土日にしなくてはならないことや、残業の多さ、管理業務なども引き受けるようになった時期に子どもが生まれたことで、家族に携わる時間が減り、約9年勤めた後、退職した。
「管理業務は慣れないことだらけで、向いていなくて、会社を辞めることにしました。実家が農家を営んでおり、米・小麦などを作っていたのでそれを手伝うことにしました。今も作業を手伝っているのですが、これも向いていなかった。ならば資格を取ろうと思い、資料を見ていたところ、兄が『社労士なんていいんじゃない?』と提案してくれたんです」(萩原代表)
3年間は独学での資格取得を目指したが、現実はそう甘くはなかった。「3度目の頃になると手応えもあったんですが」と萩原代表は振り返るが、合格率が毎年6~7%とされる難関の試験には、結果的に3年連続で受からなかった。「これは独学では無理だと考え、資格取得の専門予備校の通信教育を受けることにしました。35万円ほどの投資は大きかったですが、2014年に受験した4年目の試験がクセのない問題だったこともあって合格。これで人生が変わると思って、しびれました」(萩原代表)
高校の同級生の父の下、2年半の修業を経て独立し、社会保険労務士事務所を立ち上げ 自分のイメージで動きたい
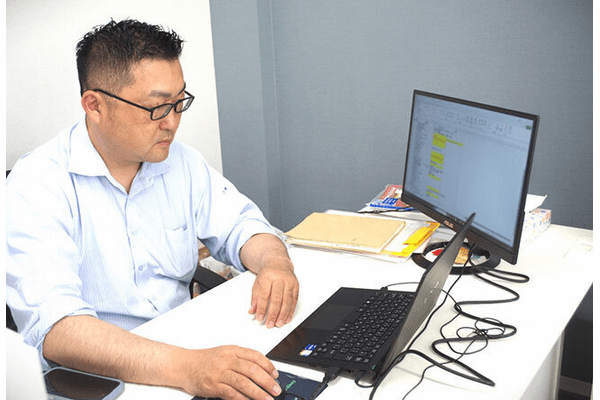
社労士の資格を得たものの、それまでの職歴を考えれば、当然ながら社労士としての人脈などがあるわけではなかった。たまたま合格後に開かれた高校の部活の同窓会で、同級生の父が社労士をしていることを耳にし、「話を聞かせてほしい」とつないでもらった。
挨拶に訪れたところ、時給制のアルバイトではあったが、同級生の父の下について社労士を務めることとなった「そこは事務所といっても、従業員は私だけ。しかも行政書士の仕事をメインにやっており、社労士の仕事は最低限のことをやっているにすぎませんでした。先生からは、行政書士の資格も取ってとも言われたのですが」と萩原代表は振り返る。
社労士に関しては試験に受かったこともあって、細かい実務なども含めてその仕事内容に思い入れがあったが、「行政書士には関心がなかった」という。そのため、2015年初頭から約2年半の修業を経た後で、実家の一室を父に改築してもらい、そこを拠点に社労士として独立した。そこには「人に使われるよりも自分のやりたいイメージで動いたほうがいい」という考えもあったが、「今思えば(独立は)早かったかもしれない」という中で、個人事業主として社労士の活動を2017年からスタートさせた。
独立後、顧客ゼロ 赤字続きでも電子化の波が追い風に。元システムエンジニア時代の経験が奏功

振り返れば「早かったかも」と感じた社労士としての独立だが、社労士が取り扱う書類にも電子化の波が押し寄せるなど、環境的には追い風も吹いていた。「それまでは社労士といえば、税理士職員が経理伝票を預かりながら、入退社の申請も書類に印鑑をもらいながら扱っていたというイメージでした。ですが、パソコンでデータをやり取りする時代になったので、社労士としての経験が浅くても仕事ができる土壌になっていたんです」(萩原代表)。そうした電子申請を扱うことで新規の仕事を取ってくるやり方で、創業以降は仕事を増やしてきた。
アルバイトをしていた2年半の修業時代に、経験が浅くても電子申請の仕事に携わらせてもらったことも奏功した。「ありがたかったですね。システムエンジニアをやっていたので、ICTには強いと思われていましたから。かつての経験が無駄ではなかったと思いました」(萩原代表)
とはいえ、決してすべてが順風満帆ではなく、顧客企業が最初からいるわけでもないため、創業時からは赤字が続いた。先輩の社労士が経営していた事務所から、労務関係の仕事をもらい、それで食いつなぐ日々が3年程度は続いた。しかし、実家の農家の手伝いによる収入、事務所も実家の中で家賃は不要、妻の収入などもあって、社労士のみで赤字でも何とか続けていくことができた。
「今でも親交のある先輩労務士ですが、週4ぐらいで外注してもらった仕事をしながら、自分の事務所の仕事を進めていましたね。ただ、最初についた先生と違ったのは、この先輩社労士が、税理士や行政書士の仕事ではなく、社労士関連の業務で事務所を運営していたことです。企業の給与計算の代行や、業務ソフトを使用した従業員管理などを学ぶと同時に、その運営の仕方を見ながら『社労士でも食べていけるな』というイメージも徐々に湧いてきました」(萩原代表)
そのイメージから、赤字ではあったものの、人件費がかかることを承知で早期に社労士の受験を目指す男性を採用した。「社労士の仕事が、従業員を雇うことに対する相談に乗るものなので実際に雇用して経験する、という考えでした」と萩原代表は明かす。
徐々に仕事が増えてはきたが、人件費などの経費も先行したため、黒字になったのは、法人化する前の2023年になってからのことだった。
かつてのサラリーマン時代の同僚も社労士となって、仕事の相談をしていたところ、「企業に対する助成金の申請代行を手掛けたほうが良い」との助言を受け、そうした業務も手掛けるようになった。
助成金申請代行を手掛ける中で、得意にしてきたのは「キャリアアップ助成金」の申請代行だ。「有期契約の従業員が正社員になる場合に申請するものです。元手は掛からないメリットがある一方で、受給するまでのスパンが結構長いため、成功報酬を受け取るまでの資金繰りなどにも苦労しますが、顧問料に加えて、こうした成功報酬が売上の3~4割を占めるようになっていました」(萩原代表)
群馬県内はもとより、埼玉県北西部、東京都内の企業などでの仕事も増えてきた。新型コロナウイルス禍においては、人の動きも少なく、新たな顧客企業の獲得もなかなか難しかったが、法人化後の現在は顧問契約している企業が約60社を数え、2025年4月には新たに事務所を移転し、5人の従業員とともに仕事をやりくりしている。
業務の進捗管理、顧客管理を従業員全員で見える体制を構築するため、ICT化を進める。得意の助成金申請代行で顧客企業の拡大を目指す

従業員を増やしてきた中で、業務の進捗管理や顧客管理も煩雑になってきた。従業員を1人だけ雇っていた時代は、そのやり取りも単純だったが、「Excelだと私が管理して、作業を従業員の人に任せておけばよかったのですが、従業員全員が管理しようとするとExcelファイルは同時に開けない」(萩原代表)という壁にぶち当たった。移転前の狭い事務所では、従業員同士が、「今からこのファイルを開いてもいいですか?」と声かけをしてからでないと作業ができなかった。
そこで導入したのが、業務アプリも簡単に開発できるクラウドサービスだ。これにより、「従業員が全員、管理も作業もできる体制が整いました」と萩原代表は話す。加えて外出先からでも管理作業などがしやすくなり、萩原代表が顧客企業訪問のために外出しても、即時に状況を把握できるようになった。
萩原代表は「今後は、このクラウドサービスを用いて、顧客管理をさらにしっかり行い、取りこぼしのないように仕上げていきたいですね」と話す。得意の助成金申請代行なども、このサービス上で見れば進捗などが一目瞭然となる。「今はまだ従業員が私に聞いてくることもある過渡期ですので、顧客企業に対するサービス向上、スピード感アップのためにも実現していきたいですね」(萩原代表)
視野に入れているのは、厚生労働省が進める時間外労働削減や年休取得促進などに取り組む「働き方改革推進支援助成金」、生産向上のための設備投資などを念頭に置いた「業務改善助成金」、育休や介護休暇など柔軟な働き方に対応するための「両立支援等助成金」の取り扱い。そうした情報を顧客に提供する「提案力」を上げることで差別化を図っていく方針だ。
その上で萩原代表は「社労士は人の手でやらないといけないことは多いが、ICTを活用すれば顧客企業の給与設計などまで出来る。それを望む顧客企業も多い」とさらなるICTの強化を視野に入れる。「顧客のニーズをいかに受け止められるか」を念頭に、従業員の教育訓練やキャリアアップを実施。そのために事務所でも助成金活用を視野に入れ、顧問契約企業の拡大を目指す。
企業概要
| 会社名 | はぎわら社会保険労務士法人 |
|---|---|
| 住所 | 群馬県伊勢崎市田部井町2丁目579-1 田園ステーションA-1 |
| HP | https://hagiwararoumu.jp |
| 電話 | 0270-61-8655 |
| FAX | 0270-61-8622 |
| 創業 | 2017年6月 |
| 従業員数 | 5人 |
| 事業内容 | 企業各種相談対応、企業助成金申請代行、定例業務の手続代行、給与計算代行等 |



















