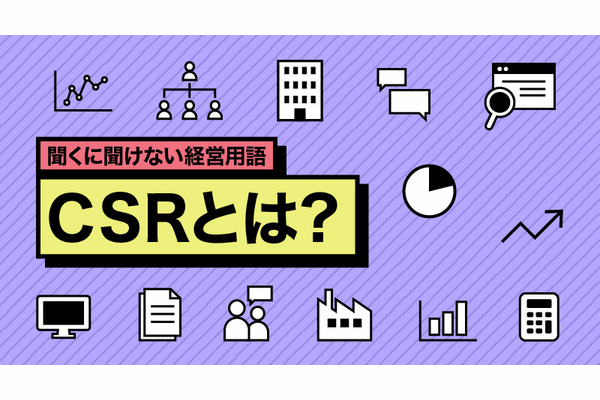
目次
近年、企業に向けられる利害関係者の目がシビアなものになりつつあります。こうした時代においては、大企業だけでなく中小企業にとってもCSR(企業の社会的責任)が重要な課題となっているのが実情です。 この記事では、CSRの基本的な考え方や関連用語との違い、中小企業がCSR活動に取り組むメリットについてわかりやすく解説しています。中小企業が実践しやすいCSRの取り組み例や、CSR活動を推進する際に意識しておきたいポイントもまとめていますので、ぜひ参考にしてください。
CSR(企業の社会的責任)とは
CSRとは、企業が組織としての活動を行う上で担う社会に対する責任のことです。英語のCorporate Social Responsibilityの頭文字をとって、CSRと呼ばれています。たとえば、企業活動に関する情報を積極的に開示して経営の透明性を高めることや、誠実性や公平性に根差した事業活動を推進していくことなどは、CSR活動の好例です。
はじめにCSRの原則と、近年重視されている背景について解説します。
| 国際規格 ISO26000における「7つの原則」 |
|---|
CSRの原則として挙げられるのが、国際標準化機構(International Organization for Standardization)が定めている「ISO26000」です。ISO26000は、社会的責任に関する国際規格として2010年に発効されました。ここに定められている「7つの原則」は次のとおりです。
| 1. 説明責任 | 企業活動が社会に与える影響について、十分に説明する。 |
| 2. 透明性 | 組織としての意思決定や活動の透明性を保つ。 |
| 3. 倫理的な行動 | 公平性や誠実性などの倫理観にもとづいて企業活動を推進する。 |
| 4. ステークホルダーの利害の尊重 | 多方面のステークホルダーに配慮して企業活動を行う。 |
| 5. 法の支配の尊重 | 自国および他国の法令を遵守する。 |
| 6. 国際行動規範の尊重 | 国際的に通用している規範を尊重・遵守する。 |
| 7. 人権の尊重 | 重要かつ普遍的な人権を尊重する。 |
この原則は、すべてを満たすべき事項としてではなく、組織がそれぞれの特徴にあわせて必要な部分を活用して、社会的責任を果たすためのヒントとして定められています。
| CSRが重視されている背景 |
|---|
近年、CSRが重視されている要因として、環境や社会と共存しながら成長していく企業像がいっそう求められている点が挙げられます。企業は利益の追求に終始するのではなく、自社がもたらす社会的影響を十分に考慮しつつ事業を推進しなければならない、というのがCSRの根底にある考え方です。
たとえ短期的に多くの利益を得たとしても、不正行為や環境破壊などの問題が発覚すれば、結果として事業活動を継続できなくなってしまいます。説明責任や透明性、倫理観などが企業に求められているのはこのためです。
CSRと関わりのある用語との違い
CSRと関わりのある用語として、次の4点が挙げられます。
・サステナビリティ・コンプライアンス・SDGs・CSVそれぞれの用語の意味と、CSRとの違いを整理しておきましょう。
| サステナビリティとの違い |
|---|

サステナビリティは、「持続可能性」という意味を表す言葉です。企業が社会や環境、経済などに与える影響を考慮しながら事業活動を行うことで、地球や人間社会の持続を目指すことを指します。 CSRは企業が世の中に対して果たす責任を指すことから、サステナビリティとは意味や用い方が異なります。ただし、社会の持続可能性を目指すサステナビリティに寄与することも、CSR活動の1つです。CSR活動の推進が結果としてサステナビリティの実現にもつながるという点において、両者には密接な関わりがあります。
| コンプライアンスとの違い |
|---|

コンプライアンスとは、企業が法令をはじめとするさまざまな規則や社会的機関を遵守することを指します。CSRにも法令遵守の考え方が含まれているものの、企業が社会的責任を果たす上で法令を守る必要があるという考え方に根差している点が大きな違いです。
一方で、CSRを推進するには大前提としてコンプライアンスの強化が必須条件の1つとなります。そのため、近年ではCSRの倫理的活動をコンプライアンスの一環と捉えるケースも見られるようになりました。
| SDGsとの違い |
|---|

SDGsは、2015年に国連サミットで採択された国際目標です。2030年までに持続可能なよりよい社会を築いていくために、環境問題や貧困といった社会問題を解決する目標を掲げています。 CSRは、企業が世の中に対する責任を果たすための社会貢献活動です。これに対して、企業にとってのSDGsはビジネスを通じて持続可能な社会の実現に貢献する取り組みを指すことから、両者は異なる概念といえます。ただし、SDGsを実現するには企業の協力が欠かせないとされている点において、SDGsは企業が果たすべき社会的責任の一環ともいえるでしょう。
| CSVとの違い |
|---|
CSV(Creating Shared Value)は、事業活動を通じた社会的課題の解決と、企業価値の向上の両立を目指す経営手法のことです。日本語では「共有価値の創造」などと訳されます。 CSRでは企業の社会的責任に重きが置かれているものの、企業にとっては利益を生み出すための活動も欠かせません。よって、CSR活動を推進しつつも、一連の活動が企業価値の向上や利益の増大をもたらす取り組みが理想といえます。こうした企業活動のあり方を実現するのが、CSVの基本的な考え方です。
アメリカやヨーロッパにおけるCSR

CSRは突如として現れた概念ではなく、各国の歴史的・文化的背景と密接に結び付いて育まれてきた考え方です。アメリカやヨーロッパにおけるCSRのあり方を知ることで、CSRに対する理解をいっそう深められるでしょう。
| アメリカにおけるCSR |
|---|
アメリカでは、CSRへの取り組みに対する投資家の関心が非常に高い傾向がみられます。グローバル企業を多数輩出している国であり、アメリカ国内だけでなく多くの国や地域での企業活動が国際的な評価に直結しやすいというのがその一因です。 したがって、とくに大企業ではCSR関連の大規模な予算を確保しているケースも少なくありません。企業としても、CSRへの取り組みは企業価値を左右する重要な要素です。このように、CSRと事業の関連性が長年にわたって共通認識となっている点がアメリカ社会の特徴といえます。
| ヨーロッパにおけるCSR |
|---|
ヨーロッパには、労働や環境に対する国民の意識が高い国々が多くみられます。社会的影響を度外視した企業活動に対しては、国民から厳しい目が向けられるケースも多いのが実情です。 そのため、ヨーロッパにおいて事業を存続させていくには、必然的に未来を見据えた投資や活動を推進していく必要があります。CSRに関しても、こうした文化的背景から自然と醸成されてきた概念の1つといえるでしょう。
中小企業がCSR活動に取り組む3つのメリット
CSRと聞くと、主に大企業を中心となって推進する活動というイメージが強いかもしれません。しかしながら、中小企業においてもCSR活動の推進は重要な課題の1つです。中小企業がCSR活動に取り組むメリットとして、次の3点が挙げられます。
| メリット1:社会的な信頼向上につながる |
|---|
CSRを積極的に推進している企業は、高い倫理観にもとづいた事業活動を推進しており、不祥事が起こりにくい組織として認識される傾向があります。そのため、取引先や消費者から信頼を得られ、継続的な取引や購買につながる可能性が高まる点が大きなメリットです。 実際、消費者がある商品を選ぶ際、より企業イメージが良好でクリーンな印象を受ける企業の商品を優先的に購入するケースは少なくありません。このように、社会的な信頼の向上は長期にわたる業績の安定をもたらす可能性があります。
| メリット2:人材採用において有利になる |
|---|
CSR活動の積極的な推進は、人材採用においても効果を発揮します。信頼性が高い企業には人が集まりやすくなる傾向があるため、優秀な人材を確保しやすくなるからです。 さらに、既存の従業員が自社に対していっそう信頼を寄せることにより、従業員エンゲージメントが高まる効果も期待できます。結果として、従業員による紹介を通じた採用(リファラル採用)の機会が得られるなど、採用チャネルの多様化にも寄与するでしょう。
| メリット3:消費者の購買行動の変化に適応しやすくなる |
|---|
CSR活動の推進は、急速に変化しつつある消費者の購買行動に適応する意味においても有効です。近年は、とくに若い世代を中心にエシカル消費が浸透しつつあります。エシカル消費とは、自分自身の欲求を満たすためだけでなく、社会問題の解決につながる行動や意思決定を意識した消費行動のことです。 利益の追求に終始することなく、社会問題の解決に取り組む企業は、こうした消費者の志向と親和性が高いと考えられます。結果として、CSR活動を積極的に推進する企業の商品・サービスが選ばれやすくなることは十分にあり得るでしょう。
中小企業が実践しやすいCSRの取り組み例
ここまで、CSRに関する一般的な概念や推進するメリットについて解説してきました。では、中小企業がCSR活動を推進する場合、どのような取り組みが想定されるのでしょうか。中小企業が実践しやすいCSRの取り組み例を紹介します。
| 事例1:ガバナンス/コンプライアンスの強化 |
|---|
企業規模を問わず求められるCSR活動として、ガバナンス(企業統治)やコンプライアンス(法令遵守)の強化が挙げられます。法令に則って適切に業務が遂行されていることや、それらのプロセスが適正に管理されている状態が、CSRのベースとなるからです。
【ガバナンス/コンプライアンス強化策の例】
- 社外取締役や社外監査役の選任
- 弁護士や税理士、公認会計士などの社外専門家に協力を仰ぐ
- ステークホルダーとの建設的な対話の推進
ガバナンスやステークホルダーといった用語については、次の記事で解説しています。こちらもぜひ参考にしてください。
https://www.ricoh.co.jp/magazines/smb/column/001092/
| 事例2:人権の擁護 |
|---|
人権は広く認知されている基本的な権利であることから、これを擁護するための取り組みは重要なCSR活動の1つといえます。人権擁護に関する方針を策定するだけでなく、経営陣および従業員にその重要性を浸透させていくことが重要です。
【人権擁護に向けた取り組み例】
- 人権擁護に関する方針策定
- 人権意識を高める従業員教育の実施
- 公正な雇用の宣言と実践
| 事例3:労働環境の改善 |
|---|
従業員の労働環境を改善していくことも、CSR活動の一環といえます。好ましくない労働環境を放置することは自社の問題にとどまらず、業界全体の評判の低下につながったり、社会全体の労働慣行に悪影響を与えたりすることにもなり得るからです。自社が現状抱えている課題を洗い出し、改善を図る取り組みを継続していくことが、CSR活動の推進へとつながっていきます。
【労働環境の改善策の例】
- 長時間労働の是正
- リスキリングの推進
- 労働衛生の改善
- ハラスメント相談窓口の設置
| 事例4:環境保全 |
|---|
事業によってもたらされる環境負荷をできる限り軽減するための取り組みも、CSR活動の1つといえます。リサイクル商品を積極的に備品として取り入れるなど、小さな取り組みを積み重ねていくことが大切です。
【環境保全につながるCSR活動の例】
- 温室効果ガスの排出量削減に向けた取り組み
- 省エネ設備への切り替え
- 環境保全に積極的な企業との取引の推進
| 事例5:倫理観に根差した事業慣行 |
|---|
利益の追求に終始しない、倫理観に根差した事業慣行を定着させていくための取り組みも重要なCSR活動です。自社の都合のみで取引条件を押し通したり、下請法に抵触しかねない取引を行ったりすることは、厳に慎む必要があります。
【倫理観に根差した事業慣行の推進策の例】
- 内部通報窓口の設置
- 定期的なコンプライアンス研修の実施
- フェアトレード製品を優先した仕入
| 事例6:積極的な情報開示 |
|---|
ステークホルダーに対して積極的に情報を開示していくことも、CSR活動に含まれます。自社が提供する商品・サービスによって消費者に危害がもたらされるのを防ぐとともに、消費活動を通じて環境保全に自ずと貢献できるような製品の開発をしていくことも、有意義なCSR活動の1つです。
【情報開示に関する取り組み例】
- 自社の商品・サービスに関する情報開示
- カーボンニュートラル製品の公表
- 消費者の声を聞き、対話を促すための窓口の設置
| 事例7:地域貢献 |
|---|
各拠点において、地域コミュニティの発展や活性化につながる活動を展開していくことも、CSR活動の一環といえます。地域貢献に積極的な企業として認知されることは、それぞれの地域において事業活動を進めやすい環境を整えていくためにも、重要なポイントの1つです。
【地域貢献につながる活動の例】
- 地域イベントへの参加
- 教育啓蒙活動の推進
- ボランティア活動への参加
中小企業がCSR活動に取り組む際のポイント
中小企業がCSR活動に取り組む際に、いくつか注意しておきたいポイントがあります。効果的なCSR活動を推進していくためにも、次の3点に留意しましょう。
| 自社の得意分野との相乗効果を意識する |
|---|
CSR活動には幅広い取り組みが想定されます。どのような取り組みを強化していくべきか検討する際には、その活動に自社の得意分野が生かせるかどうかを十分に検討しておくことが大切です。
たとえば、セキュリティ関連商材を扱っている企業であれば、地域の教育啓蒙活動においても地域住民のセキュリティ意識を高めるための活動に注力するのが得策でしょう。自社の専門分野であれば、その知見を生かしてCSR活動を無理なく展開できるからです。自社の得意分野を発揮することで効果的なCSR活動を実現しやすくなるだけでなく、自社の認知度向上につながるなど、本業との相乗効果が得られる可能性が高まります。
| 費用対効果を慎重に判断する |
|---|
CSR活動に必要なコストと、活動を通じて得られる中長期的なリターンのバランスを十分に考慮しておくことも重要なポイントです。膨大なコストをかけたにもかかわらず、ほとんど効果が得られないといった事態に陥ることのないよう、取り組むべき活動を慎重に選択する必要があります。
たとえば、BtoB企業が一般消費者を対象としたイベントを開催したり、教育啓蒙活動に取り組んだりするのは、中長期的な視点に立つと効果のある活動といえます。企業名や事業内容を広く知ってもらうことによって、中長期的には企業イメージの向上や採用活動の強化にもつながり得るからです。一方で、企業イメージが広く浸透するまでには長い期間を要する傾向があります。その期間中にかかるCSR関連費用と、得られる効果のバランスをよく見極めておくことが重要です。
| リソースの配分に留意する |
|---|
CSR活動を継続的に推進していくにあたって、リソースの配分を考慮しておくことが大切です。CSR活動には多くのリソースを必要とします。従業員が本来の担当業務とCSR活動を兼務したことにより、本業に充てるリソースがひっ迫するようでは本末転倒といわざるを得ません。
本来であればCSR専任の部署や担当者を配置するのが理想ですが、中小企業においてはこうした対応が容易ではないことも想定されます。必要に応じて外部の専門家に協力を仰ぐなど、現実的な対応策を検討していくのが望ましいでしょう。
CSR活動の推進が組織力の強化につながる
CSR活動を通じて社会やステークホルダーに対する責任を果たしていくことは、長期的に見ると自社の利益や成長へとつながっていきます。CSRの重要性を理解し、実践していくことは、会社が新たなステージへと踏み出すきっかけとなるでしょう。今回紹介した取り組み例や実践のポイントを参考に、CSR活動の推進策を検討してみてはいかがでしょうか。
中小企業応援サイトでは、CSRの他にも、ビジネスパーソンに必須の10の用語を解説する「聞くに聞けない経営用語集」のダウンロードを実施中です。重要な経営用語を知ることでビジネスの新しい視点を得られるこの資料を、ぜひご活用ください。



















