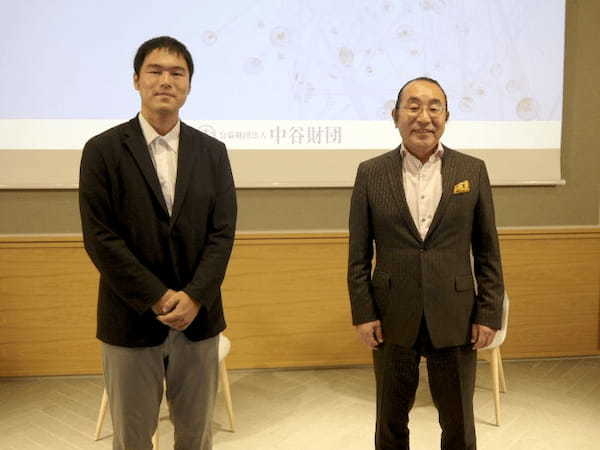
BME(Bio Medical Engineering)分野の発展を通じて、日本のイノベーションを促進させるため、表彰事業および新しい研究や技術開発を支援する助成事業など幅広い活動を行っている中谷財団は、第2回「神戸賞」大賞受賞者である東京大学大学院 理学系研究科 教授の菅裕明氏の革新的かつ独創的な研究に関するセミナー「異端からの発想。特殊ペプチド創薬は常識を変える!」を6月24日に開催した。今回のセミナーは、科学コミュニケーターの加藤昂英氏を迎え、菅氏の特殊ペプチド創薬の研究によってどのような“常識”が変わっていくのかを様々な視点から掘り下げた。

セミナーの開催にあたり、中谷財団 事務局長の松森信宏氏が挨拶。「当財団は1984年の設立から40年にわたって助成事業と表彰事業を手がけており、累計助成金額は66億円、累計助成件数は2700件を超えている。昨年、財団設立40周年を記念して学術賞『神戸賞』を創設した。同賞は、今後、日本がリードしていく分野として注目しているBME分野(生命科学と理工学の融合境界領域)においてイノベーションをもたらす優れた独創的な研究で実績を挙げた研究者や、ユニークな研究で将来性が嘱望される若手研究者に光を当てる学術賞となっている。大賞受賞者には賞金5000万円、若手研究者を対象としたYoung Investigator賞では賞金500万円と5年間で4000万円の研究助成金を贈呈する。近い将来、大賞受賞者からさらに画期的な研究成果が発表されることを期待している」と、「神戸賞」の概要について紹介した。

第2回「神戸賞」で大賞を受賞した東京大学大学院 理学系研究科 教授の菅氏は、生物有機化学の新領域を開拓・展開し、非天然型のアミノ酸が連なる特殊なペプチドを、細胞抽出液で合成できる「人工酵素フレキシザイム」、「遺伝暗号リプログラミング技術」や、ペプチド薬剤候補を高効率で探索できる「RaPIDシステム」を開発した。これらは独創性が極めて高く、特殊ペプチドを用いた創薬プロセスを飛躍的に効率化する優れたイノベーションとなる。合成から薬剤探索までの一気通貫した開発技術は、2006年に菅氏が創業したペプチドリームによって、大手製薬企業を中心に共同研究、サブライセンスされ、特殊ペプチド創薬に向けて世界各国の企業で技術が活用、応用されている。

今回のセミナーでは、科学コミュニケーターの加藤氏がインタビュアーを務め、「異端からの発想。特殊ペプチド創薬は常識を変える!」をテーマに、研究開発における“非常識”の価値や特殊ペプチド創薬が変える未来の社会像などについて話を聞いた。「私は、『異端は認められた瞬間に先端に変わる』を研究哲学としている。先端研究に取り組んでいる時、それは真の先端ではなくなっている。異端なことをやっていて、それが初めて認められた瞬間だけが先端になり得ると考えている」と、自身の研究哲学を語る菅氏。「特殊ペプチド創薬の研究では、遺伝暗号を人工的に書き換えることで特殊なペプチドを合成することに取り組んだが、当時、こうした発想を持つ研究者は少なく、実現は難しいと考えられていた。私が研究成果を発表したときにも、“非常識”な研究として懐疑的な目を向けられたこともあった。しかし、現在ではこの研究の価値が認められ、多くの企業で活用・応用されている」と、非常識な研究への挑戦が特殊ペプチド創薬のイノベーションにつながったのだと訴えた。

研究を社会実装することの難しさについて加藤氏に問われると、「社会実装に向けては資金面が大きな課題となる。そこで、特殊ペプチド創薬では、開発技術の事業化・商業化を担う会社としてペプチドリームを設立し、大手製薬企業との協業やサブライセンスを通じて社会実装を進めている。また、ペプチドリームは、私の研究室からは独立した組織であるため、同社が協業している製薬会社からの制約を受けることなく、自由に研究を行うことが可能となっている」と、研究・開発と社会実装はフェーズを分けて取り組む必要があるとの考えを述べた。「特殊ペプチド創薬が社会実装されることで、現在、注射で投与している抗体医薬品を、口から飲める経口薬として提供できるようになる可能性がある。そして、将来的には、様々なアンメットメディカルニーズを持つ患者に、特殊ペプチド創薬による新規治療薬を届けていきたいと思っている。そのためにも今後、多くの製薬会社やAI技術を持つスタートアップとも協業を広げていきたい」と、特殊ペプチド創薬がもたらす未来の社会像について言及した。

「異端な研究をすることはリスクをともなうため、なかなか一歩を踏み出せない研究者は多い。しかし、リスクを冒さなければ新しいものは何も生まれてこない。もちろん、絶対失敗するような研究はやる必要はないが、その研究に希望があるならば、リスクを冒してでも自分の夢に向かって進んでいってほしい。そして、夢を具現化するためのアイデアを考え、それを計画・実行することが、異端な研究を成功へと導くことになる」と、信念を持って異端な研究にチャレンジしてほしいと力を込める。最後に菅氏は、「これからの若手研究者は、積極的に海外に飛び出して、どんどん海外の研究者との共同研究に取り組むべきだと思っている。実際に現地に行くことでわかることも多く、海外の研究室や文化の違いを体験することは大きな財産になるので、ぜひ海外留学を活用してほしい」と、国際的な視点から若手研究者にエールを送ってくれた。



















