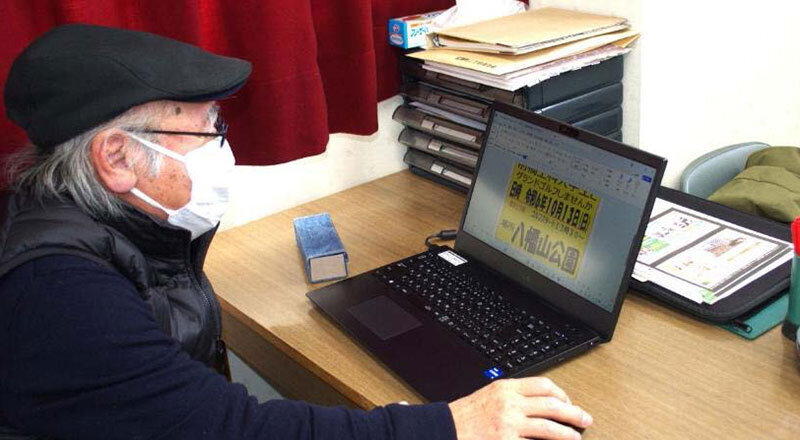
目次
市町村内の一定の区域に住所のある人々の地縁に基づいて形成され、地域住民の相互連絡や環境整備をはじめとするさまざまな活動を行う「自治会」。全国的に加入率が下がる中で、全国平均に比較すると高い加入率を誇っているのが、群馬県前橋市の「広瀬町二丁目自治会」だ。高齢化が進む中で、自治会の運営も高齢者が行うことが多いが、社会全体で進展するデジタル化に自治会とて遅れを取るわけにはいかないと、改革を進めてきた。(TOP写真:自治会が所有するパソコンを使って作業する金子副会長)
昭和時代中盤の新興住宅地として開発が進み、人口が増えたことを背景に、1976年に自治会を創設

前橋市は市制施行から130年超を数え、群馬県の県庁所在地であると同時に、県内初の中核市に移行した歴史を持つ。昭和中期の1960年には首都圏化都市開発区域に指定され、多くの工場誘致を実施した。
広瀬町はそうした工場誘致を背景に、1966年に市営・県営住宅などが建設され、県内最大規模となる広瀬団地の造成が進められた、当時の新興住宅地として開発されてきた(広瀬団地は、県営住宅730戸、市営住宅1,535 戸、群馬県住宅供給公社(以下「公社」という)賃貸住宅112戸、公社分譲住宅281戸等からなる県内最大規模の住宅団地です)
「当時はまだ私も子どもでしたから、はっきり認識していたわけではないですけど、前橋市の中心部などに住まいが足りなくなってきたということだったんでしょうね」と解説するのは、広瀬町二丁目自治会の山田公男会長だ。山田会長によると、広瀬町二丁目自治会の世帯数は現在、およそ1,150世帯ほど。周辺を含めた「上川淵地区」の中でも、比較的大きな自治会にあたるという。
金子博元副会長が「当初は隣接する後閑町などの名前を冠した自治会だったようですが、1976年4月に正式に『広瀬町二丁目自治会』という名で動き始めました」と解説する。2026年4月で実に創設50周年を迎える歴史を持った自治会なのである。

人口や世帯数はピークアウト、コロナ禍以降に地区行事の参加率が低くなったことが課題だが、1,000を超える世帯数を抱え、今なお95%の高い加入率を誇る

広瀬町二丁目の世帯数はピーク時には約1,300世帯あったという。広瀬団地の造成が進められた頃は第2次ベビーブームにもあたり、世帯ごとの家族の人数も現在よりは多かったため、当然ながら世帯数、人口ともにピークアウトしているが、それでも約1,150世帯が自治会に加入。あまりにも多数の世帯を抱えるため、広瀬町二丁目自治会自体を四つの区に分割し、2~5区にそれぞれ区長を置いて、自治会を管轄している。金子副会長は3区の区長も兼任する。
山田会長によると、「区によって多少のばらつきはありますが、各区におよそ300世帯があって、そのうち自治会に非加入の世帯はそれぞれ15世帯ほど。ざっと全体の5%ほどですから、加入率はおよそ95%ということになります」という。非加入世帯としては、新たに引っ越してきた人たちが、自治会へ加入しないケースが多いという。
総務省のサイトで公開されている「地域コミュニティに関する研究会 報告書」によると、「全国600市区町村における自治会等の加入率の平均(単純平均)」は、2010年に78.0%だったものが、2020年には71.7%まで減少。年を追うごとに漸減してきた。市区町村の人口規模などによってばらつきはあるものの、広瀬町二丁目自治会の約95%という加入率の高さは、近年の自治会離れが騒がれる中では誇れる数字と言ってよさそうだ。
「都市部などでは、自治会が維持・管理しているゴミ出し場所の利用について、自治会員とそうでない人の間で問題が起きているなんてニュースも聞きますが、同様のことはうちの自治会員からも聞くことがあります。こうした問題は日本中のあちこちで起きていることなのかもしれないですけど」と山田会長は指摘する。
広瀬町二丁目自治会では毎月会費400円を集めており、それを使った行事が長年、さまざまな形で行われてきた。目玉となる関東地方各地を目的地とする日帰り旅行は、今でも大型バス4台が連なり、200人規模が参加するという恒例行事。だがその一方で、地区運動会やソフトボール大会、グラウンドゴルフ大会など、いわゆる地域レクリエーションへの参加者が、2020年の新型コロナウイルス禍以降はめっきり減ってきた。コロナ禍後もその傾向は変わらないという。
金子副会長は「行事だけでなく、自治会事務局がある広瀬町二丁目集会室などでは、ダンス教室やヨガ教室なども行われていましたが、コロナ禍が何年か続いた間に、ほぼすべて消滅してしまった状態です。もちろん、コロナ禍も明けましたし、改めてそうした教室をやってもらうことについては全く問題ないのですが、先生やインストラクターが高齢になったケースも多く、『いい機会だから教室自体をやめましょう』という形になったものもあります」と話し、コロナ禍後の自治会活動や地区が活発に動いていない状況に気をもんでいる。
新型コロナウイルス禍で必要になった自治会運営業務のデジタル化 前橋市からのタブレット端末貸与も契機に
山田会長が自治会長に就任したのは2024年4月。広瀬町二丁目自治会としては4代目の会長にあたるが、それ以前も役員として自治会運営に携わってきた。自治会役員も自治会の会員自体も高齢者が多いとあって、「前会長も、さまざまな連絡事項については、紙ベースでのやり取りをしていました」と金子副会長は振り返る。金子副会長はパソコンなどの扱いにも明るく、自ら個人所有のパソコンなどを使い、書類も自前で作るなどしていた。
そうした中、2020年からはコロナ禍に見舞われ、毎年恒例の日帰り旅行も中止にせざるを得ない状況が数年続き、旅行費用に充当されていた自治会予算も余ってしまう状況が続いた。
一方、前橋市は2023年度から、市内全24地区284自治会を対象に、タブレット端末を無償で貸与する事業を始めた。タブレット端末貸与開始時点では、自治会事務局や広瀬町二丁目集会室にはWi-Fi設備がなかった。いくら回線契約がされているとはいえ、Wi-Fi設備の有無で使い勝手も異なる。そこで、自治会予算を活用し、2023年12月から事務局にWi-Fiを導入した。
こうして、デジタル化への一歩を踏み出した広瀬町二丁目自治会。タブレット端末を使えるようになるまでは、前橋市からの連絡は郵便によるところが大半だった。「何かの会議の出欠にしても郵便で返信・返送してくださいというものが多かったからね。それが今では、タブレット端末上でボタンを押せば済ませられるようになりました」と金子副会長は、便利さを享受する。
山田会長も、「少し前には、市のほうも『必ず文書にて』などと言っていたものですけれどね」と同調。「近くの川沿いに細い道があるんですが、近隣の住民の方から『車の交通量が多くて子どもが危ない』という声が届きまして。そのことに関して市に陳情しようと思うと、以前だったら全て紙に書いた上で、郵送したり直接届けたりしていました。今は道路の状況がわかるような写真を添えて担当課にタブレット端末から陳情書を送ればOK。そんな事例ひとつとっても、ものすごく効率的になりましたよね」と、スピード感を噛み締めている。
タブレット端末上のみでは、書類などが見えづらいという高齢者ならではの悩みもある。そこで、複合機を刷新し、端末で閲覧できる情報を複合機に送るアプリを導入。貸与されたタブレット端末を、便利に利用できる環境に整えた。同時に、金子副会長以前もパソコンに詳しい人が私物のパソコンを自治会運営業務に使っていた状況を改善し、自治会としてのパソコンを導入。一歩一歩ではあるが、着実にデジタル化を進めている。
自治会員もデジタルでやり取りできるようになれば、さらに自治会運営の効率や利便性は上がる

前橋市役所の各担当課とのやり取りはタブレット端末を通じて行うことで、利便性は格段に上がった。以前なら現地調査を含め、トータルで1ヶ月ほどかかることもあった陳情が、2、3日で完結するケースも出てきた。ただ、自治会運営側がデジタルの便利さを享受する一方で、実はまだまだ課題が多い。
「川沿いの細い道の危険性などについては、その近所の方から情報を受けて、自治会役員が直接話を伺いに行きます。まだそういう情報をタブレットやスマートフォンを使って受けることはしていないのが実情です」とは金子副会長。自治会員の特に高齢者などは、スマートフォンを持っていても使いこなせていないケースが多いというのだ。さらに、いわゆる「ガラケー」派の高齢者も一定程度いるという。
「スマートフォンを持っている高齢者でも、LINEの存在を知っているのに、使ったことがない人も多い。スマートフォンを電話としてだけしか使っていない人は本当に多いんです。なのでまずはLINEなどを使ってもらえるようになり、運営側と自治会員、あるいは自治会員同士の間でスムーズにやり取りができるようになれば。そこの普及が今後、進んでいけばと思います。そうすれば、例えば道路が凸凹になっている状況なども、情報と同時に写真を送ってもらうこともできるようになるし、運営側も状況をすぐに確認できる」と金子副会長は展望する。
自治会員のうち、どれほどスマートフォンを使いこなせている人がいるかは現状では把握していないが、「70歳を過ぎる世代ぐらいから、電話としてしか使わない方が多くなるように感じています」と金子副会長は話す。
回覧板なども、情報を一斉伝達できるようになるか

これらの複合的な背景から、自治会内で情報を一斉伝達しようとすると、時間がかかっても、昔ながらの回覧板に頼らざるを得ない状況だ。
「例えば人気の日帰り旅行にしても、参加者数の確認などをしている際に『あれ?うちには旅行の話は回ってこなかったよ』みたいなお声をいただくこともあります」と山田会長。「回覧板が最後の方まで回り切るまでのタイムラグなどもあるし、お留守の方を飛ばして先のお宅へ回覧板が回ってしまい、飛ばされたお宅の方が旅行のことを知らなかったりすることも、紙ベースの回覧板では起こりうることです」と実情を明かす。
金子副会長は「そういう漏れをなくすためにも、受け手側である自治会員の方々もデジタルで情報を受け取ってもらえるような環境にしたいですね。私の目が黒いうちに実現してみたいことです」と説明する。
自治会員がタブレット端末やスマートフォンを使いこなせるようになれば、そうした情報伝達の漏れを防ぐことはできそうだ。「スマートフォンを少しでも使えるようになりたいと、高齢者向けのスマートフォン講習会開催を望む声も自治会員から出始めています。市に対してそういう陳情を発信することも、デジタルならすぐにできますね」と金子副会長。さらなる自治会運営や自治会員の利便性アップのために、今後も骨を折っていく方針だ。
企業概要
| 団体名 | 広瀬町二丁目自治会 |
|---|---|
| 住所 | 群馬県前橋市広瀬町2-25-4 |
| 設立 | 1976年4月 |
| 加入世帯数 | 約1,150世帯 |




















