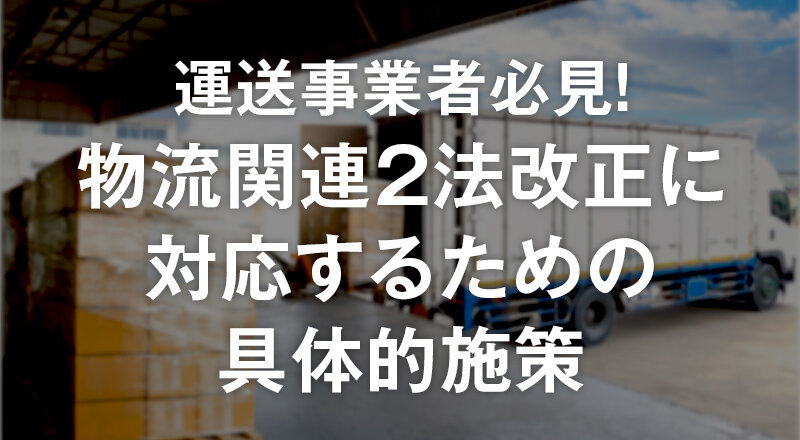
2024年に改正された物流関連2法は、2025年4月から順次施行される予定です。
物流関連2法の「2法」とは、「物資の流通の効率化に関する法律」(旧「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」からの改称)、と「貨物自動車運送事業法」の2つの法律を指しています。
今回の記事では、改正法の施行に向けて運送事業者がどのような対応を取るべきかについて解説します。
なお、改正内容のポイントは、「物流関連2法改正の基本:企業が知っておくべき重要ポイント」を読んでいただくとよくわかります。
物流関連2法の改正を受けて運送事業者が取るべき対応
| ほとんどの運送事業者が実運送体制管理簿の作成・管理をしなければならない |
|---|
今回の法改正により、荷主から発注を受けた企業が、協力会社に運送業務を再委託(下請け発注)する場合、実運送管理簿を作成することが義務づけられました。
ほとんどの運送事業者は、業務の繁閑に対応するため、協力会社への再委託(下請発注)をおこなっています。
つまり、ほとんどの運送会社が、今回の法改正により、必ず実運送体制管理簿や運送契約書を作成しなければならなくなったのです。
実運送体制管理簿の書式は任意とされており、法律で定められた書式はないため、表計算ソフトや、場合によっては紙のノートでも作成することはできます。
しかし、実運送体制管理簿は、「だれが」「なにを」「どの区間」運んでいるのかを明確にするための記録ですから、配車計画と密接に関係しています。
したがって、配車計画の作成・管理と、実運送体制管理簿の作成・管理とを別々に考えて実行するのでは効率が悪く、運行管理者や事務担当者の事務作業が大きく増えることになります。
| システム導入による効率化の契機と捉える |
|---|
配車計画の作成・記録から、実運送体制管理簿の作成までを連携しておこなえるシステムがあれば、運行管理者の作業効率は大きくアップします。
現在、配車計画のシステムを導入している運送会社では、そのシステムと連携して実運送体制管理簿の作成ができるシステムの導入を検討するとよいでしょう。
また、配車計画の管理システムを導入していない場合、これを機に、配車計画から、実運送体制管理簿の作成・管理までを統合して扱えるシステムの導入を検討するとよいでしょう。
デジタルタコグラフなどとあわせて利用すれば、配車計画・運行記録・実運送体制管理簿から、労務管理までを一気通貫でおこなうことが可能になります。
システム化によって、これまで属人的に管理されていた配車計画を共有化、標準化することは、スタッフの若返りや事業承継をスムーズに遂行していくためにも必要なことです。
| コスト構造など計数管理の重要性が高まる |
|---|
下請取引健全化については、実運送を担う事業者が負担する費用を把握し、それを考慮した報酬を支払うことや、荷主に対しても適正な報酬を求めるように交渉することなどが努力義務とされています。
これまでは、荷主が提示する運送料を基準として、トップダウンで協力会社に支払う報酬額を定めることが普通でしたが、これからは逆に、下請事業者が必要な金額からボトムアップで荷主へ請求する料金を見積もらなければならないということです。
荷主との運送料交渉のためにも、労務コストをはじめ、客観的で妥当な原価の把握に務める必要があります。
労務費、人件費、燃料費などをはじめとした数値管理をこれまで以上に徹底して、計数管理に基づいた経営管理を進める必要があります。
荷主の努力義務もシステム化で対応可能
物流の効率化には、運送を依頼する荷主側の協力も不可欠です。今回の法改正では、荷主企業にも、物流効率化のための努力義務が課されています。具体的に求められている内容は、以下のようなものです。
①バラ積み、バラ降ろしなどによる非効率な荷役作業削減のためにパレットの利用促進を図る
②パレットの規格違いによる積み替え作業等を削減するために標準パレットの導入推進を図る
③ドライバーに運送業務のみを行わせ、ドライバーの負担軽減のために荷役分離の実施を検討する
なお、特定事業者以外の事業者においては努力義務とされていますが、取り組み状況については国土交通省による指導・助言や調査・公表の対象となっています。
まとめ
運送業界における人手不足は深刻化しており、それに対応するためには、業務を効率化し、生産性を向上させる取り組みを行っていく必要があります。
今回の法改正は、運送事業者にも荷主にも様々な対応を求めるものとなっています。しかし、その対応を通じて経営のシステム化や計数管理の強化を進めることができれば、それは結果として経営の効率化や生産性の向上につながっていくでしょう。

玉川 豪史

中小企業応援サイト 編集部 ( リコージャパン株式会社運営 )




















