近年、世界中の多くの人が環境保護や人権保護など社会的課題対策に関心を持ち、実際の消費行動で示す流れが出てきている。このような行動をエシカル消費というが、言葉は知らなくても実行している消費者は少なくない。
株主や消費者に向けたメッセージとしてSDGsを意識している企業は増えてきているが、これからはエシカル消費もさらに意識するのがよいだろう。
本記事では、SDGsのなかでも人々の消費行動に直接影響する「エシカル消費」について解説する。
目次
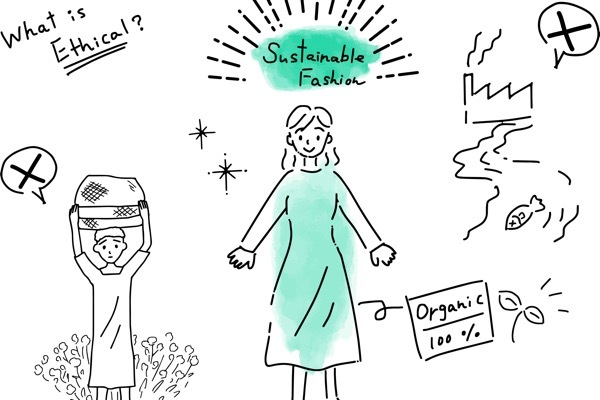
エシカル消費とは?
エシカル消費とは、消費者それぞれが各々の社会的課題の解決を考慮し、課題に取り組む事業者を応援しながら消費活動を行うことをいう。具体的にいうと人や社会、環境、地域に配慮した製品やサービスを選んで購入することで、例えば次のような行動が挙げられる。
【人や社会への配慮】
・フェアトレード商品を買う
・障害者支援につながる商品を買う
・寄付付き商品を買う
【環境への配慮】
・エコ商品や省エネ製品を買う
・リサイクル製品を買う
・オーガニック製品を買う
・サステナブル・シーフードを買う
・放し飼い鶏卵を買う
【地域への配慮】
・地産地消をする
・被災地を応援できる商品を買う
・伝統工芸品を買う など
そもそもエシカル消費の「エシカル(ethical)」には、日本語では「倫理的・道徳的」という意味がある。つまり単に価格や品質、産地、機能性などを購入の選択基準としているわけではない。主に以下のような点にも考慮しながら選択しようという考え方である。
- 商品がどのように生産・流通しているか
- 製品を製造するにあたり不都合を被る人がないのか など
SDGs視点で見るエシカル消費
エシカル消費に取り組むうえで知っておきたいのがSDGs(持続可能な開発目標)との関係だ。SDGsという言葉自体は、近年多くのメディアで見聞きするため知っている人も多いだろう。「2030年までに持続可能な世界を実現しよう」という世界的な目標のことで、2015年に国連で採択され193の国連加盟国がこれに合意している。
SDGsは、17の分野ごとに目標が設定されており、そのうち12番目の「つくる責任 つかう責任」にエシカル消費が該当する。つまりエシカル消費は、消費者だけに課せられている責任ではないのだ。作る側や売る側の事業者、そして消費者と事業者をつなぐまちづくりを行う側の行政の3者が一体となって社会的責任を受け止め、実現していくべきものである。
消費者
消費者は日常的な消費活動を通して課題の解決に貢献できる立場にある。その際、購入する商品の背景に社会や環境、労働に過度な負担が与えられていないものであるかという観点で商品・サービスを選択する。なぜならエシカルな商品やサービスを選ぶ消費者が増えるほど、事業者もエシカルな商品・サービスを生産・販売するようになるからだ。
行政
行政は人権や環境に配慮したまちづくり、地産地消、消費者教育などの取り組みをする立場だ。例えば、消費者と事業者の協働によるWin-Winの関係の構築、地域の活性化などに取り組む責任がある。
事業者
事業者はエシカルな商品・サービスを供給する立場にある。企業の社会的責任の重要性を認識し、サプライチェーンの透明性向上を図るのが役割だ。またエシカルな商品・サービスを企業競争力の新たな基準とした差別化に努めることが大切である。これにより利害関係者からの信頼感を獲得し、企業イメージの向上につなげることが期待できるだろう。
企業がエシカル消費に取り組むべき理由
本来、エシカル消費とは消費者が行う行動だ。しかし昨今エシカル消費は、企業がビジネスチャンスをつかむためにも重要な活動となっている。なぜなら「仕入れや原料調達を行う」「社内の消耗品を購入する」といった場合、事業者がエシカル消費への取り組みをしたり、消費者へエシカル消費を促したりすることは経営や業績へのメリットにつながりやすくなるからだ。
企業イメージが高まる
商品・サービスだけでなく、企業の活動に対する消費者や投資家の注目度が高まっている時代においては、イメージアップが期待できる。例えば「消費から持続可能な社会をつくる市民ネットワーク」では、毎年産業別に対象企業を絞り、企業がエシカルな方法で事業を行っているかどうかを多面的に調査して10段階の成績をつけて発表する「企業のエシカル通信簿」をウェブサイト上で公表している。
同ネットワークの目的は企業批判ではなく、サステナブルな社会づくりに貢献することであるが、目的はどうであれ、企業イメージが高まると、消費者・投資家からの信頼を得られ、潜在顧客や顧客の獲得が期待できる。
売上向上への可能性が高まる
2022年に消費者庁が行った調査では、「同じようなものを購入するなら環境や社会に貢献できるものを選びたい」という人が53.8%と過半数いることが分かる。他にも環境問題や社会問題の解決・貢献、節約・ムダの削減を理由にエシカル消費に取り組もうとしている消費者は多いようだ。
また同調査では、世代が若くなるほどエシカル消費の認知度が高くなっている。特にZ世代と呼ばれる年代は「言葉も内容も知っている」という人が他の世代に比べて最も高い。Z世代は、個性や自己表現を重んじ、社会正義や環境問題に敏感な人が多く、消費においてもブランドよりも個々の製品や経験により価値を認める傾向がある。
トレンド、時事問題に即座に反応し、購買につなげる傾向があるため企業がエシカル商品を供給すればエシカル消費の意識が高い顧客層を獲得し、売上向上が期待できるだろう。
従業員の意欲向上につながる
企業市民として社会的課題解決に貢献できる会社であることは、そこで働く従業員のモチベーションアップ、ひいては従業員エンゲージメントの向上につながる。
消費者の倫理的消費行動を積極的に促すために
消費と供給の関係は、「ニワトリとタマゴ」の関係のようにどちらが先かは明確にできない。しかし供給側である事業者は、消費者がエシカル消費をどの程度意識しているかを知り、消費者のニーズに応じた商品・サービスを供給することが必要である。もちろん一般的なマーケティングでも行っているように消費者の消費行動を促すことも重要だろう。
上でも少し紹介したが、以下で消費者庁が調査・公表している「『倫理的消費(エシカル消費)』に関する消費者意識調査報告書」の結果の一部を紹介するのでぜひチェックして欲しい。事業者にとってエシカル消費に向けた取り組みの重要性が増していることも分かるはずだ。
言葉の認知度
2022年の調査によると「言葉および内容を知っている」人は7.6%、「言葉のみ知っている」人は19.4%で、合わせて26.9%と認知度は低めだが、2020年度調査の12.2%と比較すると2倍以上に向上している。
エシカル消費に対するイメージ
2020年調査では、エシカル消費を「これからの時代に必要」と考える消費者は51.8%と過半数であった。実際、2022年の調査では「特にエシカル消費につながる行動をしない」という人が23.6%で、あとは何らかの行動を行っている。エシカル消費を必要と考え、実際に行動に移した人が増えてきていることが読み取れる。
エシカル商品・サービスの購入状況および意向
エシカル消費につながる行動として、エシカル消費につながる商品の購入状況に関する質問に対しては、全体の28.8%の人が「エシカル消費につながる商品を購入する」と応えている。ただし、エシカル商品の購入は認知度との高い相関関係があることが窺える。エシカル商品の購入意向はエシカル消費の内容まで知っている人が最も高くて55.0%。言葉のみ知っている人が42.8%、言葉も内容も知らない人は22.3%と最も低い。
企業がエシカル消費に取り組む際のポイント
エシカル消費を推進することは、これからの経営において必要不可欠といえそうである。しかし取り組む際には、以下のポイントに注意することが大切だ。
コスト増の可能性がある
エシカル商品の種類にもよるが、例えば農作物でいえば化学肥料不使用栽培は使う場合に比べて生産コストがかかる傾向がある。またエシカル商品であることを示す認証ラベルを取得するためには、第三者機関に認証検査の申請や費用の支払いが必要だ。
商品価格が高くなりやすい
コスト増は、商品価格に反映するのが通常だ。価格が高めでも安心・安全・エシカルな商品を購入したい消費者がいないわけではない。しかし価格次第では、購入意欲があっても購入できない消費者もいるだろう。企業の社会的責任が重要だとはいえ、消費者の購買力を顧みず高い価格をつけると企業イメージや信頼の面で逆効果になる可能性もあるため注意が必要だ。
エシカル消費取り組みに対するアピールと実態へのギャップに注意
認証ラベルや広告・宣伝などでエシカル消費の取り組みをアピールしたとしても、実態とのギャップがあれば、かえって不買運動など消費者離れにつながる可能性がある。先に紹介した「企業のエシカル消費通信簿」のように、目的は企業や社会にプラスになるためのものでも企業の実際の行動を調査し、評価として公表する動きはさらに広がっていくことも考えられる。
SNSでも、すぐに拡散される時代であることを意識しておこう。
業種別エシカル消費への取り組み事例
最後に事業者としてエシカル消費にどのような取り組みができるのか、すでにエシカル消費への取り組みをしている「アスクル」の例を紹介しよう。自社での取り組みへの参考としたり、事業内容によっては実際に参加したりするのもいいだろう。ぜひ参考にして欲しい。
商品破棄ロス削減の削減や物流の2024年問題に貢献する「アスクル」
アスクルは、BtoB向け通販サイト「ASKUL」と個人向けの通販サイト「LOHACO」の両輪で事業展開している企業だ。供給側でも消費側でも同社を利用している企業は多いかもしれない。同社は、未開封で品質上問題ないにもかかわらず、「パッケージデザインが古い」「売れ残った」などの理由で「商品を廃棄せざるを得ない」という多くの事業者に接していた。
そういったなか個人向け通販サイト「LOHACO」で「Go Ethical」を展開。品質に問題のない商品を廃棄せずに、シークレットセールとして販売することで廃棄ロスの削減につなげている。なお、その際には「特売セールで安価で買える」「破棄ロス削減(環境問題)で安価で買える」といった違いをGo Ethicalのなかでしっかりと説明し、消費者理解を得ることに努めている。
Go Ethicalのコンセプトに賛同する企業数も着実に増え、2024年2月20日時点で累計廃棄削減数は約130万個を超えた。
またYahoo!ショッピング内で展開しているLOHACOでは、消費者がお得にポイントを貯めたい気持ちと注文発送が多くなる物流事業者への負担削減の双方を調整すべく「おトク指定便」を提案。これは、注文をお得な日にして注文の配送日を柔軟に設定できるというもので、物流の2024年問題の削減に貢献している。
できることからエシカル消費に取り組んでみよう
エシカル消費が「どのような行動」で、社会や環境、人、企業に「どのような効果」をもたらすのかご理解いただけただろうか。SDGsの12番目の目標である「つくる責任 つかう責任」にあるようにエシカル消費で社会的課題を解決していくためには消費者の行動だけでなく、企業もエシカルな取り組みをする必要がある。
すぐに企業イメージのアップや顧客拡大とはならなくても、対内、対外でのエシカルな取り組みを続けることで業績向上につながることも期待できる。今回紹介した事例を参考に、できることからエシカル消費に取り組んでみてはいかがだろうか。
文・續恵美子(CFP®)





















