チームビルディング研修を実施したものの、「効果が見えない」「一過性のイベントで終わる」などの悩みを抱える人事担当者は少なくない。しかし、戦略的に設計・実施されたプログラムは組織パフォーマンスを大きく向上させる。
本記事では人事責任者のためのチームビルディング研修の実施に際してのポイントや、期待できる3つの効果や注意点を解説する。(文:日本人材ニュース編集部)
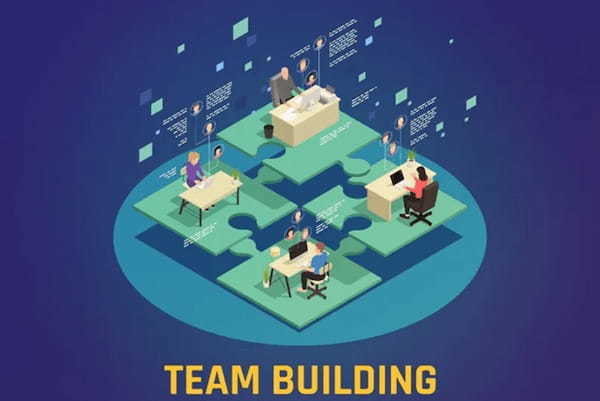
目次
チームビルディングとは

チームビルディングとは、メンバーの能力や経験を最大限に引き出し、高いパフォーマンスを上げるチームを作る体系的なプロセス。単なる親睦行事ではなく、組織開発の手法として位置づけられ、個々のスキルや能力を発揮しつつ、共通の目標達成に向けて協働できる状態を構築するための取り組みである。
チームビルディング研修で得られる3つの効果

チームビルディング研修の実施によって得られる効果は、単なる社員間の親睦強化にとどまらない。これから紹介する3つの効果は、人的資本経営の視点からも重要な投資対効果として評価できる要素である。
組織目標達成に向けた集合知の形成
チームビルディング研修は、個人の成果主義から組織全体の目標達成への意識変革を促進する。VUCA時代において、単独での問題解決が困難な複雑な課題が増加しており、多様な視点を統合した集合知の活用が不可欠となっている。
心理的安全性の確立
心理的安全性が確保された環境では、失敗を恐れずに意見交換ができるため、組織内の知識共有が活性化する。チームビルディング研修で培われる「発言しやすい雰囲気」と「相互尊重の文化」は、心理的安全性の確保を促進し、失敗を恐れない意見交換ができるためデジタル変革時代における最重要の組織資産といえる。
個人と組織のパフォーマンス最適化
チームビルディング研修を通じて、各メンバーの強みと弱みの相互理解が深まることで、適材適所の人材配置と効果的な協働体制の構築が実現する。また、「Who does What」が明確になることで、責任の所在が明確化され、意思決定の迅速化にも寄与する。
チームビルディング研修の導入事例

チームビルディング研修は多くの大手企業で戦略的に導入されている。ここでは、業界をリードする企業の事例から、導入目的、手法、そして成果について分析する。
サミットの事例:パラスポーツを活用した新入社員研修
サミット株式会社は、例年実施していた新入社員合宿研修を、感染症対策として2020年に座学中心の短縮版に変更した。その結果、本来研修で期待されていた新入社員間の関係構築や交流機会が大幅に減少するという課題が生じた。
この課題解決のために、同社は「ボッチャ」というパラスポーツを研修プログラムに導入した。ボッチャは「障がいの有無に関わらず平等に参加できる」「状況変化への適応力が求められる」「チーム内コミュニケーションが不可欠」という特性を持つスポーツである。
導入後の効果測定では、新入社員間の相互理解度が約35%向上し、変化対応力の自己評価スコアが導入前と比較して28ポイント上昇した。また、研修3か月後のフォローアップ調査では、日常業務における協働意識の定着が確認されている。
タニタの事例:ビジネスゲームによる組織力強化
株式会社タニタでは、営業部門における交渉力と組織的な課題解決能力の強化が経営課題となっていた。特に、高難度案件に直面した際の諦めやすさが組織文化として定着しつつある懸念があった。
同社が選択したのは「ビジネスゲーム」を活用したチームビルディング研修である。この研修では4〜5名でチームを構成し、他チームとの交渉や協力関係構築を通じて仮想事業を発展させるシミュレーションを実施した。研修設計においては、実際の業務課題を模した状況設定を行い、実践的なスキル獲得を重視している。
研修実施6か月後の効果検証では、参加者の提案件数が平均42%増加し、難易度の高い案件への挑戦意欲が社内アンケートで顕著に向上した。また、部門を超えた協力体制が自発的に構築されるようになり、組織全体の問題解決能力の向上も確認されている。
チームビルディング研修を成功に導く5つのアプローチ

チームビルディング研修を形式的な取り組みで終わらせず、実質的な組織変革につなげるためには、人事担当者が以下の5つの戦略的アプローチを実践することが重要である。厚生労働省「人材開発支援助成金」の活用実績調査によれば、研修効果の定着には事前・事後のフォローが決定的に重要であることが示されている。
経営課題と連動させる
研修の目的を単なる「チームワーク向上」といった抽象的な表現ではなく、「プロジェクト完遂率の向上」「部門間連携の強化」など、具体的な経営課題と紐づけて設定する。
研修実施前に経営層も交えた目的設定ワークショップなどを実施することで、全社的な取り組みとしての位置づけを強化する効果が期待できる。
参加者の心理的安全性の確保
研修の成功には、参加者が「評価されている」という緊張感から解放され、本来の自分を表現できる環境づくりが不可欠である。具体的には、研修の冒頭で「この場での発言は評価に影響しない」「正解のない対話を重視する」などのグラウンドルールを明示し、徹底することが効果的である。また、階層混合型の研修では、グループ分けや役割付与において権力勾配を最小化する工夫が求められる。
実務と紐づいた研修の設計
研修内容が実際の業務課題と乖離していると、「研修のための研修」という印象を与え、効果の定着が困難になる。理想的なアプローチとしては、実際の業務課題をテーマにしたアクションラーニング形式を採用し、研修と実務の境界を曖昧にすることなどが挙げられる。
多様な測定指標による効果検証の実施
チームビルディング研修の効果を適切に測定するためには、複数の指標を組み合わせたアプローチが効果的である。具体的には、以下の3層での測定が推奨される。
・参加者の主観評価(満足度、有用性認識など)
・行動変容の観察(発言頻度、協力行動の増加など)
・組織パフォーマンス指標(生産性、イノベーション創出件数など)
特に、研修前と3ヶ月後、6ヶ月後の比較データを取得することで、効果の持続性を評価することが重要である。
フォローアップ体制の構築と継続的な強化
単発の研修では効果が一時的なものにとどまるため、組織的なフォローアップ体制の構築が不可欠である。具体的には、研修後のアクションプランの進捗確認ミーティング、相互フィードバックセッションの定期開催、成功事例の全社共有など、研修で得た気づきを定着させる仕組みを設計する。人事制度との連動(評価項目への反映など)も効果持続の重要な要素となる。
チームビルディング研修の注意点

チームビルディング研修を効果的に実施するためには、いくつかの注意点を理解し、適切な対策を講じる必要がある。ここでは主要な3つの課題とその解決策について解説する。
一過性のイベントで終わらせない
チームビルディング研修の課題の1つとして、その効果を一時的なものに終わらせずに持続的な組織変革につなげることがある。この課題に対処するためには、以下の仕組みづくりが効果的である:
・日常業務での実践を促す「アクションプラン」の策定と定期的なレビュー
・研修で形成されたチーム単位での定期的な振り返りミーティングの制度化
・研修内容を反映した評価指標の導入(例:チーム貢献度、協働行動の頻度など)
・研修効果の好事例を共有する社内プラットフォームの構築
特に重要なのは、研修で得た気づきや技術を実践に移す「行動変容」のフェーズを意図的に設計することである。
研修効果を測定・可視化させる
チームビルディング研修の効果を正確に測定し、経営層に対して投資価値を説得力をもって説明することは、人事担当者にとって重要な課題である。抽象的な「チームワークが向上した」という定性評価だけでは不十分である。
効果的な測定と可視化のためには、以下のアプローチが推奨される:
・研修前・直後・3ヶ月後・6ヶ月後の多時点測定
・多角的評価(自己評価・上司評価・同僚評価)の組み合わせ
・業績指標との連動(プロジェクト完遂率、品質指標、顧客満足度など)
・エンゲージメントスコアやチーム健全性指標の継続的測定
具体的な測定ツールとしては、「チーム・アセスメント・スコアカード」や「組織開発効果測定フレームワーク」などの標準化されたフォーマットの活用も効果的である。
リモートワーク環境下では異なるアプローチをする
テレワークやハイブリッドワークが標準化する中、物理的な場の共有に依存しない新たなチームビルディング手法の開発が課題となっている。リモート環境でのチームビルディングを成功させるためのポイントは以下の通りである:
・同期・非同期のハイブリッド型プログラム設計(リアルタイムセッションと自己学習の組み合わせ)
・デジタルコラボレーションツールの戦略的活用
・マイクロラーニング形式での頻度高実施(月1回の大型研修より、週1回の小規模セッション)
・オンライン空間での心理的安全性を高める工夫(ブレイクアウトルームの活用、ファシリテーション技術の強化)
特にデジタルホワイトボードや協働編集ツールを活用した「見える化」は、非言語コミュニケーションが制限されるオンライン環境において不可欠の要素となる。
チームビルディング研修を組織変革につなげる
チームビルディング研修は、単なるコミュニケーション促進の場ではなく、組織パフォーマンスを向上させる戦略的投資として位置づけることが重要である。特に昨今のハイブリッドワーク環境下では、オンライン・オフラインの両方の特性を活かした統合的なアプローチが求められる。
人的資本経営の時代において、チームの力を最大化することは組織競争力の源泉となる。戦略的なチームビルディング研修の実施を通じて、持続的な組織価値の向上につなげることが、人事部門に求められる重要な役割である。
【関連記事】
・キャリア自律を促し、個の力を引き出す新たなスキル開発手法(導入企業:NTTコミュニケーションズ)【人的資本経営を加速する みらいワークスの実践型リスキリングサービス「みらRe-skilling」】
・【著者が語る】主体的なチームを創る実践型プログラム BUSINESS WORKOUT
・行動指針策定と研修強化でマネジメント層の育成に注力【MIXI】


















