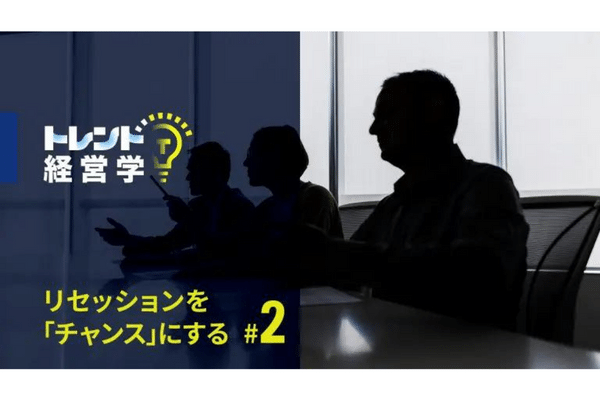
前回は、金融政策はどのように企業活動にインパクトを与えるのかという観点から、金融政策が特に経済景気後退期の企業活動をどのように変化させ、景気を浮揚させようとしているのかについての理論的なメカニズムを解明しました。今回は、リセッションを克服するための企業の投資戦略について具体的な事例を挙げながら考えていきます。
リーマン・ショック後の日立
MBAの教科書的な考え方では、企業は自社の強みを生かすべく得意分野に集中して投資していくことで、企業価値を上げるべきだとされています。戦略的には正しいのかもしれませんが、国民性や企業文化・風土も、戦略が成功するかどうかを左右する大きな要因となりえます。
具体的な例として、東芝の集中投資戦略と日立製作所の多角化戦略を対比しながら考えてみます。
日立は2009年3月期に当時の国内製造業で過去最大となる7873億円の最終赤字(米国会計基準)を計上しました。2008年秋に発生したリーマン・ショックの影響を受けたためです。2009年4月に川村隆氏が本社再建のために子会社から戻されるという異例の人事によって日立本社の社長に就任すると、「100日プラン」と称される経営方針を策定し、赤字の止血策を断行するのと同時に構造改革にも着手します。液晶テレビ用パネルや半導体、ハードディスク、携帯電話などの事業を次々と整理する一方、成長が見込まれる社会イノベーション事業(情報・通信システム、電力システム、社会・産業システム、建設機器、高機能材料)へ投資を集中させていきました。
しかしながら、事業セグメント別の売上高や営業利益の構成をみるかぎりでは、日立に顕著な変化は見られず、「集中と選択」というよりは「安定経営基盤の確立」を重視した構造改革であったと考えられます。従来から日立はそのCMソング「日立の樹」が象徴するように、日本最大の技術研究所と言ってよい存在であり、そこで開発された技術が事業化されていくことで複合企業体となっていった歴史があります。
2009年から始まる事業構造の改革も、表面的には選択と集中といえますが、企業文化にそぐわない変動の激しい事業(最たる例がハードディスク事業)から撤退する一方、ITを中核にシナジーの期待できる事業に集中していきながらも、依然として多様な事業を抱える複合企業体としての形態を維持していたことに変わりはありません。
東芝の「集中と選択」
米ゼネラル・エレクトリック(GE)や独シーメンス、そして米ゼネラル・モータース(GM)のように、過去に多角化しながら巨大化した複合型企業の業績は、悪化後は非中核事業を整理し、筋肉質になって収益力を高めてきています。日本では東芝が集中と選択を徹底した事例と言えます。
東芝の集中投資戦略は、2006年に米原子力大手ウェスティングハウス社を約6400億円で買収して以来、加速していきました。リーマン・ショックの影響を受け2009年3月期には3435億円の最終赤字(米国会計基準)を計上しましたが、ハードディスク装置事業を富士通から買収する一方、携帯電話事業やメディカルシステム事業のほか、東芝シリコーン、東芝セラミックス、東芝EMI等を立て続けに売却し、原子力事業と半導体の2大事業に経営資源を集中させていきました。原子力事業が失速するまでは「電力・インフラ」と「電子デバイス」が、それ以降は「電子デバイス」一本鎗の利益構造で、まさに教科書で見るような「集中と選択」を絵に描いたような事業展開だったといえます。
2011年の東日本大震災後に原子力事業が失速していく中で、東芝の「集中と選択」戦略は破綻していきました。また、「チャレンジ」という言葉が一時期、大きな話題となりましたが、2007年以降、社内外にプレシャーをかけることで利益をねん出し、損失を隠し続けた結果2015年に不正会計問題が発覚し、2016年3月期に4600億円、2017年3月期は9656億円もの最終赤字を計上、債務超過に陥りました。その後も今日に至るまで東芝の経営は迷走を続けています。
集中と選択、「言うは易く行うは難し」
日立は新型コロナウイルスの影響を受けながらも、2022年3月期には過去最高の最終利益(国際会計基準)を計上するなど業績も好調に推移しています。何故、東芝の教科書的とまで言える「集中と選択」戦略が破綻する一方で、多角化戦略の日立は成功しているのでしょうか。
集中と選択の根底にあるのは、ある種「狩猟民族的」な発想です。狩場に獲物がいなくなったらその狩場は放棄し、別の新しい狩場に移動すれば良いという考え方です。これを事業に当てはめれば、将来性がなくなった、もしくはなくなると想定される事業は早々に見切りをつけて売却もしくは廃止し、経営資源を将来有望な事業に転換し集中するということです。
これは言うがやすいが実行は難しく、強力なリーダーシップが必要となります。東芝も「チャレンジ」を内向きに使うのではなく、大胆な事業構造改革に向けていれば、戦略が成功していたかもしれません。
「稲作文化的」な多角化戦略
一方で、日立の多角化戦略がうまくいっているのは、単なる多角化ではなく、前述のようにITを中核にシナジーの期待できる事業に集中していきながらも、依然として多様な事業を抱える複合企業体としての多角化だったからです。不確実性が高く、事業ごとの先が読みにくい今日の経営環境下ではかなり有効な事業戦略と言えるのではないでしょうか。
このような日立の事業戦略の背景には、一定の土地に定住しながらもその時代にあった、時流に乗った事業を継続して育成していくという、日本的な「稲作文化」を背景とした企業文化があるとみることができます。台風が来たら一時避難し、暴風が収まる辛抱強く待つ、つまり、経営環境の変化で特定事業の業績が厳しくなったら、ほかの事業にウエイトをシフトしながら景気の回復を待つという考え方です。
事業戦略が成功するかどうかは、①適切な事業戦略の立案、そして②その戦略を有効に実行できる経営資源と企業文化、が必要となります。
東芝の戦略は立案時には適切だったのでしょうが、その後の経営環境の変化に対応した大胆な戦略変更が企業の体質・文化に阻害されて実行できずに破綻してしまった。一方で、日立は経営環境の変化に柔軟に対応していく企業文化を内包した事業展開ができている。これが東芝と日立の企業の明暗を分けた原因ではないでしょうか。
この先、世界的にリセッションが現実味を帯びた時には、①と②の重要性が一段と増すこととなります。日立が示してきた事業戦略と企業文化は、現代のビジネスパーソンにとって、危機を好機とするための重要なヒントが散りばめられていると言っていいでしょう。
(執筆者:斎藤 忠久)GLOBIS知見録はこちら


















