
目次
- 大学卒業後は海外への好奇心からアメリカ行きを計画 1年間のアルバイトで渡航資金を貯め、現地の飲食店にかけあって働くことに
- 入社後は自分で試行錯誤しながら仕事を覚える日々 弟も入社してお互いの得意分野でタッグを組み、新規顧客の開拓にも取り組む
- 公共工事の入札対応として積算ソフトを導入 経験への依存と手作業・手計算の時代から飛躍的に作業効率が上がった
- 5名分の業務を1名分の人件費でまかない、専門性の高い業務にも対応できる子育てママによるテレワークの外部委託で業務改善
- 会社の外部窓口であるホームページで認知度向上を図る 働きやすい職場環境のPRで反響 仕事の問い合わせや見積の依頼も
- 異業種の仲間とも学び、広い視野で経営を学んでいきたい さらに、次世代への継承も見据えて業務の「仕組み化」も進めていく
栃木県北部、那須塩原市に本社を置く株式会社大向電設は、電気工事の設計・施工を手がける企業だ。創業は1982年。現社長の渡辺将基氏の父が、勤めていた電気工事店から独立し、母とふたりで興した会社である。当時はマンションやアパートの建設ラッシュだったことから、何社ものゼネコンに幾度も足を運んで仕事を確保し、公共工事の実績も重ねていった。そして、2009年には長男の将基氏が入社。2019年からは2代目社長として陣頭指揮をとっている。2025年に創業47年を迎え、同社は取引先の新規開拓やICTを活用した業務の効率化にも積極的に取り組み、さらなる成長に向けたフェーズを迎えている。(TOP写真:勤怠や業務の一元管理を目的に2022年に導入したグループウェア。スマートフォンからも閲覧可能)
大学卒業後は海外への好奇心からアメリカ行きを計画 1年間のアルバイトで渡航資金を貯め、現地の飲食店にかけあって働くことに

2019年から同社の代表取締役として会社を取り仕切っている渡辺社長。しかし、当初は家業で働く考えはなかったという。「東京の大学に進学して英語を学びました。海外に興味があったので卒業後は1年間アルバイトをして資金を稼いで、翌年から2年半、アメリカのサンフランシスコに滞在しました。現地では日本人の経営する飲食店で働かせてもらったんですけど、最初の頃は自分の英語があまり通じなくて…」と苦笑しながら振り返る渡辺社長。知り合いなどいない現地の飲食店にかけ合い、2年半も働くタフさと行動力は渡辺社長の強みであり、持ち味だ。
そんな渡辺社長が帰国した理由は父が病に倒れたとの一報だった。帰国後、母親が当時営んでいたレストランの仕事を5年ほど手伝った渡辺社長は、病から回復した父から一級施工管理技士の資格取得を勧められ、その後父の経営する大向電設に入社した。それは、自分にとって自然な流れだったという。
入社後は自分で試行錯誤しながら仕事を覚える日々 弟も入社してお互いの得意分野でタッグを組み、新規顧客の開拓にも取り組む

「入社しても父はさほど仕事を教えてくれませんでしたから、現場で先輩たちの仕事を見ながら自力で覚えた感じです。そして、ほどなく会社を任されました。ちょうど弟も入社したので、弟は工事担当、私は全体の舵取りと職人たちへのマナー指導を担当するという分担で、会社を回していきました」(渡辺社長)
その頃から新たに手がけていったのが新規顧客の開拓だった。「父の代ではゼネコンの下請けの仕事が中心でしたが、一極依存はリスクがあります。だから私は顧客の幅を広げるべく個人のお客様や店舗、施設、工場、公共工事にも手を広げました」(渡辺社長)
「たとえ小さな仕事でも取っていき、請求書の枚数を増やそう」をモットーに営業し、紹介つながりで依頼は増えていった。こうした仕事は、従業員にも良い結果をもたらしたという。「小さな仕事だからこそ、お客様から感謝されて、喜ぶ顔も見えるので従業員のモチベーションも上がるんです」(渡辺社長)
仕事の幅も広がった。脱炭素分野ではエアコン室外機への遮熱塗装や、ブレーカーの電力消費を抑えるピークカット制御工事。そのほか補助金の情報提供や申請業務を電設メーカーとタッグを組んで手がけるなど常にニーズを読み取り、柔軟な対応を心がけている。「近年はインターネットの普及により、お客様は多くの情報をすでに入手しています。価格よりも付加価値が求められるといえるでしょう」(渡辺社長)
公共工事の入札対応として積算ソフトを導入 経験への依存と手作業・手計算の時代から飛躍的に作業効率が上がった

「いつも1年、5年、10年というスパンで先のことを考えています」と話す渡辺社長は、ICTの導入にも積極的だ。渡辺社長が入社した頃、すでにCADは導入されていたが、2015年には現場の施工状況をタブレット端末で撮影し、工事台帳を自動で作成できるソリューションを導入。現場で記録が完結するため、帰社後の写真整理などの作業が不要となり、業務効率が上がった。渡辺社長が社長に就任し、決定権が移行した2019年以降はさらに積極的にDXを促進。同年には公共工事の入札に対応するための積算ソフトを導入し、経験や手作業に依存していた時代と比較すると、作業効率が格段に向上した。
顧客管理におけるICTの活用としては2020年に名刺管理用のアプリを導入。複写機で名刺をスキャンして電子データ化することで、必要な時にすぐに取り出せる環境を構築している。

さらに2022年には勤怠管理や業務管理用のグループウェアを導入し、会社から携帯電話も支給した。これにより業務状況が一元的に把握でき、労務担当者の作業負担も軽減されている。なお、会社が従業員に支給した携帯電話はスマートフォンではなく、「ガラケー」だという。それはなぜか。「現場ではみんな手袋をしていますので、電話が鳴ってもすぐに出られないんです。それに、手袋をはずすのも煩わしいということなので、結局ガラケーになりました」(渡辺社長)
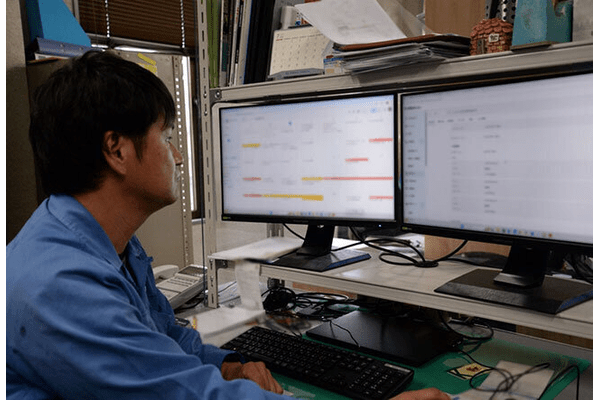
データの管理・保管については、今年はクラウドサーバーの導入を予定している同社。残る課題は資機材の在庫管理だという。「現場で資材が足りなくなって会社に戻る場合、その時間を人件費に換算すると大きなロスになります。必要な資機材の種類が多いのですが、資材管理が確実にできるようにし、出戻りがないようにしたいですね」と話す渡辺社長。資機材管理専用アプリにも関心を寄せている。
5名分の業務を1名分の人件費でまかない、専門性の高い業務にも対応できる子育てママによるテレワークの外部委託で業務改善
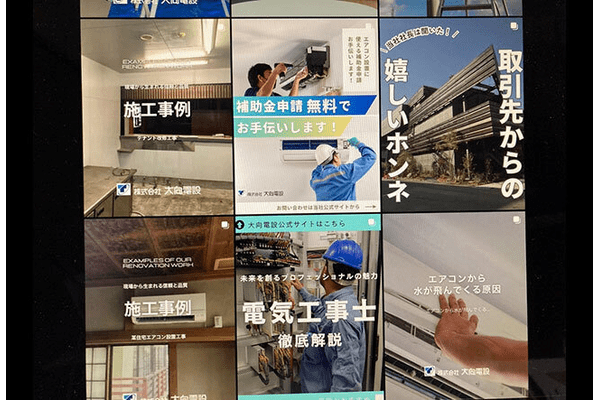
ICTによる業務効率化に次々と着手していった渡辺社長は、人材確保においても新しい試みを行っている。そのひとつが、子育て中の母親が在宅で従事するテレワークの活用だ。派遣会社に求める業務内容を伝えると、その仕事内容に適したテレワーク人材をマッチングしてくれるという。同社では現在事務所内の職場改善、人材評価、電話営業、インスタグラムの更新などを5名の人材にそれぞれ委託しており、各自が着実に結果を出していることに驚いているという。
「実際にお会いしたことがない人もいますが、専門性の高い仕事にもかかわらず、テレワークでちゃんと結果も出してくれる。なんて優秀な人たちなんだろうと驚いています」(渡辺社長)また、全員が子育て中で業務時間が短いため、5名のワーカーを1名分の人件費でまかなえることもメリットだった。
会社の外部窓口であるホームページで認知度向上を図る 働きやすい職場環境のPRで反響 仕事の問い合わせや見積の依頼も
現状では工事技術者の人材はそろっている同社だが、将来へ向けて常に若手人材の確保は必要だ。そこで同社では、ホームページにも力を入れている。漫画を駆使して仕事を説明したり、スタッフの声や自然体の写真を掲載するなど、わかりやすく伝えるよう努めている。その努力の甲斐あって、反響があるという。「あまり求人を強調すると、人が定着しない会社かと思われてしまうので、バランスには気をつけています。でも、ホームページのおかげで、問い合わせや見積依頼が寄せられることもあります」と渡辺社長は手応えを感じている。
異業種の仲間とも学び、広い視野で経営を学んでいきたい さらに、次世代への継承も見据えて業務の「仕組み化」も進めていく

渡辺社長は自分へのインプット、経営に対する学びにも積極的だ。心がけるのは、広い視野で物事をとらえることだ。
「基本的には、自分のことを誰も知らない勉強会に参加するようにしています。もちろん地元の付き合いも大切です。けれど、いつも同じ顔ぶれ、いつも地元…では成長できないと思うので」と話す渡辺社長。未知の世界に飛び込み、情報を得ることが楽しいという。その貪欲(どんよく)な姿は大学卒業後に飛び込んだアメリカ滞在時期の頃と重なって見える。
物事に縛られず、決断力と実行力で道を切り開いていくタフさを持ちながらも、5年、10年のスパンで将来を考えるという渡辺社長の大局的な視野が同社を支えている。
今、渡辺社長が取り組むのは、業務の基本的な「仕組み」を構築することだ。今後はそれをベースにさまざまな業務に応用していきたいという。それは、大向電設を次世代へと引き継ぐための準備でもある。
創業期を経て、成長期を迎えている同社。企業が衰退を招かないためには数年先の自社の課題を予測し、早くから対策を講じることが欠かせない。さらに、消費者のニーズを分析しながら柔軟かつ積極的に対応していく姿勢も必要だ。
現代に欠かせないソリューションとなったICTを武器として積極的に取り入れている同社は、次の時代に向けてどんな挑戦をしていくのだろうか。今後の飛躍が楽しみである。
企業概要
| 会社名 | 株式会社大向電設 |
|---|---|
| 本社 | 栃木県那須塩原市西朝日町9番3号 |
| HP | https://taiko-densetsu.com |
| 電話 | 0287-36-4076 |
| 設立 | 1982年3月 |
| 従業員数 | 24人 |
| 事業内容 | 電気工事設計施工 |



















