生物多様性の観点から昨年に続いて今年も400本の植樹を実施
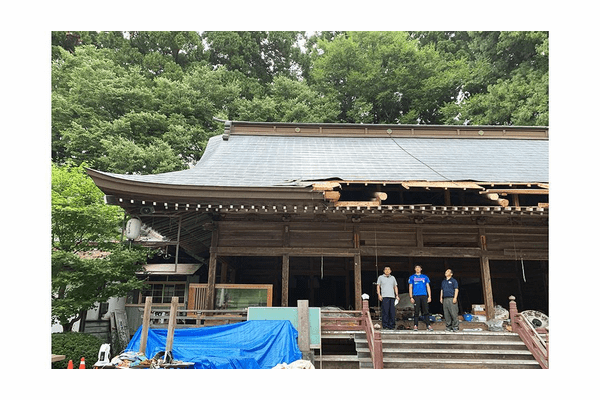
本プロジェクトでは、令和6年から3カ年計画で合計1200本の広葉樹を中心に植樹し、森の基礎をつくります。
初年度(令和6年)の第1期では、西野博士の『潜在自然植生』に基づく森の設計のもと、計400本を植樹しました。植えた樹種はコナラやケヤキなど20種類以上で、その大半は落葉広葉樹のため、冬場にいったん葉を落としてしまい見た目は寂しくなりがちですが、春に新芽が芽吹き盛んに葉を広げています。現在の段階でおよそ8〜9割が順調に根付いており、一部の樹種では既に樹高3メートルにも達しています(芽が大きく膨らんでいます)。
西野博士による森づくりは、その土地に本来あるべき自然な森の復元を目指しています。そのため、スギやヒノキのような木材生産を目的とした人工林ではなく、その地域に適した樹種を選んで植えているんです。植物が地表面を覆っている状態を『植生』と呼び、森づくりを行う際に専門用語で『潜在自然植生』と言います。
「100年後、200年後、さらには1000年先まで続く森を育てる」という長期的なビジョンのもとで、今年(令和7年)の第2期も400本を植樹。苗木たちが共生しあい、地上だけでなく地下で根を張りめぐらせることで、より豊かな生態系をつくっていきたいと考えています。
今回の第2期の植樹では、生物多様性の観点をしっかり取り入れています。落葉広葉樹は季節ごとに花や実をつけるため、小鳥などの小動物、昆虫が集まりやすくなり、そこをきっかけに食物連鎖が復活し始めます。地域の子どもたちが「昔、森で遊んだおじいちゃん・おばあちゃんのように豊かな自然と共存したい」と願う気持ちに応えたい。この2期目の植樹は、その思いをさらに確かなものにする大きな一歩なのです。
旧境内の鎮守の杜にはフクロウがいました。この土地の本来の植生に戻すことで、生態系が復活して、元々いた動物や微生物が戻ってくる可能性があります。なぜなら、植物は生態系において生産者としての役割を果たし、その存在が食物連鎖の基盤を形成するからです。フクロウが再びこの地に営巣したら本当に素晴らしいことだと思います。




















