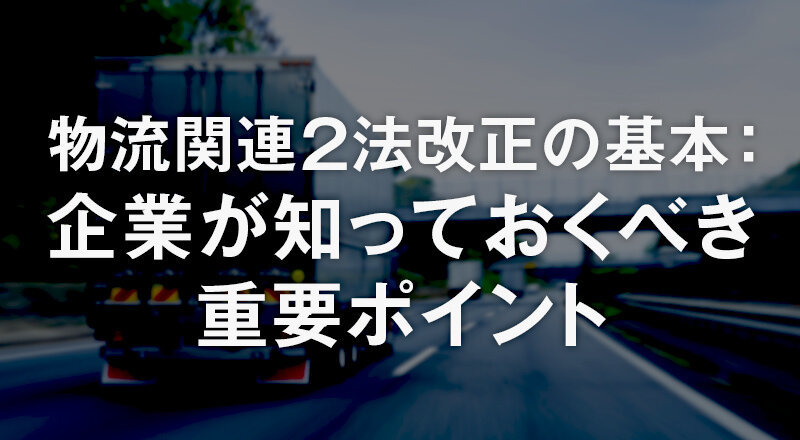
2024年5月に物流関連2法の改正がおこなわれました。この改正により、運送事業者や荷主に、様々な義務や努力義務が課されることとなりましたが、その内容は事業者の規模、荷主との関係(元請けか、下請けか)などにより異なります。
そのため、「法改正があったことは知っているけど、うちの会社はなにをすればいいのかよくわからない」と感じている運送事業経営者の方も少なくないようです。
そこで今回は、法改正において知っておくべき重要ポイントを解説します。
法改正により運送事業者に求められる取り組みについては、「運送事業者必見!物流関連2法改正に対応するための具体的施策」で詳しくご紹介していますので、そちらもご確認ください。
物流関連2法の改正とは
物量の増加と人材不足とによる物流危機は、ネット通販の台頭よりいわれてきました。2024年にはトラックドライバーの残業時間上限規制が適用されるいわゆる「2024年問題」により、人手不足は加速し「人手不足倒産」に至る運送事業者も増えています。
国の「持続可能な物流の実現に向けた検討会」では、2030年には約34%の輸送能力が不足すると試算されており、日本の産業全体への悪影響が懸念されます。(「持続可能な物流の実現に向けた検討会 最終取りまとめ」参照)
そのような危機意識から、荷主、運送事業者の双方が協力して、物流の効率化や人手不足解消を図ることを目的に実施されたのが今回の法改正です。さらに、近年、貨物軽自動車運送業において、死亡、重傷など重大事故の件数が増加していることから、その安全対策も盛り込まれました。
物流関連2法の「2法」とは、「物資の流通の効率化に関する法律」(旧「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」からの改称)、と「貨物自動車運送事業法」の2つの法律を指しています。
以下、それぞれの概要を見ていきましょう。
物資の流通の効率化に関する法律の改正
以前の「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」から、「物資の流通の効率化に関する法律」に改称されました。略して、「新物効法」と呼ばれます。本記事では、以下「新物効法」と呼びます。
同法は、「流通業務(輸送、保管、荷さばき及び流通加工)を一体的に実施するとともに、「輸送網の集約」、「モーダルシフト」、「輸配送の共同化」等の輸送の合理化により、流通業務の効率化を図る事業に対する計画の認定や支援措置等を定めた法律」(国土交通省)です。
荷主と運送事業者が協力して、物流効率化への取り組みを進めることを後押しするための法律だといえます。
| 2つの改正ポイント |
|---|
荷主、物流事業者、連鎖化事業者(フランチャイズ本部)に対して、物流効率化に対する取り組みを定めた内容が盛り込まれています。 主なポイントは以下の2点です。
(1)荷主、物流事業者、連鎖化事業者(フランチャイズ本部)が物流効率化のために努力義務として取り組むべき内容が規定されました。
①荷主
ドライバー1人あたり、運送ごとの貨物重量の増加を図るために物流事業者に協力すること。
②物流事業者
ドライバー1人あたり、運送ごとの貨物重量の増加を図るため、輸送網の集約や共同配送などの措置を講じること。
③連鎖化事業者(フランチャイズ本部)
荷待ち時間の短縮や、ドライバー1人あたり、運送ごとの貨物重量の増加を図るため、一定の措置を講じること。
なお、これらの物流効率化措置に関する国の判断基準の具体的な内容は、今後、省令において定められます。 また、主務大臣は必要に応じて、荷主、物流事業者などに対して指導、助言をしたり、調査を実施したりしてその結果を公表します。
(2)特定事業者(特定貨物自動車運送事業者等)の指定、および特定事業者が義務として取り組むべき内容を規定
新物効法において、一定規模以上の事業者が該当する「特定事業者」(特定貨物自動車運送事業者等)という分類が新たに定められました。特定事業者には以下のような義務が課されます。
①物流効率化に関する中長期計画の作成および定期報告等
特定事業者には、物流効率化に関する中長期計画を作成し、実施状況を毎年定期報告することなどが義務付けられます。
物流効率化の実施状況が著しく不十分な特定事業者は、主務大臣による勧告・公表・措置命令の対象となります。
②物流統括管理者の選任(荷主および連鎖化事業者)
特定事業者である荷主および連鎖化事業者には、物流統括管理者の選任が義務付けられます。物流統括管理者は「CLO」とも略されます。
その役割は、社内において管理的な立場から、トラックドライバーの荷役等時間の短縮や積載率向上促進などのため、貨物の運送に前後する調達、生産、保管、販売等の過程との調整を図りつつ、運送の効率化に向けた取り組みの計画や実施を統括管理することです。
その役割から、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある役員等から選任しなければなりません。
| 特定事業者の該当基準 |
|---|
どのような規模の事業者が「特定事業者」に該当するのかという基準については、現在、経産省、国交省などの合同会議により検討が進められています。現時点では、下記のような案が示されています(概要のみ)。
| 荷主、連鎖化事業者 | 取扱貨物の重量が9万トン以上 |
| 倉庫事業者 | 貨物の保管量が70万トン以上 |
| 運送事業者 | 保有車両台数150台以上 |
貨物自動車運送事業法の改正
貨物自動車運送事業法は、貨物自動車運送事業の運営を適正かつ合理的なものとし、輸送の安全、貨物自動車運送事業の健全な発達を図るための法律です。
| 4つの改正ポイント |
|---|
運送業界においてはかねてより、トラックドライバーの長時間労働やドライバー不足を起因させるものとして、多重下請構造による下請業者の低収益が問題視されてきました。
今回の改正においては、運送業界の多重下請構造の是正を図るため、(1)元請事業者における「実運送体制管理簿」の作成義務、(2)運送契約書面交付の義務化、(3)下請取引健全化の努力義務(一定規模以上の事業者においては義務)、の3点の法改正が実施されました。
さらに、(4)貨物軽自動車運送(軽トラック)事業者に対する安全施策の義務化も盛り込まれています。
以上の4点を、それぞれ見ていきましょう。
(1)元請事業者における「実運送体制管理簿」の作成義務
荷主から受託した元請事業者が、下請事業者に業務を再委託する場合、実際に運送内容を明確にするために、「実運送体制管理簿」という書類を作成し、荷主から請求があれば提示しなければなりません。実運送体制管理簿は、実際の運送(実運送)について、「だれが」「なにを」「どの区間」運んでいるのかを明確にするための記録です。
①元請事業者、下請事業者とは
元請事業者とは、「荷主から直接運送業務を委託された事業者」です。また、元請事業者が、他の運送事業者に、運送業務を再委託する場合、他の運送事業者から再委託された事業者のことを下請事業者と呼びます。
元請か下請かはあくまで委託の流れのどの段階にいるのかという点だけにより決まり、会社の規模などは関係ありません。
②実運送体制管理簿の作成頻度
元請事業者は、下請事業者に運送を委託する場合、その運送ごとに実運送体制管理簿を作成しなければなりません。
なお、実運送体制管理簿は下請事業者への再委託の際にのみ必要なものであり、荷主から受けた運送業務を自社内で担当する場合は、作成の必要はありません。
③実運送体制管理簿に記載する内容
実運送体制管理簿には、以下の内容をすべて記載します。
・実運送をおこなう事業者の商号または名称
・実運送をおこなう貨物の内容および区間
・実運送をおこなう事業者の請負階層(孫請けなら「2次」など)
など
(2)運送契約書面交付の義務化
荷主が元請事業者に運送を依頼する場合、また、元請事業者が下請事業者に運送業務を再委託する場合には、契約書を書面で交付しなければなりません。書面を交付することにより、契約の条件や責任の所在を明確にし、下請事業者への一方的に不利な契約が結ばれることを防ぎます。
①運送契約書面の作成頻度
元請事業者は、下請事業者に運送を委託する場合、その運送ごとに運送契約書面を作成しなければなりません。
②運送契約書面に記載する内容
運送契約書面には、以下のような内容を記載します。(トラック運送業における書面化推進ガイドラインより)
・運送委託者および受託者の商号または名称、連絡先等
(多重下請になっている場合、すべての委託事業者)
・委託日、受託日
・運送日時(積込み開始日時・場所、取卸し終了日時・場所)
・運送品の概要
・車種、台数
・運賃、燃料サーチャージ
・附帯業務内容
・有料道路利用料、附帯業務料等、車両留置料その他費用
・支払方法、支払期日
など
契約書面の作成に際しては、国土交通省が発行している「トラック運送業における書面化推進ガイドライン」の内容が参考になります。
「トラック運送業における書面化推進ガイドライン」(国土交通省)
(3)下請取引健全化の努力義務(一定規模以上の事業者においては義務)
下請事業者が一方的に不利益を被らないようにするため、元請事業者には発注の適正化による下請の健全化措置を講じる努力義務が求められることとなりました。なお、一定規模以上の元請事業者には、義務も課されます。
①下請取引の健全化措置
元請事業者は、下記の努力義務を負うこととなります。
・実運送に要する費用の概算額を把握し、その金額を勘案した上で利用の申込みをすること
・荷主が提示する運賃・料金が上記概算額を下回る場合は、荷主に対し、運賃・料金の引き上げ交渉をしたいと申し出ること
・下請事業者に2段階以上の再委託を制限すること
など
なお、特定事業者が上記に反する場合は、100万円以下の罰金が科されます。
②一定規模以上の下請取引をおこなう元請事業者の義務
一定規模以上の下請取引をおこなう元請事業者については、下記の措置を取ることが義務化されました。
・運送利用管理規程を策定すること
・運送利用管理者を選任し、国土交通省に届け出ること
(4)貨物軽自動車(軽トラック)運送事業者に対する安全施策の義務化
貨物軽自動車(軽トラック)運送事業者においては、過去6年間で、死亡・重傷事故が倍増しています。軽トラック事故の抑制のために、新たに以下の3点が義務化されました。
・貨物軽自動車安全管理者を選任し、国土交通大臣に届け出ること
・貨物軽自動車安全管理者に定期的に安全講習を受けさせること
・国土交通大臣に対して事故を報告すること
まとめ
物流関連2法の改正において、特に重要なポイントを解説しました。特に、実運送体制管理簿の作成については、多くの運送事業者に関係するものであり、理解を深めておく必要があります。
また、「運送事業者必見!物流関連2法改正に対応するための具体的施策」の記事で、運送事業者がどのような対応を取るべきかを解説しているので、そちらもあわせてご確認ください。

玉川 豪史

中小企業応援サイト 編集部 ( リコージャパン株式会社運営 )





















