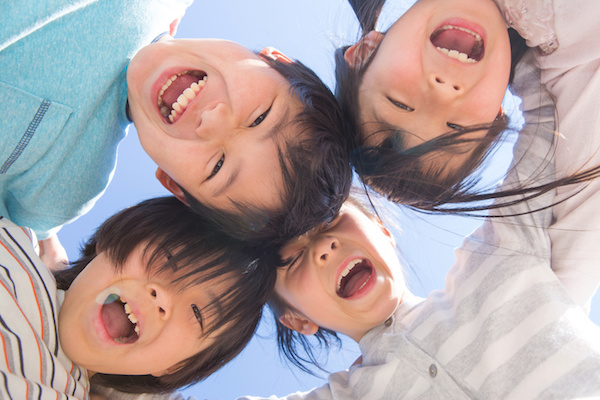
4月1日、こども政策の司令塔「こども家庭庁」が発足した。従来型の縦割り行政から脱し、子育て支援、児童虐待、いじめ、貧困対策など関連行政を総合的に調整、主導する。言うまでもなく、新たな行政機関は「異次元の少子化対策」と一体だ。3月31日に公表されたその “たたき台” では、出産一時金の引き上げ、児童手当の所得制限の撤廃、給付型奨学金の支給条件の緩和などが示された。財源の裏付けがない、「こども家庭庁」の権限が曖昧であるなど、実効性については依然不明な点も多い。とは言え、まずは一歩前進ということだろう。
少子化対策の成功事例として取り上げられるフランスの出生率が人口置換水準を割り込んだのは1970年代前半、日本とほぼ同時期だ。異なるのは予見された人口減少に先手を打っていることだ。今、日本で議論されているこどもが増えるほど税負担が軽くなるN分N乗方式をフランスが初めて導入したのは1946年、1977年には最長2年の育休を制度化、以後、保育施設の拡充、乳幼児養育支援の強化など、途切れることなく施策を打ち続ける。そして、1999年、同性婚や事実婚も税控除や社会保障が受けられる民事連帯協約(PACS)を施行する。結果、1993年に1.66まで低下した出生率は2007年に1.98,2010年には2.03に回復する。2014年以降、再び低下に転じるが、2020年1.82、2021年1.83と高いレベルを維持している。
フランスについては婚外子率の高さが強調されることが多い。ただ、ここで見落としてはならないことは “非嫡出子” という言葉自体が民法から消えたということの意味である。長らくフランスの少子化対策を担ってきたのは家族・児童・女性の権利省である。現在、これを首相府付の男女平等・多様性・機会均等担当大臣とこども担当副大臣が引き継ぐ。つまり、少子化は決して “家庭” に閉じた問題ではなく、社会全体の変化の中で解決すべき問題と認識されていて、かつ、それが政権交代を越えて国策として継続している点が重要である。
子育て世代への個別経済支援に異論はない。しかし、そもそもそれが必要とされる背景には一向に所得が増えない状況、つまり、中間層の縮小、格差の固定化という構造要因があることも看過すべきではない。こどもの未来、そして、自分自身の将来に希望が持てる社会であり続けること、これが少子化解消の最大のドライブとなる。そのためには経済を含めた「日本社会」全体の総合的、長期的なビジョンが不可欠である。産業構造、働き方、地方、そして家族の在り方それ自体のアップデートが必要であるということだ。
今週の“ひらめき”視点 4.2 – 4.6
代表取締役社長 水越 孝




















