
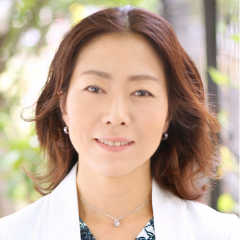
生産性をどう向上させるかは、経営者の悩みの一つだ。特に最近は、少子高齢化による働き手の減少や働き方改革の推進により、日本の企業にとって重要な課題となっている。その難題の解決のヒントになるのが「ホーソン実験」だ。
目次
ホーソン実験とは何か
「ホーソン実験」とは、労働者の生産性向上に必要な要素を導き出すために行った実験である。アメリカ・シカゴにあるウェスタン・エレクトリック社のホーソン工場で1927年から1932年にかけて実施された。
当初、ウェスタン・エレクトリック社と全米学術協会の全国調査会議で調査が実施されたが、途中からハーバード大学の教授であり、後に「人間関係論の父」と呼ばれるエルトン・メイヨーとその弟子のフリッツ・レスリスバーガーが研究に加わったことで、実施機関はハーバード大学に移った。
なお、要素として導き出されたのは、環境や時間といった物理的なものではなく、人間関係が人間心理に与える影響だった。労働者個人の心理状況や個人的な人間関係が生産性に影響を与えることを示した画期的な実験だったと言ってよいだろう。
ホーソン実験が行われた時代背景
ここで、ホーソン実験が行われた時代背景を見ていこう。
「狂乱の20年代」で生産性の向上が課題に
ホーソン実験が行われた当時は、「狂乱の20年代」と呼ばれる頃であった。第一次世界大戦が終わり、ヨーロッパ各国が疲弊している中、アメリカだけは好景気だった。軍事市場に代わって個人市場が一気に拡大するとともに人々は大量の物資を消費し、国中が活況を迎えていた。
その影響で同時期、各企業は「生産性向上」という壁にぶつかることになる。大量消費で利益を上げるには、大量生産・大量販売が欠かせない。いかに効率よく作業を行っていくかが課題だった。
当時の経営管理の中心は「仕組み重視」
当時の経営管理論の中心は、フレデリック・テイラーが提唱した科学的管理法だった。
科学的管理法とは、工場の従業員を効率的に管理する方法だ。1日の作業量と作業手順を決めて作業の標準化を図ることで、どのような人材であっても一定時間内に標準作業量を遂行できるようにすることを重視した。
さらに、「成功報酬」「不成功減収」といった賃金体系を加えて、労働者のモチベーションを上げようというものであった。実際、このテイラーの管理法を導入したことで1903年に創業したフォードは成功を収めた。ただし、その一方でこの経営管理法には問題もあった。
労働者の意欲低下や離職が問題に
科学的管理法で大量生産が可能になった一方、労働者側にはさまざまな問題が生じた。単純作業が多くなり、熟練労働者が不要となったのだ。
半熟練、不熟練労働者でもできる仕事が大半となったため、大量の移民労働者が従事した。つまり、技術や仕事そのものに熟達していない者を、単純作業中心の生産ラインに適応させ、大量生産が実現したのである。
しかし、細分化された単調な作業の反復と連続に労働者は嫌気がさし、無断欠勤や離職が企業の新たな課題となった。事実、フォードでは労働者の定着を図るべく、労働関係全般を扱う雇用部を設置したのである。
このような人事に関連する部署が、労働者の採用や訓練、配置、福利厚生を扱うようになるのと同時に、「産業心理学」という形で労働者の心理に関する学問も注目されるようになった。とはいうものの、当初は簡単な心理テストで労働者の心理を見る程度の粗末なものだった。
「人間は社会的な生き物だ。『賃金』や『就労時間の減少』といった個々の要素で一面的に労働者の心理を測るのではなく、人間関係全体の状況とその中での個々人の態度を慎重に研究すべきである」。
このように主張するメイヨーの研究に、ウェスタン・エレクトリック社の人事部長が注目し、研究調査への協力を申し出る1通の手紙を彼に送った。これを機に、ホーソン実験は始まったのである。
実施した4つのホーソン実験
実際に行われた実験と実証目的は、次の4つだった。
1.照明実験
「労働環境が生産性に影響するかどうか」を調べるための実験だ。「照明が暗い状態で作業すると生産性が下がり、明るい状態だと生産性が上がる」という仮説を置き、それぞれの環境での生産性を測定した。
具体的には、被験者集団を2グループに分けた上で、片方は照明を一定に保ち、もう片方は徐々に照明を100ワットの照明から25ワットの間で変化させ、それぞれの作業能率の変化を観察するというものだった。
仮説の通りになるだろうと多くの研究者が期待したが、実験は彼らの予測から大きく外れるものだった。明るさが一定でも変化しても、一定時間が経過すると作業効率が徐々に上がったのだ。つまり、照明と生産性は関係しないという結果になったのである。
2.組立実験
この実験は疲労と能率の関係を調べるための実験だ。無作為に女性6名を選び出し、休憩時間と就業時間を変更したり、部屋の温度や賃金関係を変えたりしながら、彼女たちに継電器のリレーをさせた。
「物理的な労働環境が悪くなれば、作業効率も悪化する」という仮説が立てられたが、実験の結果はこの仮説に反するものだった。最初は賃金や休憩時間といった条件を改善することで作業効率も上がったが、その後に労働条件を元に戻しても効率が悪くなることはなかったのである。
結果として、労働条件や待遇にいい影響がでることが判明した。
共通の友人がいたり、毎日コミュニケーションがあったりしたことでチームの連携が強化され、それがモチベーションの向上やパフォーマンスの発揮につながったと見られている。つまり、人間関係が作業効率に寄与したのだ。
3.面談実験
「賃金制度や就業時間よりも、管理体制のあり方が作業効率に影響を与えるのではないか」という仮説の下で行われた実験だ。2万人の従業員に対して1人ずつ面談を行ったのである。この面談は、急成長する工場の管理に際し、よりよい管理監督方法を編み出す意味でも必要だった。
面談した結果、従業員の満足度は賃金や就業時間といった客観的な労働条件よりも、個人の主観的な好みや感情に左右されやすいということが判明した。同じ条件であってもある者は満足だと言い、ある者は不満を述べたのである。
「特定の外部環境に関して誰もが不平を述べる」といった共通した事実を見出すことはできなかった。
このことから、「従業員の態度や行動は感情によるところが大きい」「満足度は単に相互関係や社会組織内の居場所だけでなく、その人の感情や欲求を考慮した上で測らなければならない」ものだという結論に至った。
4.バンク配線作業実験
「バンク」とは電話交換機のことだ。この実験では、従業員を職種でグループ分けし、バンクの配線作業を行わせ、その共同作業の成果を観察した。それまでも3つの実験が行われたが、これらから「現場に小さなグループがあり、それが社会統制機能を果たしている」という仮説が立てられた。
さらに利害関係のない者同士の関係や従業員同士の関係が、作業にどのような影響を与えているかも観察対象となった。
この実験では、仮説の通りインフォーマルな組織(非公式組織)の存在が発見された。しかし分かったのは、それだけではない。「上司・部下」「担当作業を行う上での関わりの有無」に関係なく、インフォーマルな組織が形成されたのだ。
さらに、労働者は自分の持てる力をすべて出し切るのではなく、状況や場面に応じて労働量をコントロールしていることが分かった。これは、労働量を増加すると、今後の作業水準が引き上げられたり、賃金単価が下がったりして、人員削減で仲間の誰かが犠牲になるからである。つまり組織の人間関係が、生産性や製品の品質に影響することが判明した。
ホーソン実験から生まれた「ホーソン効果」とは
この4つの実験によって、物理的な環境だけでなく、人間の感情や意志、他者との関係性が生産性に影響することが証明された。同時に、「ホーソン効果」も認められたのである。
ホーソン効果とは
4つの実験のうち、とりわけ注目したいのが「組立実験」だ。この組立実験の第12期では、作業時間が短縮された後、第3期の条件の悪い作業環境に戻されたのである。これまで増やされてきた休憩や軽食はなし、48時間体制で作業を行うことになった。
しかし、同じ労働環境であるにも関わらず、労働量は大幅に増加していた。ここから、人間は組織の中で社会的存在として認められ、相談を受けたりすると仕事にやりがいを感じるため、環境が悪くても作業を遂行しようとする現象が確認された。この「注目や承認がモチベーションを上げる」という現象を「ホーソン効果」という。
ピグマリオン効果との違い
ホーソン効果と同じく、人からの承認がやる気を引き出すとしているのが「ピグマリオン効果」だ。ピグマリオン効果は、アメリカの教育心理学者のロバート・ローゼンタールが提唱した心理的行動をいう。野球チームで監督が選手に期待をかけると、選手はそれに応えようとして能力を発揮するというものだ。
どちらも「他者からの期待でモチベーションが上がる」という点では同じだ。しかし、ホーソン効果は上下関係を問わないのに対し、ピグマリオン効果は「上位の立場(教える側)と下位の立場(教わる側)」という関係の中で生じる。また、ホーソン効果は相手への「注目」が動機となるが、ピグマリオン効果は「期待」がきっかけとなる。
ホーソン実験からわかる人間関係の重要性
ホーソン実験の結果から、単に給料や就業時間といった物理的な環境だけがモチベーションになるわけではないことがわかる。むしろ、人と人との関係や連携、日常会話や居場所といった人間関係が生産性を左右する。
この「人と人との関わり」の重要性は、昨今、リモートワークを余儀なくされたビジネスパーソンなら理解できるだろう。通勤時間や職場への拘束がなくなり、勤務そのものは楽にはなったものの、孤独と不安で仕事の効率が下がった人は少なくないはずだ。つまり、生産性を上げるためには、お互いに認め合い、人とつながっている感覚が欠かせないのである。
リモートワークでも、オンライン会議でできるだけ頻繁に五感を使って人と関わる機会を持ったり、相談できるメンターや機関、対面で会う機会を設けたりして、社内の人間関係を維持する対策が必要だ。ホーソン実験で得られた結果を上手に活用すれば、コロナ禍でもチームワークを維持し、生産性を上げることができるだろう。
文・鈴木まゆ子(税理士・税務ライター)





















