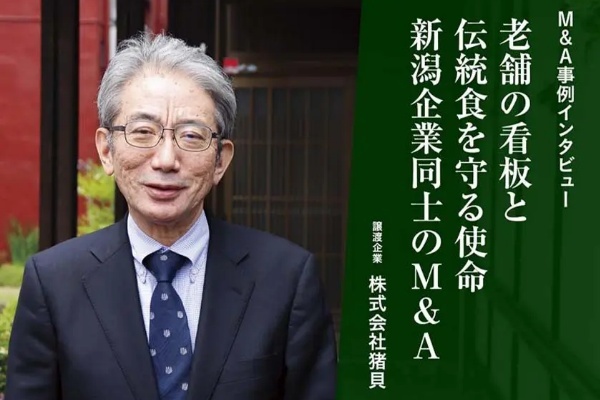
※M&A実行当時の情報
| 譲渡企業情報 | 譲受け企業情報 |
|---|---|
|
社名:株式会社猪貝(新潟県) 事業内容:こんにゃく、えご、 ところ天等製造・販売 売上高:約2.6億円(2024年2月期) 従業員数:20名(パート・アルバイト含む) |
社名:有限会社間瀬屋商店(新潟県) 事業内容:不動産管理業 |
新潟県長岡市でこんにゃくやところ天、新潟の郷土食「えご」を製造販売する猪貝は、100年以上の歴史をもつ老舗企業です。後継者不在からM&Aを決断し、4年の検討期間を経て2024年3月に不動産管理業を営む間瀬屋商店(新潟県新潟市)に譲渡しました。一時はM&Aを諦め廃業も考えたという猪貝 克浩社長(現会長)にM&A 検討から成約までを伺いました。(取材日:2024年5月17日)
4代目の後継ぎとして期待され守り続けてきた老舗の看板
――M&A成約の感想をお聞かせください。
株式会社猪貝 猪貝様:安堵の一言です。私の役割がひとつ終わったと肩の荷が下りる気がしました。 というのも後継者がおらず、M&Aが実現しなければ廃業するしかない状況でしたから。老舗の看板と郷土食の「えご」を守るために何をすれば良いのか模索を続けてきました。
――舗の看板の重圧があったのですね。
猪貝様: 当社の創業は1913(大正2)年で、こんにゃくやえごを取り扱う地元の商店として100年以上の歴史があります。私は4代目の後継ぎとして期待されて育ちました。祖父から父の代まで手弁当でコツコツ育ててきた会社ですが、1990年代にデフレの波にさらされはじめてからは、目まぐるしく変化する日本の経済背景に翻弄され、家族の支えを受けながら必死に対策に走り回る日々でした。
――デフレの時期はどのような状況だったのですか?
猪貝様: まず、平成に入って地方に大手総合スーパーが参入して全国一律で販売値が決められたことで、原料の価格変動を売値に反映できなくなりました。ディスカウントショップが登場してからは、従来の半値で売られる商品が増え、その対応に追われるようになりました。中国工場と契約して経費削減を図った時期もありましたが、製品の質が低く廃棄率も高かったことが痛手となりました。それでも2000年代の頭は低価格商品も扱い、テレビ番組をきっかけとした「ところてんブーム」が起きて、2005年には売上6億円を達成しました。
――その後の展開は?
猪貝様: ブームが去ると同時に売上が大きく落ち込み、半分まで落ち込みました。当社の商品よりもさらに安い商品を他県の同業者が出してきたことも大きかったですね。そこで視点を変え、2013年に、創業100年記念として新事業への取り組みに着手しました。そのひとつが「越後えご保存会」です。えごという、江戸時代から続く伝統的な食文化の保存へ注力しはじめたのです。えごは文化庁で掲げている「100年フード」という食文化継承の取り組みにも認定された商品でもあり、今も事業の柱となっています。

4年の検討期間を経てようやくお相手に巡り合う
――M&Aに踏み切った理由は後継者不在ですか?
猪貝様: 一番の理由はそうです。一人娘は東京で就職して、自分の道を見つけ戻らない意思を固めていました。血縁関係や従業員を後継者として育てることも考えましたが、ここ10数年で同業他社の倒産や廃業が続く厳しさの中、借り入れを抱える会社を引き継ぐのは非常に負担がかかることでしょう。そうなると、会社を畳むか、別の方に引き継いでもらうしかないと。そこで、当時お付き合いがあった金融機関からM&Aの提案をいただき日本M&Aセンターに依頼したのが約4年前でした。
――お相手との出会いまで、なぜ4年かかったのでしょう。
猪貝様: 同業者は当社とほぼ同じ業界環境ですから、相乗効果が期待できないと考えて保留にしていました。当社の独自性は大切にしたかった。県内企業の顔見知りに話を持っていくのは、もっと後だという意識がありました。しかし昨年(2023年)の2月に脳出血で倒れまして、おかげさまで後遺症はありませんでしたが、「いつ何が起こるかわからない」と心境が変化しM&Aは諦めて廃業しようと思いました。そんな中、担当者から「半年でも3カ月でも良いので、最後までやらせてください」と言われ、年末までと期限を区切り条件を広げて探すことにしました。半ば諦めていたのですが、諦めず熱意を持って探し続けてくれて、最後の最後のところで「御社に関心を持っている会社がある」と話があったのが間瀬屋商店でした。 お声掛けがあったのが2023年の12月末頃で、トップ面談が実現したのが翌年の2月の頭、3月に最終契約と想像以上にスピーディーな展開でした。担当者の最後の粘りがなければ、今ごろは会社を畳む準備をしていたでしょうね。
――トップ面談の印象はいかがでしたか?
猪貝様: 間瀬屋商店の鈴木社長は芯の通った、細かな気遣いのできる方だと感じました。当社について理解し評価してくださったうえで面談に臨んでくださり、最近の取り組みや従業員の雇用など、当面は継続してくださるとの確約をいただき、安心して話ができました。
――企業としての印象は?
猪貝様: 間瀬屋商店は江戸時代に廻船問屋からスタートして、300年以上の歴史をお持ちです。明治時代以降に鉄道が登場して業態が変容していく中、北洋漁業や船具塗料商、不動産管理業へと事業転換を行いながら、厳しい時代を乗り越えて来られました。当社も1990年代以降、デフレの影響で幾度となく厳しい状況を経験しましたから、頼もしさを感じました。
――業種の異なる企業とのM&Aに不安はありませんでしたか?
猪貝様: ありませんでした。間瀬屋商店は、将来に向け「新潟でゼロからモノを作っていきたい」という構想をお持ちで、当社とのM&Aの前に、化学農薬を使わない農産物を生産する企業も譲り受けています。伝統食文化を守ろうと奔走してきた当社と一緒になることで、食品製造業への進出を強化したいという思いを伺い、その一員として新たに再出発できることは非常に嬉しいことだと感じましたね。

M&Aに好意的な反応が多く、経営者仲間からは祝福の声も
――M&Aに対して取引先はどんな反応でしたか?
猪貝様: 取引先へは成約式の後に鈴木社長と挨拶へ行きました。M&Aは時代の風潮としても一般化していますので、身近な例として好意的に理解してくださるところがほとんどでした。経営者仲間からは「おめでとう」と言ってくださる方も多く、嬉しく感じました。
――従業員の反応はいかがでしたか?
猪貝様: 従業員に伝えたのは成約式の翌日ですが、驚くほどあっさりと受け入れられました。古参の従業員からは「お疲れ様でした」という声掛けもありました。鈴木社長から「安心・安全な製品づくりを大切にする」「待遇面は変わらない」とお話をいただいたことで、動揺もなかったのだと思います。
――猪貝の今後に期待することは?
猪貝様: これまでは経営者として、こだわる部分とこだわらない部分のバランスを大切にしてきました。これから3年間は会長として残り、食品製造のノウハウなどサポートしていく予定です。鈴木社長の人柄と手腕を拝見して、これからの100年を歩める確かな企業となれると確信しています。
――M&Aを検討する方へ向けてメッセージをお願いします。
猪貝様: 出会いがすぐになくても、粘り強く担当者と相談しながら検討を続ける姿勢が大事です。諦めるということは可能性がなくなるということですから。当社は、覚悟を決めて「ここで終わりにしましょう」と言った数日後に話が舞い込みました。幸運なことでしたが、仮に1カ月早く諦めていたら今はありません。時間が許す限り、じっくりと腰を据えて取り組むことで、先へつながる手がかりを掴めるのだと思います。 ただ、検討期間が長ければ良いということでもありません。私は、経営者が60歳になる前くらいに、方向性をきちんと出すほうが良いだろうと思います。 健康面に自信があって80代になっても現役を貫く方もいらっしゃいますが、そんな方ばかりではないでしょうから。体力的な面でも、早いうちに検討を始めることをお勧めします。

地域金融チャネル 金融法人部 コンサルタント 受川 祐太(株式会社猪貝担当)




















