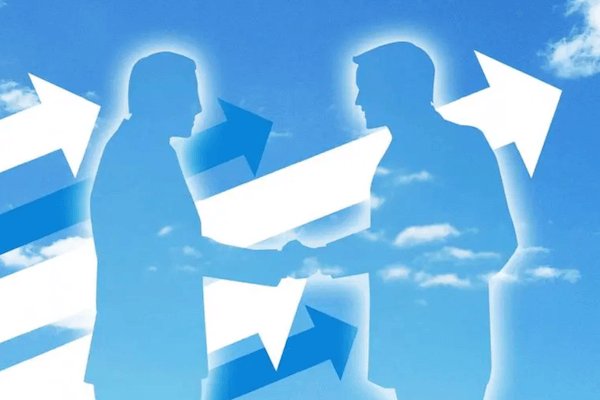
厳しい競争が繰り広げられているビジネス界では、各企業による熾烈な競争が日々行われています。これら企業同士の関係は、ライバル関係にある場合もありますが、そればかりではありません。ときには共に協力し合い、お互いの不足する面を補いながら業績を伸ばしていくことも必要だといえます。
このように、企業同士が友好的な関係を築き、互いに業務を補完し合う施策のひとつが業務提携です。そこで本記事では、業務提携とは何なのかを整理したうえで、M&Aや資本提携などとの違い、業務提携の種類やメリット・デメリット、そして業務提携の流れと実例などについて解説します。
業務提携とは?
業務提携とは、 複数の企業が経営資源を出し合い、1社だけでは解決できない問題を協力し合うことで事業成長、競争力強化を行う施策 の一つです。具体的には、企業がそれぞれに持っている技術や販売網、様々なノウハウや人材、設備やブランド力などを提供し合い、お互いが足りない部分を補い合うことでシナジー効果を創出します。
業務提携は、新規事業の参入や新製品の開発、業務縮小に伴う社内業務の外注化や販売網の拡大など、各企業の多種類のニーズに応じて色々な形で行われています。
業務提携を行う目的
自社単独で、経営に必要な全ての業務を行うことができればベストですが、残念ながら多くの場合、社内で活用できるリソースには限りがあります。また足りない部分をすべて自前で調達して埋め合わせようとすると、膨大な時間とコストがかかります。
さらにすべてを自社内で行おうとすると、莫大なリスクも覚悟することになります。人材確保や研究開発、販路開拓やブランド力を確立するためには、社内のリソースをフル活用して多くの時間をかけなければなりません。しかも、それを行ったとしても必ずしもうまくいくとは限らないのです。
このような事態を避けるために、多くの企業間で業務提携が行われています。言い換えると、 目標を達成するためのリスクやコストをできるだけ低くしつつリターンを高くする ことが業務提携の目的であるといえます。
「資本提携」「業務連携」「業務委託」「M&A」との違い
業務提携に類似する言葉として、「資本提携」「業務連携」「業務委託」「M&A」の4つがよく用いられます。業務提携との違いについてそれぞれ見ていきましょう。
資本提携とは
資本提携とは、経営権に影響を与えない程度に他企業の株式を取得し、出資によって協力関係を高めることを言います。資本提携においては、一方が他方の株式を持つことが一般的ですが、お互いの株式を持ち合う形の資本提携が行われることもあります。
出資を受ける方法は主に2つあり、一つはオーナー経営者などが所有している株式の譲渡で、もう一つが新株を発行して行われる第三者割当増資です。いずれにしても、出資を受ける側の経営の独立性を侵害しないように、引き受ける株式数は発行済株式総数の1/3未満とします。
資本提携を行うと、会社同士の結びつきがとても強くなるため両社による長期的な提携に基づく経営戦略が立てやすくなります。また、出資を受けることにより与信能力が高まるのもメリットの一つです。なお、業務提携により資本や業務の結びつきが強くなった結果、M&Aに発展する場合もあります。
このように、提携を行う両者の間に資本関係があることが業務提携と異なる点です。業務提携は、あくまで業務面での提携になります。
業務連携とは
業務連携は、実はその定義に明確なものがありません。「連携」という言葉が「互いに連絡をとりながら物事を行なうこと」を意味することから、小さいものでは業務における簡単なやりとりから、大きなものでは契約書を交わして行うものまで広範な意味を有しています。したがって、広義的には業務提携も業務連携に含まれるといえるでしょう。
業務連携は専門用語ではありませんが、一般的には企業同士がお互いに協力しながら何かを行う場合などに用いられます。
業務委託とは
業務委託とは、社内ではできない業務などを外部へ委託する業務形態のことを言います。業務を委託する側とそれを受ける側の間で業務委託契約が交わされ、それに準じて業務が行われます。
同じように社外へ業務を委託する形態としては派遣契約がありますが、勤務時間の制約がない点や委託側に指揮命令権がない点などが派遣契約との違いです。
なお、業務委託契約は請け負った仕事の成果によって報酬が支払われる「請負契約」と、契約期間中の業務に対して報酬が支払われる「委任契約」に分けられます。
業務委託は、多くの場合単なる発注者と受注者の関係にとどまるのに対し、業務提携はお互いに足りないものを補い合いながらシナジーを生み出すことになりますので、この点がまったく違います。
M&Aとは
M&Aとは、資本提携をさらに進め、一方が他方の株式を取得することにより親会社・子会社の関係となることを言います。買収側は被買収側を子会社としてグループ企業内に迎え入れることになるため、新規開拓や自社の欠点を補うなど様々なメリットが享受できます。
いっぽう被買収側も、グループ企業の一員になることで親会社のリソースを存分に使えるようになるだけでなく、株式売却によってオーナー経営者が創業者利益を確保することも可能です。
企業間が資本関係で結ばれている点は資本提携と同じであり、この点が業務提携とは異なりますが、一方が他方の支配権を有する点が資本提携とは違います。
近年では、中小企業を中心に後継者不在問題を解決するための手段として、このM&Aが積極的に用いられています。
業務提携の種類
業務提携と一言で言っても、その種類には様々なものがあります。その中でも企業同士でよく用いられている業務提携は、主に以下の4つです。それぞれについて見ていきましょう。
1.技術提携
技術提携とは、他社(あるいは自社)が有する技術を使って自社(あるいは他社)の研究開発や製品製造などを行う業務提携のことを言います。技術提携には「ライセンス契約」と「共同研究開発契約」の2つがあります。
特許や特殊な製造ノウハウなどを持った企業に対してその使用対価を支払い、特許やノウハウを自由に使用する許可を得るのが「ライセンス契約」です。一方、複数社が共同で製品などの研究開発を行うのを「共同契約」と言います。
技術提携で盛り込むべき契約条項
技術提携を行う場合「ライセンス契約」であればライセンス契約書を「共同研究開発契約」であれば共同研究開発契約書を作成します。これらの契約書を作成するにあたり、後のトラブルを避けるためには、最低限以下の条項を盛り込んでおかなければなりません。
| 盛り込むべき条項 | 内容 |
| 技術協力の範囲とその目的 | 特許はもちろんのことノウハウなどをライセンス契約する 場合は、その内容をできるだけ具体的に書いておきます |
| 業務と費用をお互いどのように分担するのか | 共同研究を行う場合、業務の内容や費用の負担を明確にしておきます |
| お互いの設備の利用条件について | お互いの設備を利用する場合の条件に関して事前に明確にしておきます |
| 技術提携で得られた新たな知的財産権について | 共同研究開発によって新たに得た特許やノウハウの管理を どのように行うのかを決めておきます |
| 技術提携で得られた情報の秘密保持について | 提供を受けた技術や新たに開発した技術に関し、 情報の秘密保持を決めておきます |
| 契約の有効期限 | ライセンス契約や共同研究開発の期間を定めておきます |
| 契約違反に対する処遇について | 契約違反が起きた場合の処遇について明確にしておきます |
2.生産提携
工場などの製造設備を有している他社に対し、自社製品の製造の一部を委託して製造能力を補完する業務提携が生産提携です。生産提携は、製品を製造するプロセスにおいて頻繁に用いられています。
電子産業などにみられる収益構造を表すモデルに「スマイルカーブ」があります。これは、製品開発のようなバリューチェーンの上流工程と製品販売や保守メンテナンスなどの下流工程の付加価値が高く、製品製造や組み立てなどの中間工程の付加価値が低いことを表しています。
たとえばApple社のiPhoneなどはこのスマイルカーブに従い、企画開発と販売のみを自社グループで行い、製品の製造や組み立ては中国や韓国などの企業と生産提携を結ぶことにより自社の利益を最大化しています。このような生産提携は、世界中の様々な場所で見られます。
なお、生産提携には「OEM(Original Equipment Manufacturing)」や「ODM(Original Design Manufacturing)」などがあります。
生産提携で盛り込むべき契約条項
生産提携を行うためには、生産提携契約書を締結しなければなりません。この契約書の作成にあたり、後のトラブルを避けるためには、最低限以下の条項を盛り込んでおかなければなりません。
| 盛り込むべき条項 | 内容 |
| 契約の目的 | 生産提携によって何をどのように行うのか、 もっとも基本的な内容について定めます |
| 製品の仕様変更が生じた場合について | 製造中に製品の仕様が変更した場合、 お互いにどう対処するのかをあらかじめ定めておきます |
| 再委託の禁止 | 生産委託された製品の製造を更に再委託して第三者に製造させないために、 禁止事項として定めておきます |
| 最低発注保証 | 生産提携に基づいて製品を製造するために、 受託側は原材料や生産ライン、人材などの確保をしなければなりません。 これらの投資を受託側が安心して行えるために、 最低限の発注量や発注期間などをあらかじめ定めておきます |
| 瑕疵担保責任 | 納品時にチェックしきれなかった製品の瑕疵などに関して、 事前にその対処法を定めておくことによりトラブルになるのを防ぎます |
| 製造物責任 | 製品が最終的なエンドユーザーに渡った後で起こった トラブルに関する責任の所在を事前に定めておきます |
| 改良技術の知的財産権について | 製品を製造する過程で新たに改良技術を開発した場合、 その知的財産の所有権がどうなるのかについて定めておきます |
| 有効期間 | 生産提携の契約期間を定めておきます |
| 秘密保持 | 生産提携によって知り得た情報を外部に漏らさないように 秘密保持契約を締結します |
3.販売提携
販売契約とは、販売ルートやチャンネルを持っている他社に製品の販売を委託する業務提携の一種です。なお、販売提携には以下の3つの種類があります。
販売店契約
販売店契約とは、販売店がメーカーから商品を仕入れ、顧客に販売する販売提携です。販売店と顧客との間で売買が行われるため、販売価格は販売店が決められます。
代理店契約
代理店契約とは、メーカーやサプライヤーが顧客と売買契約を結ぶ契約形態のことを言います。したがって、販売店契約とは違い、販売店が契約の当事者となることはありません。また、販売店契約のように製品の在庫を抱えることもありません。
フランチャイズ契約
フランチャイズ契約とは、フランチャイズ本部が商標の使用権や商品の販売権を提供する義務を負うのに対し、加盟店側はその対価を支払う義務を負う契約のことをいいます。フランチャイズ契約を締結すると、加盟店側は本部に対して保証金やロイヤリティを支払わなければなりません。フランチャイズ契約の例としては、コンビニなどが挙げられます。
販売提携で盛り込むべき契約条項
販売提携契約書の作成にあたり、後のトラブルを避けるためには、最低限以下の条項を盛り込んでおかなければなりません。
| 盛り込むべき条項 | 内容 |
| 販売権の範囲 | 販売代理店等に対して販売権を独占的に付与するのか、 それとも複数の代理店同士で競業させるのかなども含め、 販売権の範囲について定めておきます |
| 最低販売量 | 販売店に対するノルマを設定します。 ノルマを下回った場合のペナルティと、 上回った場合のインセンティブを定めておきます |
| 販促費の負担 | 販売促進のための値引きなども含め、 販促費のコストをどのように負担し合うのかを定めておきます |
| 販売提携の形式について | 販売提携には、上述のように販売店契約・代理店契約・ フランチャイズ契約の3つの契約形態があります。 これらの中からどの契約にするかを定めます |
4.その他の提携
業務提携には、これまで紹介した提携以外にも、たとえば以下のような提携があります。
- 調達提携……原材料などの仕入れを共同で行い、スケールメリットを生かして仕入価格を下げます
- 流通提携……製品の流通ルートを共有し、運送費などのコストを下げます
- 包括提携……おもに自治体などが企業と提携し、市民サービスの向上と地域の発展を目指します
業務提携を行うメリット

企業同士が行う業務提携には、様々なメリットがあります。その中でも特に大きなメリットが、以下の5つです。
技術力・生産力・販売力の強化や補充ができる
業務提携を行うと、自社単独で行うよりも確実にピンポイントで必要な分野の強化や補充ができます。
技術力が必要であれば技術提携を、生産力が必要であれば生産提携を、販売力が必要であれば販売提携をすることにより、自社にはない技術や生産力・販売力などがあっという間に手に入れられます。
効率化・リスク低減が見込める
業務提携をすると苦手な部分は他社からのサポートが受けられるため、社内の限られたリソースを得意分野に集中できます。したがって、経営効率を上げることが見込めます。
どの会社にも弱い部分はありますが、これを自社単独で解決しようとすると莫大な時間とコストが必要であり、かつ必ずしも成功するわけではありません。しかし業務提携であれば、既に成功している企業と提携できるため、失敗のリスクを大幅に低減することが見込めます。
新規事業に進出しやすくなる
新規事業に進出するためには、人材や資金・時間やノウハウなど様々なものが必要になります。事業規模が小さくなればなるほどこれらの資源を社内だけで集めるのは難しくなるため、成功確率がどんどん低くなってしまいます。
しかし、業務提携を選択すれば、このような成功を妨げるものに頭を悩ませることはありません。何故なら、自社にはない新規事業の進出に必要なものは、提携相手がすでに持っているからです。
したがって、提携先が持っている技術や生産能力、販売網やブランド力などを使って、失敗するリスクを極力抑えながら新規事業に進出できます。
多額の資金を必要としない
新製品の開発や生産設備を整えるための設備投資・販売網の整備には多額の資金と時間が必要です。しかし、これらを業務提携によって賄えることができれば、このような資金が必要になることはありません。 業務提携であれば、自社単独でこれらを行うほどの費用は要らないため、会社のキャッシュフローが悪化して経営を圧迫するような心配をしなくても済みます。
必要がなくなった場合、提携解消も選択できる
業務提携の契約には期限が設けられている場合がほとんどのため、提携によるメリットが薄れたと判断した場合は提携を解消できます。
設備投資のような大型投資の場合は、投資のメリットが薄れたからといって簡単に撤退することはできません。投資のための借入金の返済は毎月しなければなりませんし、定期的なメンテナンスも必要です。もちろん、設備を動かすために必要な人材も、一度雇用すると簡単にカットすることはできません。しかし、業務提携であれば、必要な時に必要なだけ使えるだけでなく、また必要が無くなれば解消もできるため無駄なコストが発生しません。
業務提携を行うデメリット

業務提携には多くのメリットがある反面、デメリットもあります。その中でも大きなデメリットが、以下の3つです。
自社の技術やノウハウの流出リスクがある
業務提携のデメリットの中で最も大きなものが、自社の技術やノウハウの流出です。業務提携を行う場合、秘密保持契約を必ず締結します。しかし、相手側が情報の管理に慣れていない場合、誤ってこちら側の大切な情報を社外へ流出させてしまいかねません。
また、相手側が開発したものが意図せずにこちら側の技術やノウハウを流用してしまうこともあります。このようなことは、相手側だけでなく自社側にも生じる可能性があります。
業務提携を行う場合は、このようなリスクを避けるために何重にも予防線を張った契約書を作成しますが、それでも技術やノウハウの流出リスクを完全にゼロにすることはできません。
法的問題への対応が遅くなる場合がある
業務提携は、技術やノウハウなどに関連する部門の判断が先行するケースが多く、提携の方法によってはあまり大きな資金が動くことはありません。したがって、弁護士などの外部の専門家が提携段階に応じたリーガルチェックを行うことはまれです。
その結果、法的なリスクが提携後に見つかるケースや、実際にリスクが生じてしまった後で専門家に相談する場合が生じてしまうため、どうしても法的問題への対応が遅くなりがちです。
関係が希薄化しやすい
業務提携のメリットは、資本の結びつきがないため提携解消がしやすい利点がありますが、これが逆にデメリットになる場合があります。
いつでも提携が解消しやすい関係は、お互いを簡単に希薄化してしまうともいえるため、担当部署の人間が人事異動で現場から離れてしまうことなどがきっかけとなり、提携がより希薄化して一気に解消に向かってしまうことも決して珍しくありません。
業務提携の流れ
それでは次に、実際に業務提携を行うまでの流れについて解説します。業務提携は、おおむね以下の流れに従って行われます。
① 目的・戦略立て
② 提携先の選定
③ 秘密保持契約(NDA)の締結
④ 基本条件の交渉・基本合意の締結
⑤ 提携事業・パートナー企業の調査
⑥ プロジェクト体制の構築
⑦ 最終条件交渉・提携契約の締結
⑧ 業務提携の開始
①目的・戦略立て
業務提携を検討するにあたり、はじめに自社の現状を分析し、業務提携をする目的とそれを達成するための戦略を立てます。
自社の弱みを社内のリソースのみで解決しようとすると、コストも時間もかかり、失敗のリスクも増えます。しかしその反面、成功すればリターンは大きく、場合によっては一気にIPOまで持って行くことも不可能ではありません。これを業務提携で解決しようとすると、コストや時間やリスクは低減しやすくなる半面、リターンは当然少なくなります。
これらをよく検討し、本当に業務提携が最善の策かどうかをスタート前に確認しておくことが大切です。またこの時、資本提携やM&Aのような他の手法についても検討しておいた方が良いでしょう。業務提携もM&Aも、自社にないものを他から取り入れるという点では同じです。場合によってはM&Aを選択するのがベストになることもあるでしょう。
いずれにしても、できるだけ幅広い選択肢の中から最適な施策を選ぶように、多角的な検討を行わなければなりません。
②提携先の選定
業務提携の目的と戦略が決まったら、次は提携先の選定です。このときには、提携によりシナジー効果がもっとも大きくなる企業をパートナーに迎えなければなりません。
提携先を選定する方法としては、自力で行う方法と第三者を介して紹介してもらう方法の2つがあります。インターネットの検索や交流会などに積極的に参加することにより自力で提携先を見つけられる場合もありますが、ネットの検索や交流会での話し合いなどで正しい情報を引き出すことはかなり難しいでしょう。
第三者を介して提携先を探す方法としては、大学の産学連携コーディネーターや中小企業基盤整備機構などへ相談する方法もありますが、資本提携やM&Aなども視野に入れるのであればM&Aの仲介会社に相談することもできます。
仲介会社であれば日本中の様々な事業者を顧客に抱えているため、業務提携先の相談をすることもできるでしょう。また、将来的にM&Aを視野に入れているのであれば、今のうちから懇意にしておくのも良いでしょう。
③秘密保持契約(NDA)の締結
業務提携先の候補をリストアップできたところで、秘密保持契約(NDA)を締結します。業務提携をするかどうかの話し合いを行う過程で、お互いの技術やノウハウなどの内部情報をオープンにしなければ話を進めることはできません。したがって、交渉を始める段階で、まず秘密保持契約を締結します。
なお、秘密保持契約書を作成するにあたっては、特に以下の条項を確認しておかなければなりません。
- 秘密情報の定義
- 秘密保持義務
- 目的外使用の禁止
- 秘密情報の返還
- 有効期限と存続状況
それぞれの内容を見ていきましょう。
秘密情報の定義
開示される技術やノウハウなどのうち、どこまでの情報が秘密情報にあたるのかを定めます。それと同時に、秘密情報に含まれないものも定義しておくことが必要です。
たとえば、開示されていた情報に関して、開示を受けた側がすでに知っていたものなどについては秘密情報に含めないなどの例外条項を記載します。
秘密保持義務
秘密情報を管理する義務とその方法を定めます。また、第三者以外で秘密情報を開示できる例外規定もここで定めます。
開示を受けた秘密情報を漏洩してはいけませんが、業務を遂行する上で、関連会社や委託先、税理士などのアドバイザーなどに対しては秘密情報を開示できる例外規定を設定しておくのが一般的です。
目的外使用の禁止
開示された秘密情報をどこまで使用できるのか、その範囲を設定しておきます。一般的には、秘密情報を開示する側はできるだけ利用範囲を狭くしたいと考え、情報を開示される側はできるだけ利用範囲を広くしたいと考えます。
したがって、この項目を設定して、当事者間で認識のずれが生じないようにします。
秘密情報の返還
契約が終了した場合や、情報の開示側から要請があった場合などに、開示した秘密情報を変換したり破棄したりする義務を負わせる条項を設定しておきます。
当該条項は契約終了後に秘密情報が漏洩することを防ぐためには、必ず記載しておかなければなりません。
有効期限と存続状況
秘密保持契約の期限をいつまで定めるのかを記載します。一般的に、開示側は「できるだけ長期間にしたい」と考え、開示を受ける側は「できるだけ短期間にしたい」と考えるため、本契約の契約期間と契約期間終了後の効力の存続について定めておきます。
④基本条件の交渉・基本合意の締結
業務提携の締結に向けて、締結後のお互いの役割分担や責任の分担、業務フローや利益・費用などの分配と負担などを定めていきます。提携後のトラブルを防ぐために、できるだけ公平性を保ちながら一つ一つお互いが納得できるように交渉します。
これらの話し合いがある程度まとまったところで、基本合意書を締結します。基本合意書で定める項目は業務提携の内容によって様々ですが、自社以外の第三者との提携を禁止して独占交渉権を付与する条項や、デューデリジェンス(投資対象となる企業や投資先の価値やリスクなどを事前に調査すること )への協力義務などが付記される場合もあります。
なお、こうした基本合意書の締結は、資本の移動をともなう資本提携やM&Aでは必ず行われますが、資本の移動や大規模な資金が必要でない業務提携では省かれることもあります。
⑤提携事業・パートナー企業の調査
業務提携が最終合意に至る前に、提携事業の調査とパートナー企業の調査がそれぞれ行われます。
提携事業の調査
提携事業の調査とは、提携によって新たに始める事業やサービス、プロジェクトなどが実現可能なものかどうか、また利益はどれくらい生じるのかを提携前に調査・検討することを言います。調査結果によっては、計画の内容を変更したり、計画そのものを取り消したり、また代替案を検討したりもします。
このように、企業が新規事業に進出する場合に行う調査をフィージビリティスタディと言います。フィージビリティスタディは、一般的に以下の3つのステップで行われます。
| ①課題の明確化 | 新規事業の市場規模や業務提携によって得られる技術によって、 市場でどれくらい優位な地位を占められるのか、 またコストとリターンとそれに必要な期間がどれくらいあるのかなどを調査していきます |
| ②必要事項のリストアップ | 課題を解決するために現段階で必要だと思われるものや、 不足していると思われるものを徹底的にリストアップしていきます |
| ③代替案の作成 | 現状分析や必要な課題、不足しているものなどを加味した上で、 当初の計画を修正していきます。業務提携であれば、 提携のやり方や契約内容などに修正を加え、より実現可能なものへ近づけていきます。 なお、この時点で業務提携すべきでないと思われた場合は、 提携そのものを中止することもあります。 |
パートナー企業の調査
パートナー企業を調査する時には、法務や財務などを中心に提携企業として契約の遂行や業務の継続に問題がないのかどうかを調べます。
たとえば、業務提携後に提携企業に何らかの問題が生じて業務そのものが座礁してしまうと、せっかくの業務提携がすべて水の泡です。コストや時間もそれなりにかけているため、当然損失も生じてしまいます。そうならないために、事前にパートナー企業の調査が行われます。
なお、業務提携におけるデューデリジェンスはM&Aのように包括的に行うものではなく、第三者との契約や取引などを中心に簡易的に行われるのが通例です。また、規模の小さな業務提携であれば、デューデリジェンスそのものが行われない場合もあります。
⑥プロジェクト体制の構築
提携業務やパートナー企業の調査と並行して、提携に向けたプロジェクト体制を社内で構築していきます。業務提携によって始まる新しいプロジェクトの担当者にふさわしい人物を社内からピックアップし、プロジェクトチームを立ち上げて提携後の業務がシームレスに行えるように準備を開始します。
また、提携先との人事交流や定例ミーティングなどの企画や準備なども同時に進めて行かなければなりません。
⑦最終条件交渉・提携契約の締結
弁護士などの社外専門家のアドバイスを受けながら、提携に向けた最終条件の交渉を行います。契約に盛り込むべき事項に漏れがないかどうかを確認し、作成した契約書に関しては必ず弁護士のリーガルチェックを受けるようにしなければなりません。
万が一契約書に法的な不備があると、将来的に不測の事態が起こりかねません。したがって、外部の専門家には必ず意見を求めるようにした方が良いでしょう。
提携相手との最終交渉が済んだら、業務提携の契約を締結します。ただし、ビジネス環境は刻一刻と変わるため、契約締結後も定期的に契約内容を見直すようにしましょう。
⑧業務提携の開始
業務提携契約書を締結したら、契約に基づいて業務を開始します。業務開始前に思い描いた内容と実際に業務を開始してから分かったことは違うことが多いため、業務の実情に合わせながら契約を適宜見直すようにしなければなりません。
また、必要に応じてさらに業務内容に応じて個別契約を締結する場合もあります。
業務提携を締結する前に確認したい注意点
業務提携は、契約さえ締結すればうまくいくというわけではありません。業務提携を締結する前に、確認すべき事項や注意すべき点を抑えておかなければ、せっかくの業務提携が思い通りの効果を生じないままに終わってしまうこともあります。
そのようなことが起こらないために、業務提携の締結前に確認すべき注意点は以下の5点です。
業務やコストの配分、権利の帰属を明確にする
業務提携が行われると、共同で行う業務やお互いに経費を支出し合うことがあります。こういった業務やコストの配分をどのようにするのかを事前に明確にしておくことが大切です。
お互いに目標を達成するためには、各々がどの分野でそれぞれの強みを活かせるのかを十分に検討した上で、それぞれの業務の範囲と内容を具体的に決定しなければなりません。同時にコスト配分についても、お互いに経費をどのように負担し合うのかを事前に明確にしておかなければなりません。
また、業務提携によって生じた利益をどのように配分していくのかも事前に規定しておく必要があります。特に、技術的な提携や共同開発などを行う場合には、提携によって開発された成果物に対する知的財産権(特許権など)がどちらの企業に帰属するのかを規定しておかなければ、提携業務をスタートできません。
利益の分配や成果物に対する知的財産権は、後々裁判などの紛争になることが多いため、契約締結時には十分に検討し、明確な基準を定めておくようにしましょう。
効率的に進めるための協力体制を構築する
業務提携を効率的に進めるためには、提携企業同士で協力体制を構築していくことが必須です。提携を円滑に進めるために業務スケジュールを共有して、できるだけ合同ミーティングなどで情報交換を行い、人事交流に対しても積極的に進めていくことが大切です。
交渉を進めるにあたり、このような協力体制の大切さを両社で共有し、協力体制や情報共有に関する規定を契約書に盛り込んであるかどうかもチェックしておきましょう。
情報管理を徹底する
業務提携に携わった担当者が将来的に異動する可能性もあるため、提携のシステムや情報管理を属人化しないように気を付けた方が良いでしょう。業務提携の契約内容は誰が見ても簡単に理解できるものにし、提携に関する書類などは担当者が管理するのではなく組織的に管理するなどの工夫を行うことが大切です。
契約書を明快なものにする
契約書は、誰が読んでも読み間違いが起きない明確なものにしておかなければなりません。取りようによってはどうにでも取れるようなニュアンスはできるだけ排除し、具体的な期間や金額、数字などをできるだけ盛り込んでおくように心がけましょう。
人員整理・契約解除・更新拒否など一方的に行えないものが存在する
業務提携契約は、一般に継続することを前提に作られたものが多いため、重大な契約義務違反やどうしても契約を継続できない特別な理由などがない限り、一方的に解除するのは難しい契約です。
特に以下のようなケースでは、契約を一方的に解除することは難しいと考えられます。
| 契約を一方的に解除することが難しいケース |
| 業務提携を結んだ両社の立場に事実上の上下関係があり、契約の解消を望む側が強い立場で解消を望まない側がそれに対して反対意見を述べるのが難しい場合 |
| 契約解消を告げられた側が提携業務に大きく依存した経営状態であり、かつ提携業務の遂行に際し多額の設備投資を行った場合 |
| 契約解消を希望する側が、かつて契約継続を明言していた(もしくは契約の継続を示唆する言動を行っていた)場合 |
また、将来のことを考えて契約解除をしやすくしておきたい場合は、契約書に以下の内容を付記しておくと効力を発揮することができます。
- どのようなケースであれば契約が解消できるのかをできるだけ具体的に記載しておく
- 契約が一方の意思により解消された場合は、解消された側に対して損失の補償を行う旨の内容を記載する
- 業務提携を自動更新とせず、契約期間そのものを短期間に設定し、契約終了ごとに両社の意思を確認することを契約継続の条件とする
在庫品の管理や処分を明確にする
業務提携が終了する前に、提携期間中に製造された在庫品をすべて売り切って在庫をゼロにしてしまうことは現実的にはまず不可能です。しかし、これらの在庫品の管理が曖昧では、業務提携後に自社製品が思わぬ形で市場に出回ってしまうリスクが生じます。
また製品を製造した側は、使用しなかった原材料や販売できなかった製品の在庫の処分費用などを負担しなければなりません。
そこで、最後に残った在庫品の管理や処分を巡ってトラブルが生じないように、契約書にそれらの取り扱いに関する事項を明確に記載しておきます。一般的には、以下の内容を契約書に規定しています。
- 業務提携が終了次第当該品の生産や販売を中止し、在庫を処分する義務を製造側が受け持つ一方で、業務を委託した側はこれらをすべて買い取るようにする
- すでに仕入れた原材料に関してのみ、製品を製造・販売する許可を与え、製造側の在庫がすべてなくなった時点で契約が終了するようにする
業務提携の成功事例5選
最後に、業務提携の成功事例を5つご紹介します。
事例1.日本郵政グループと楽天グループの業務提携
1つ目の成功事例は、日本郵政と楽天グループの業務提携です。この業務提携を正しく理解するために、両社がそれぞれ抱えていた課題と狙いを見ていきましょう。
日本郵政グループが抱えていた課題
日本郵政グループは、日本中のあらゆる場所に郵便局や物流ネットワークを持っていたものの、インターネットの普及によって郵便物数は平成13年度の約262億通をピークに減少し続け、平成30年度は約167億通にまで落ち込んでいました。
民営化とインターネットの発達による時代の変化、そしてかんぽ生命の事件によるイメージダウンも影響し、グループが持つ日本中を網羅した物流網を使いこなせずにいました。
| 日本郵政グループの狙い |
| ・楽天経済圏で提供されているサービスと自社のサービスを連結することによって生じるシナジー効果 ・IT化の促進によるサービスの向上とコストの削減 |
たとえばネットショッピングは、アメリカではEC化率(市場取引における電子商取引の規模が占める割合 )が15%程度ですが、日本はまだ10%に満たない程度であり、さらに伸びる余地があると考えられています。この部分の物流を押さえ、さらに楽天経済圏の顧客に対して自社グループ内の様々なサービスを提供することが日本郵政の狙いでした。
また日本郵政はIT化が遅れており、それがグループ全体のコストを上げていたことから、IT化の促進も期待されていました。
楽天グループが抱えていた課題
一方楽天グループも、グループ発足以降最大のピンチに見舞われていました。巧みなM&A戦略によってグループ企業を増やし、自社の経済圏を拡大し続けていた楽天グループは、満を持して楽天モバイルの正式サービスを2020年に開始します。
しかし、数千億を超える基地局の整備費用などが仇となり、グループ全体の連結決算は赤字に転落してしまいます。基地局の整備にはまだまだ費用がかかる上に、知名度の低さから顧客の囲い込みも思い通りに進まない事から、「進むも地獄。戻るも地獄」の泥沼状態に陥っていました。
| 楽天グループの狙い |
| ・今後さらなる拡大が見込まれるEコマースのための物流網の整備 ・楽天モバイルの基地局整備のための資金調達と整備費用のコストダウン ・楽天モバイルのサービスカウンターの増設 |
どれだけIT化を進めても、最後は顧客に商品を届けなければなりません。楽天は物流の一部を自社内で進めていくことを実験的に行っていましたが、すべてを自社で行う形態に切り替えていくよりも、他社と業務提携を行った方がコストもシナジーも大きいと予測していました。
また、楽天モバイルの基地局整備のための資金調達と整備費用のコストダウン、サービスカウンターの増設も楽天グループにとっての悲願でした。
業務提携によって達成されたもの
日本郵政と楽天グループは、共同出資により「JP楽天ロジスティクス株式会社」を設立しました。
この新会社には、楽天グループがこれまでに投資・開発してきた自動化した物流センターを組み込み、日本郵便の配送ネットワークが使われています。最新の物流センターと日本郵便の配送システムを結合することで物流のDX化を実現し、商品の発注から納品までの時間の短縮や物流システムの効率化、受注できるキャパシティの最適化を目指すとされています。
JP楽天ロジスティクス株式会社の当面の目標は、楽天市場をはじめとする楽天グループが提供するECサービスの配送をより効率化させることでした。将来的には楽天市場以外のEC事業者とも提携を行い、幅広い業務を展開していくことを中長期的な目標としています。また、ドローンや自動走行ロボットを用いた次世代型の配送サービスについても共同で開発していくことを発表しています。
日本郵政にとってはこの提携によって、収益の向上とITをフル活用した新たなプラットフォームの構築、そして将来に向けた開発に着手できるようになりました。
一方、楽天グループにとっても、この提携で得られるものは決して少なくありません。
まず、1,500億円の第三者割当増資を日本郵政が引き受けたことにより、楽天モバイルの基地局整備費用調達に成功しました。
加えて、全国に2万5千局ある郵便局内のイベントスペースに、楽天モバイルの申し込みカウンターを設置することにより、これまで獲得できなかった新規顧客の獲得を目指します。同時に、郵便局の建物に楽天モバイルの基地局を設置する計画が進んでおり、新規の基地局増設のピッチが早くなっています。
このように、日本郵政と楽天グループの業務提携は、お互いに不足している部分を補い合う結果となりました。
事例2.ファミリーマートとTOUCH TO GOの業務提携
2つ目の成功事例は、ファミリーマートとTOUCH TO GOの業務提携です。それぞれの課題から順に解説していきます。
ファミリーマートが抱えていた課題
これまで右肩上がりで拡大を続けてきたコンビニエンスストア業界は、国内市場が飽和して、ついに減少に転じはじめました。2019年末に全国のコンビニ店舗数が初めて前年比で121店舗減と減少に転じ、急激な人口減少によって国内市場がシュリンクしていく中でシェアの拡大や利益率の増加を望むことはかなり難しい局面へ突入しつつありました。
中でも業界第2位のファミリーマートが抱えている問題は深刻で、ヒット商品が出なかったことによる客数の落ち込みが影響して加盟店の経営状況が急悪化し、他のコンビニチェーンに大きく後れを取る結果となっていました。
売上の減少のほか、加盟店の経営状況を悪化させていたのが、人件費の高騰です。最低賃金の引き上げにより人件費は上昇し、それでなくてもなかなか人が集まらないコンビニスタッフの穴埋めとして人材派遣に頼ることもあるほどでした。
このままの状態が続くと契約を更新せずに経営から退くコンビニオーナーが増えるため、市場のシェアは減り、さらに苦戦することになるのは明らかな状態となっていました。
| ファミリーマートの狙い |
| ・人材確保のための手間やコストの省略 ・人件費の大幅カット |
人件費さえ不要になれば、コンビニは大型の自動販売機のようなものです。商品の補充や棚卸程度の手間を除けば、人件費はほとんど必要ありません。システムの導入と維持のための費用は新たに必要になりますが、加盟店の利益率が上がり、スタッフなどの人材確保に頭を悩ます必要がなくなるため、店舗数の増加も期待できます。
TOUCH TO GOが抱えていた課題
株式会社 TOUCH TO GOは、JR東日本グループのJR東日本スタートアップ株式会社とサインポスト株式会社の合弁で設立されたジョイントベンチャーです。
駅構内の売店の無人決裁店舗システムの開発を目指し、「TTG-SENSE」というバーコードでのスキャンすら不要の次世代決済システムの開発に成功していました。JR高輪ゲートウェイ駅でのモデル店舗の開業にも成功し、このシステムの販売先を模索しているところでした。
| TOUCH TO GOの狙い |
| ・全国のファミリーマート加盟店に向けた無人決裁店舗システムの導入 |
全国で約1万6千店舗あるファミリーマートの加盟店に自社開発した無人決裁店舗システムを卸すことができれば、保守メンテナンス料だけでも莫大な収益が期待できます。
業務提携によって達成されたもの
2021年2月の資本業務提携締結後、無人決済店舗1号店が21年3月東京の大手町にオープンしました。2024年度末までに1,000店舗を目標に無人決済店舗の出店を加速させています。
TOUCH TO GOの無人決済システムを導入したファミリーマートの店舗では、短時間で買物を済ませられる利便性の高さが他のコンビニとの差別化を生み、省人化による店舗オペレーションコストの低減が可能になりました。
一方、TOUCH TO GOは、駅やオフィス・病院内の売店や地方の小規模な店舗などへの導入をまずは先行させる形でスタートを切りました。2023年までに100店舗の導入と株式市場への上場を目標に掲げています。
事例3.トヨタとNTTの業務提携
3つ目の成功事例は、トヨタ自動車とNTTの業務提携です。こちらもまず、当時トヨタ自動車が抱えていた課題から順に解説していきます。
トヨタ自動車が抱えていた課題
自動車産業は「100年に一度の大変革期」を迎えており、トヨタ自動車は環境問題から電気自動車に舵を切った欧米の自動車メーカーに大きく水をあけられつつある状況にありました。
トヨタが総力を挙げて開発していたハイブリッド車と水素自動車は主流から外れることが確定的となった結果、新たな対抗手段を講じなければなりません。そこでトヨタが目指したのが、スマートシティ構想です。通信インフラと提携して単なる自動車会社から脱却し、モビリティカンパニーへ変革していくことこそが、次世代のトヨタのあるべき姿であると考えていました。
| トヨタ自動車の狙い |
| ・通信インフラの整備された「コネクティッド・シティ」の創設 ・モビリティカンパニーへの変革(自動車メーカーからの脱却) |
トヨタ自動車の狙いは明確でした。それは、自動車のみを手掛ける会社からの脱却です。自動車がかつてのような高嶺の花でなくなり、誰もが簡単に手に入れられる存在となった今、電気自動車の登場によりコモディティ化(初期段階では高い価値の製品であったものが、市場の活性化や他社参入により一般化すること)が 更に加速していくのは火を見るよりも明らかでした。
そこで、通信インフラの整備された「コネクティッド・シティ」を創設し、その世界で活躍する自動車やサービスを提供する会社に生まれ変わろうと考えたのです。このスマートシティ化に必要だったのが、高度化された通信インフラだったのです。
NTTが抱えていた課題
日本国内では圧倒的な通信インフラを擁しているNTTは、事実上一人勝ち状態ではありましたが、クラウドサービスやlot、ビッグデータやAIなどの急速な進展により、様々なデジタルサービスの利用が進む中で次の一手を打ちあぐねていました。
高度の情報化された社会が訪れた未来に、どのようなサービスを提供するのか、定まっていなかったのです。
| NTTの狙い |
| ・高度化された情報化社会においても優先的な地位を占めること ・その社会で価値のあるサービスを提供し続けること |
上記を狙いとし、自社の持つリソースを最大化できるパートナーとしてNTTが選んだのが、トヨタ自動車だったのです。
業務提携によって達成されたもの
両社は株式を持ち合い、業務資本提携を締結したことにより、GAFAにも対抗しうる国内最大級企業のタッグが結成されました。将来を見据え、グローバル巨大企業群に対抗しうるだけのリソースを持った業務提携が誕生したわけです。
今後は、トヨタ自動車が手がける静岡県裾野市のスマートシティ「ウーブン・シティ」などでプラットフォームの基盤づくりの実験と実証を進めて行くことが決定しています。スマートシティでは、自動運転機能を持った無人車が街中を走り、人型ロボットやドローンなどが活躍し、一般家庭では各種センサーを使った住民の健康チェックなどが行われ、病気などの予防にまでつなげていく計画となっています。
自動運転技術の発達やインターネットとの接続などによりクルマそのものの概念が変わり、あらゆるものが情報でつながる社会を迎えるにあたり、クルマを単体で考えるのではなく、スマートシティの発想により新しいサービスを生み出す第一歩を歩み始めたのです。
事例 4.KDDIとカカクコムの業務提携
4つ目の成功事例は、KDDIとカカクコムの業務提携です。こちらもまず、当時KDDIが抱えていた課題から順に解説していきます。
KDDIが抱えていた課題
業務提携の公表寸前に発表された決算短信によると、売上高・営業利益ともに増収増益で堅調に推移しているものの、その内訳を見てみると決して安泰ではありませんでした。かつて主軸であったパーソナル部門(モバイル収入部門)は対前年同期比で112億円もの赤字となっており、それを付加価値収入やグローバル収入で補っていたからです。KDDIとしては、今後会社を牽引していく部門としてこのパーソナル部門の強化を課題として考えていました。
| KDDIの狙い |
| ・KDDIとカカクコムが提供しているサービスやメディアの連携 ・両社の提携により新しいサービスメディアなどの創出 |
カカクコムの提供する「価格.com」「食べログ」と、KDDIが提供している「auスマートパス」「au WALLET」などの各種決済各種サービスと連携することで利便性を高めるとともに、au会員のライフスタイルに合わせた最適な商品やサービスを提供しようと考えたのです。
そしてもう一つが新しいサービスメディアなどの創出です。お互い将来に向けた事業部門を持っていない両社が提携することにより、新たに収益の柱となる部門を作ろうとすることが狙いでした。
カカクコムが抱えていた課題
業務提携の公開前に発表された決算短信では、前年同期と比べると安定して増収増益を達成してはいるものの、将来を見据えた時、新たな収益の柱となるようなものを作られていない状況でした。
| カカクコムの狙い |
| ・KDDIが持っている通信網を使ったインターネット広告やデジタルマーケティング事業等の推進、事業の拡大と新事業の創設 |
業務提携によって達成されたもの
KDDIがカカクコムと資本業務提携をしたことにより、KDDIはカカクコムの株式を電通から取得し、第2位株主となりました。この提携により、カカクコム側が得たのが新たなユーザーの獲得です。
auが持つ約2,500万人のauの顧客に対して自社サービスの提供を新たに開始することにより、カカクコムはユーザー数を爆発的に増やすことに成功しました。
一方KDDI側は、au会員に対して新たなサービスを提供するとともに、「ぐるなび」と資本提携した楽天に対抗できる基盤作りに成功しました。
事例5.ヤマダホールディングスとアークランドサカモトの業務提携
最後の事例は、ヤマダホールディングスとアークランドサカモトの業務提携です。こちらもそれぞれ抱えていた課題から順に見ていきましょう。
ヤマダホールディングスが抱えていた課題
もともとは家庭用電化製品の大型販売チェーンだったヤマダは、「暮らしまるごと」をコンセプトに、家電を足掛かりに家具やインテリア等をはじめとする生活にかかるあらゆる商品の取扱いを開始しました。その拡大を続ける中で正面競合となったのが、家庭用家具などの販売を行っていた「ニトリ」ですニトリは家具だけでなく家電にも進出し、さらにはホームセンターを展開する島忠までも買収してグループの傘下に入れました。ホームセンター業界への進出を考えていたヤマダとしては、ニトリに先を越された形になってしまったわけです。
| ヤマダホールディングスの狙い |
| ・先を越されたニトリに対するキャッチアップ ・SDGs対応型のスマートハウスなど次世代の需要の開拓 |
ニトリと真正面から競合しているため、ヤマダとしてはホームセンター業界へ進出するための足掛かりがどうしても必要でした。
そのほかホームセンターのアークランドサカモトと組むことで集客面での成功だけでなく、SDGs対応型のスマートハウスなど次世代の需要を開拓することも十分に狙えると考えたようです。
アークランドサカモトが抱えていた課題
従来型のホームセンターからの脱却を目指して新たな事業を始めるために、提携先を模索しているところでした。
| アークランドサカモトの狙い |
| ・新たな客層の開拓 ・SDGs対応型のスマートハウスなど次世代の需要の開拓 |
アークランドサカモトの狙いは、商品ラインナップを増やして新たな客層を開拓していくことと、上述のスマートハウスのような次世代型需要の喚起でした。
業務提携によって達成されたもの
今回の業務提携により、2022年2月25日、愛知県一宮市に両社の共同開発店舗第一号店として、総合生活提案型ショッピングスクエアスーパービバホーム内に「Tecc LIFE SELECT New一宮店」がオープンしました。
今回の出店を含めて今後3年間で6店舗の出店が予定されていることも発表されています。
終わりに
業務提携は、資本を移動させることなく他社のリソースを使って売上や利益を増やせられるため、多くの企業間で行われています。しかし実際には、今回ご紹介した成功事例から分かるように、多くの場合資本のやり取りをともなう資本提携が選択されています。
業務提携のメリットの一つは比較的簡単に提携を辞められる点がありますが、これがネックとなり、空中分解を起こすケースは珍しくありません。したがって、業務提携について考えるならば、資本の提携をともなうM&Aまでを視野に入れ、次の一手を考えるべきでしょう。






















