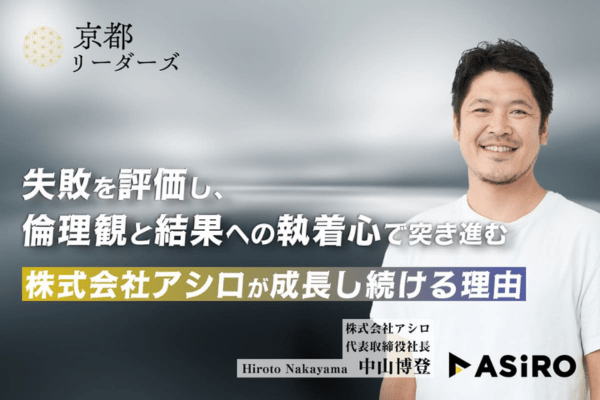
2009年11月の設立以来、リーガルメディアの運営を基盤としつつ徐々に事業を拡大し、2021年7月には東証マザーズ(現 東証グロース)への上場を果たした株式会社アシロ。代表取締役社長を務める中山博登は、どのような狙いを持ちながら事業を拡大させてきたのか。社員には何を求め、今後、どのような領域に向かおうとしているのか。生まれ故郷である福知山市や京都に対して何を思うのか――。気鋭の経営者に語ってもらった。
■アシロの多角的な事業展開と成長戦略
――株式会社アシロの事業内容を教えてください。
中山氏(以下、敬称略) メディア事業、HR(ヒューマンリソース)事業、保険事業が大きな3つの柱です。メディア事業が祖業で、メインは弁護士の比較サイト『ベンナビ』(『ベンナビ離婚』『ベンナビ相続』『ベンナビ交通事故』などのリーガルメディア)です。クライアントである法律事務所から広告掲載料をいただいて法律相談をしたいユーザーを集め、弁護士とユーザーの橋渡しを行います。成功報酬ではなく、毎月一定の金額をいただく広告掲載スタイルが特徴です。

その他にも、リーガルメディアを基軸とした派生メディアを展開しています。わかりやすいサービスは『キャリズム』です。例えば『ベンナビ労働問題』のユーザーが次にどういう行動するだろうと予測し、転職するのではないか、という発想から、転職のメディアをリリースしました。こちらに関しては、成功報酬を受け取るアフィリエイト収益モデルになります。
HR事業は『ベンナビ』のクライアントである法律事務所や法務人材を求める事業会社を対象として、『NO-LIMIT』という転職サービスで弁護士の転職支援をから始まりました。現在は弁護士だけではなく、税理士や会計士、バックオフィス人材の転職支援にも幅を広げています。
保険事業は、元々はユーザーが今後、弁護士を使うかもしれないリスクに備えて加入していただく保険を一般向けに用意していたんですが、今は新規販売を停止していまして、新たな保険商品を開発中です。
――各事業について、競合と比べての強みを教えてください。
中山 事業を継続するうえで、「何が最終的に競争優位性の源泉になるか」を見極め、そこに集中的に投資することが競争優位性につながると思います。 メディア事業でいうと、作って売って収益を上げるところまでは社外の関係者を入れてもいいんですけど、そこから収益性を安定させて拡大させていくために肝になるのは、代理店に任せず、自分たちで広告主を見つけているかどうかです。クライアントありきのメディアなので、直販をしないとクライアントの声を聞くことはできませんし、代理人が入ると収益の3割程度の手数料を支払う必要があります。
最初のうちはユーザーが右肩上がりに増えて収益面にも余裕が生まれるのですが、やがて停滞してきたときにはその手数料が重荷になりますし、代理人を入れていなければ、その手数料分を広告宣伝費にして原価に充てることができます。顧客が期待するものを安定的に供給するための仕組みを作っていることが、大きな競争優位です。
――貴社が現在の規模に成長するまでにあったターニングポイントを教えてください。

中山 紆余曲折ありますけど、やはり2021年7月の東証マザーズ上場が大きなターニングポイントとなっています。
「企業は社会の公器」という松下幸之助の言葉があります。それまでは私の器だった会社が、上場することによって公の器に近づき、社会に対してどのような影響力を与えられるのか、より大きな事業としてスケールインパクトを作っていくかという考え方に変わりました。
■なぜアシロは「失敗したい人」を求めるのか? 激変期を乗り越える企業カルチャーと「執着心」
――企業の在り方として重要視していることを教えてください。
中山 プロダクト作りを大切にしています。同じ事業を100年間やり続けることはできません。一つの事業を作ったらすぐに次の事業、またその次の事業と、新しいものを次々に生み出せる遺伝子やカルチャーが社内にあるかどうかが、企業としてかなり重要なポイントだと思います。
新しい事業は経営者以外の人間が作るのは難しいんですが、社員に新しいことにチャレンジするようにしつこく言い続けると、既存事業のマイナーチェンジをしたり、私の知らないプロダクトを生み出したりといったことが自然発生的に出てくるんですよね。それが成功するかどうかはともかく、そういう試行錯誤が非常に重要だと思っています。
――経営者としての意思決定において「これだけは譲れない」という価値観はありますか。
中山 市場のルールの中で正々堂々とやることを意識しています。私自身、裏をかいたり、誰かを排除したりといったことができるタイプではありません。社員に対しても他のお客さまに対してもユーザーに対しても、正々堂々やるようにしています。
――企業の急成長期には組織崩壊やカルチャー変質のおそれもあると思いますが、それらを防ぐためにどのような工夫をされているのでしょうか。
中山 そういった変化自体を、あまりリスクだと評価していません。むしろ、そういった変化に柔軟でありたいと思っています。そう考えていれば、結果として変化や進化しようとする社員を妨げてしまうような事象もなくなります。余計なことをせず、ちゃんと給料を払って働き方を教えて、社員同士が仲良くしながら普通に生活できていれば、辞めることもないし、組織も崩壊しないと思います。
そのためにも、人事評価だけはこだわって作っています。評価されるべき人間が正しく評価される仕組みだけは作っておかなければならないと思っています。
――人事評価のこだわりポイントについて、お話しできる範囲で教えていただけますでしょうか。
中山 定量評価と定性評価のバランスを取ることと、結果だけにフォーカスしないことを意識して評価に入れ込むようにしています。定性的に評価できることは、最終的に定量的な成果につながるので、「これをやり続けている人間は最終的に成果が出るよね」というポイントを逃さないようにしています。 ただ、人事評価は企業における“サグラダ・ファミリア”のようなもので、完璧なものは完成しないものですので、適切な評価をし切れていない部分もあることを前提として、なるべく多くの社員が納得できる評価制度に近づけ続けるつもりです。
――では、採用や人材の育成において大切にしているポイントはありますでしょうか。
中山 私が採用に関わらないことがすごく重要なポイントです(笑)。私は信じ込みやすいタイプで、誰の言うことも信じて採用してしまうので、人事担当からは「もっと厳しく選考したいので私たちに任せてください」と言われています。
――貴社のリクルートサイトには「求む、失敗したい人」と書かれています。
中山 当社の定性評価は、失敗した人間を評価するようになっています。難しいことだとは思いますが、恐れずにチャレンジできて、失敗してみたい人を求めているのです。

たとえばある社員が1,000万円ぐらいの損失を出した場合、めちゃくちゃ青ざめた顔で帰ってくるんですけど、そこに1,000万円以上の学びは絶対にありますし、それだけの投資対効果が期待できるんですよ。何をすればうまくいくかというメソッドと同じくらい、何をしたら失敗するリスクがあるかは重要ですし、私としては早く失敗してほしいんですよ。子どもだって転びながら成長するのが普通のことですよね。ビジネスにおいても当てはまることで、失敗しない大人は成長しないと確信しています。
――経営者として目標を達成するために最も大事な能力とは何だと考えていますか。

中山 気合と根性です。言うなれば執着心ですね。最初のうちはうまくいかないこともあると思いますが、「絶対に成果を出すんだ」という執着心を持ち続けて行動していれば、最後は納得できる結果につながります。途中で折れてしまったらそこまでですし、執着心が一番重要だと思います。
――気合や執着心が大事だと思うようになったきっかけは何でしょうか。
中山 世の中を見渡してみると、それらを備えた人間は、満足せずに高みを目指し続ける人間が活躍する傾向にあるんですね。8合目まで登って「もういいや」と思う人と、10合目まで登り切った後に下山し、さらに高い山を目指す人とでは、成果が大きく変わります。
人間の能力に大差はないと思っていますので、結果を左右するのはどういう成果を出したいかという志と、決めたことに対して成果が出るまで取り組み続ける気合と執着心なのではないでしょうか。
――では、経営者として最も大切にしている言葉は何でしょうか。
中山 倫理観です。もっと平易に表現すると「人に迷惑かけない」ですね。執着するがゆえに誰かに迷惑をかけてもいいわけではありませんので、「人に迷惑をかけずに執着する」という優先順位です。
私自身、幼少期には周りの大人にめちゃくちゃ迷惑をかけて育ったので、大人になってからは迷惑をかけないように心掛けていますし、経営者は上から目線で人生を語るなど、世の中に迷惑をかけがちだと思うんですよ。私自身もそういった人種にグルーピングされているはずなので、なるべく迷惑をかけないように何よりも倫理的であることを心がけています。
■故郷である京都、福知山への想い「笑顔を返してもらうために頑張る」
――中山社長は京都府福知山市のご出身ですが、地元の良いところ、好きなところを教えてください。
中山 福知山の周辺は海の物、山の物、地の物、すべての食べ物がめちゃくちゃ美味しいんですよ。これは日本で一番だと思っています。黒毛和牛の産地でもありますし、舞鶴のほうから松葉ガニも入ってきます。福知山では松茸や京野菜もつくっています。
私自身、食べることが好きなので全国各地に食事をしに行くんですけど、京都府北部は美味しいものが多いエリアだという気がします。
――「京都のリーダー」と聞いて思い浮かべる人を教えてください。
中山 京セラや第二電電(現 KDDI)の創業者である稲盛和夫さんですね。「動機善なりや、私心なかりしか」という言葉は私の心にも刻まれていまして、事業をするときには、その動機は善か、私心がないかと言い聞かせながら取り組むようにしています。
稲盛さんや、同じく京都出身である堀場雅夫さんの著書は読んで参考にしていますし、先人に素晴らしい商売人が大勢いらっしゃることは、我々にとって非常に大きなメリットだと思います。
――中山社長が京都に還元したいこと、京都を変えていきたいことはございますか。
中山 福知山には昭和初期から続く大規模な花火大会があったのですが、2013年に事故が発生して以来、中止となっていました。それが2024年、十数年ぶりに復活したのですが、地元でなかなか協賛が集まらなかったので、アシロ社がメインスポンサーを務めさせていただきました。
京都や福知山に限らず、日本のお祭りや花火大会はコンテンツとして興味深いなと思っていて。現状では地元の企業からしか協賛を集められず、存続が難しくなっているお祭りや花火大会がけっこう多いんですよ。そうしたお祭りを「コンテンツ」として捉え直し、地元だけではない大きな企業にスポンサーとして協賛してもらったり、チケット販売といったプレミア化による性が図れたりします。日本の文化継承のためにも、お祭りや花火大会のカルチャーはなくさないほうがいいと思いますので、我々の事業を通じた還元方法を模索しています。
また、福知山のような人口減少が進む地域では、学校単位での部活動の運営が難しくなっており、休日の部活動を民間団体が行う地域移行の動きが進んでいます。そういった取り組みにも連携できれば非常に有意義だと考えています。これは会社としては難しいかもしれないですが、個人でのふるさと納税や寄付などを通じて、必要な用具などの支援ができればと考えています。
養護施設などへの支援についても、継続的にやれる範囲でやっていきたいと考えています。社会的なインパクトを考えるとインパクトファンド(社会や環境を良くすることを目的とした投資ファンド)をやったほうがいいと思うのですが、見える範囲の中で手助けをして笑顔を返してもらうほうが頑張ろうと思えるタイプなので、学校の支援などでできることがあればぜひ協力したいですし、それが世の中に迷惑をかけ続けている私の、せめてものつぐないだと思っています。
――10年後のアシロ社がどのようになっていたいかを教えてください。
中山 今より大きくなっていることだけは決めていますが、それ以外の細かいことはあえて決めていません。誰にも分からない、想像もできないことですから。まずは100億円程度の営業利益を出すところまで進めていきたいと思っていますし、経営会議ではすでにロードマップを引いており、外部の方々の想像をはるかに超えるスピード感でそこに到達することをイメージしています。
――その中で中山社長ご自身は何をなすべきだと思っていますか。
中山 会社を大きくすることに集中し、フルスロットルで走り続けたいと考えています。日和ったり、集中できなくなったりしたら経営者を辞めたほうがいいと思っているので、人に迷惑をかけないように意識しつつ、全力でアクセルを踏み続けていくつもりです。そして頂上に到達したら次に登るべき山を探し、いったん下山して、さらに大きな山に向かっていくことをやり続けるつもりです。
【関連リンク】
株式会社アシロ https://asiro.co.jp/




















