
目次
- 野村病院の歩み—成長と変革の軌跡
- 病院存続の危機—野村理事長が直面した現実
- 「選ばれる病院」への道—野村病院の3段階の改革
- 怒りを捨てたリーダーシップ—職員との信頼関係の構築
- 職員の意識改革—危機をチャンスに変えた情報共有の力
- 「自分が患者なら?」—野村病院が追求する理想の医療を実践する決意と投資 全ての患者に少しでも健康になってほしい
- 「働き続けたい病院」とは—野村病院の職場改革
- 日本最大のアワード「ダイバーシティ(多様性)&インクルージョン(包摂性) D&I AWARD 2023」で全国の病院で唯一認定
- 「伝える力」が病院を成長させる—情報発信がもたらす好循環
- ICTの力で病院を進化させる—業務効率化と成長の実現
- デジタル化で築く持続可能な病院運営
- 「人を尊重する」哲学が生んだ病院経営の成功
富山県富山市にある医療法人社団尽誠会野村病院は、慢性期治療病院として地域や医療従事者から選ばれ続けている病院である。その礎には、病院の理念が確立され、実践されていることがある。理念が形骸化する組織も多い中、野村病院は経営理念を具体的な行動に落とし込み、地域、医療従事者に選ばれる病院として進化し続けている。(TOP写真:2005年に野村祐介理事長の祖父が心血を注いで新築移転した野村病院。2006年度の富山県建築賞を受賞している)
野村病院の理念
【ミッション(果たすべき使命・役割)】
私たちは、富山県内の医療・介護ニーズに応え、慢性期以降の患者・利用者の人生を支えます
【ビジョン(目指す姿)】
私たちは、富山県内の患者・利用者、医療従事者から信頼され、選ばれる慢性期病院になります。
【バリュー(行動指針・価値観)】
私たちは、医療従事者同士のチームワークを大切にして、患者・利用者の立場に立った医療・介護サービスを提供します。
野村病院の歩み—成長と変革の軌跡
野村病院は、1967年に野村祐介理事長の祖父が開院。その後、新病院の開院や増床を重ね、グループ全体で743床を擁するまでに成長した。そして2005年、現在の地に富山県初の全室個室病院(300床)として移転、祖父の「地域の方々へのお役立ち・還元をする」という思いが形になった。しかし、2004年に父、2011年に祖父が相次いで他界。2012年、野村祐介氏が理事長に就任すると、経営の軸を「量的拡大」から「質的充実」へと転換。病床の一部を介護医療院に転換し、病院・施設の整理、介護施設の開設などを進めた。
病院存続の危機—野村理事長が直面した現実

野村祐介理事長が就任した当初、病院の状況は深刻だった。これまで見てきたどの病院とも違い、「何もしなければ潰れてしまう」と感じた。病床稼働率は80%に届かないこともあった。それにもかかわらず、認知症や複雑な病態の患者を受け入れず、対応の負担が増すことを理由に断っていた。病院は「患者のために存在している」という本来の目的が忘れられ、病院の都合が優先される状態だった。まずは、四病棟のうち一病棟だけでも、できれば四病棟とも病院として存続させなければならないと考えたが、状況は厳しかった。看護師不足により病棟の一部を閉鎖せざるを得なかった。
「選ばれる病院」への道—野村病院の3段階の改革

野村理事長は、このままでは病院の存続が危ぶまれると強く感じ、改革を決意した。しかし、新たに就任した自分がいきなり改革を押し進めても、反発を招くだけだと考え、まずは病院の環境を整えることから始め、三つのステップで改革を進めることにした。
第1ステップ(2012年~):「平均的な病院」を目指す
•施設や備品の整備を進め、病院の基盤を強化
•スタッフの意識改革を行い、患者第一の姿勢を確立
•患者を受け入れる体制を整備し、適切な医療を提供
第2ステップ(2016年~):「慢性期医療で生き残る病院」へ
•診療報酬の維持に必要な医療区分を確保
•看護師の増員を進め、より充実した医療体制を構築
第3ステップ(2021年~):「地域と医療従事者に選ばれる病院」へ
•広報活動で慢性期医療を変えることを発信し、病院の認知度を向上
•メディアへの積極的な出演、サイト運営で情報発信を強化
•SNSや講演・取材を活用し、病院の魅力を広く伝える
野村理事長が改革で最も重視したのは、現場の声に耳を傾け、しっかり対応することだった。そして、日々の経営の中で以下のことを徹底して行った。
•自分が受けたいと思えるような医療を提供する
•固定観念や思い込みを排して前向きに考える
•「怒りは何も改善しない」ことを肝に銘じて行動する
•職員に現状と改革の必要性をわかりやすく伝え続ける
改革の手始めとして、新しく入職した看護師に病院の問題点を直接聞いたり、全職員を対象に病院の問題点を尋ねるアンケートを実施し、現場の意見を丁寧に拾い上げた。職員からの意見はすべて受け止め、業務改善委員会を立ち上げて議論。実行できるものはすぐに実行し、難しいものは「どうすればできるか」を考え続けた。
怒りを捨てたリーダーシップ—職員との信頼関係の構築
野村理事長が、特に重視したのは、心理的安全性(職員が安心して意見を言える環境)の確保と、「〇〇だからできない」ではなく、「どうすればできるか」を考える姿勢だった。その結果、理事長に職員が安心して意見を伝えられるようになり、建設的なアイデアがどんどん出るように。病院全体の改革がスムーズに進む環境が整っていった。
職員との信頼関係を築くきっかけとなったのは、野村理事長が就任当初、病院の状況があまりにもひどいので怒ってしまった時のことだ。職員から「怒るとこれから意見が出なくなるので、もう怒らないでください」と言われた。理事長はこの出来事から学び、それ以後は絶対怒らないと決めた。野村理事長の職員を尊重する姿勢とそれに応える職員との関係性の良さが感じられるエピソードだ。
職員の意識改革—危機をチャンスに変えた情報共有の力
2016年の診療報酬改定により医療区分の確保が難しくなり、病院経営が危機に陥る可能性があった。その際、野村理事長は毎月1回、約100人の職員を対象に月例集会を実施。以下のことをパワーポイントを使ったプレゼンテーションでわかりやすく伝え続けた。
•医療を取り巻く厳しい環境と野村病院の現状
•経営が成り立たなくなるリスク
•理事長の考える方向性
•今後の具体的な取り組み
通常、経営不安が広がると職員の退職が懸念されるが、野村病院ではほとんど退職者は出なかった。それどころか、職員の意識と行動に変化が生まれた。毎月、病院のビジョンや具体的な改善策を示し、その時々の経営データを共有しながら継続的に情報を伝え続けた。経営データが改善していくことで行動すれば成果が出ることがわかり、職員は将来への希望が持て、モチベーションが向上していった。
「自分が患者なら?」—野村病院が追求する理想の医療を実践する決意と投資 全ての患者に少しでも健康になってほしい

野村病院が目指したのは、「自分が患者だったら、どんな医療を受けたいか?」を基準にした病院づくり。それは、半端な投資ではない。しかし、患者だったらどうしてほしいか? その一点で投資を行った。その結果、以下のような安全で質の高い医療の導入につながった。
安全性を高める治療の導入
•経口摂取が難しい患者向けにより安全な末梢挿入型中心静脈カテーテルを導入
•摂食嚥下サポートチームの設立:嚥下(えんげ)内視鏡検査を活用し、必要な患者には嚥下機能評価や摂食機能療法を実施
慢性期患者の回復支援
•リハビリテーションの充実:患者の機能回復を促進
•排尿自立支援チームを設立し、人としての尊厳を守り日常生活動作(ADL)の向上をサポート
野村病院は単なる「慢性期病院」ではなく、慢性期患者の回復を追求する「慢性期治療病院」であり、すべての患者に少しでも健康になってほしいという決意の実践だった。多額の投資は決して勧められたからではなく、患者を少しでもサポートして出来れば回復して欲しいとの思いと、導入にあたっての熟慮の結果だった。だからこそ生きる投資となった。
「働き続けたい病院」とは—野村病院の職場改革

野村理事長は、自身の勤務経験を振り返り、「自分ならどんな病院で働き続けたいか?辞めたいか?」を考えた。そして以下のような職場にしようと決意した。
•理不尽が横行しない職場
•忙しくてもスキルアップできる職場
•働きやすく、やりがいが持てる職場
選ばれるためには何が必要なのかを細かく分類して一つ一つリアルにイメージして行動に移した。新入看護師の意見や全職員へのアンケートなどにより、施設・設備面では改善が進んでいた。次に、働き方や制度面の改革に着手し、以下のような制度・環境を整えていった。
働きやすい職場環境の整備
•定年延長・定年後の継続雇用
•残業ゼロ運動・有給休暇取得の推進
•男性の育児休暇取得の促進
•妊娠・出産・子育てしやすい職場環境・制度の整備
多様な働き方を尊重する環境を整えた結果、職員の確保は順調に進み、その中にはウィンタースポーツを楽しむために夏季のみ勤務する看護師もいるほど、柔軟な働き方が実現された。
日本最大のアワード「ダイバーシティ(多様性)&インクルージョン(包摂性) D&I AWARD 2023」で全国の病院で唯一認定

こうした取り組みが評価され、野村病院は「ダイバーシティ(多様性)&インクルージョン(包摂性) D&I」に取り組む企業を認定する日本最大のアワード「D&I AWARD 2023」で全国の病院で唯一認定され、さらに「D&I AWARD 2024」ではベストワークプレイスに選ばれた。これらの努力の結果、直近3ヶ月で看護師の応募は12人、その74%が紹介業者を介さない直接応募という高い割合を達成した。
「伝える力」が病院を成長させる—情報発信がもたらす好循環
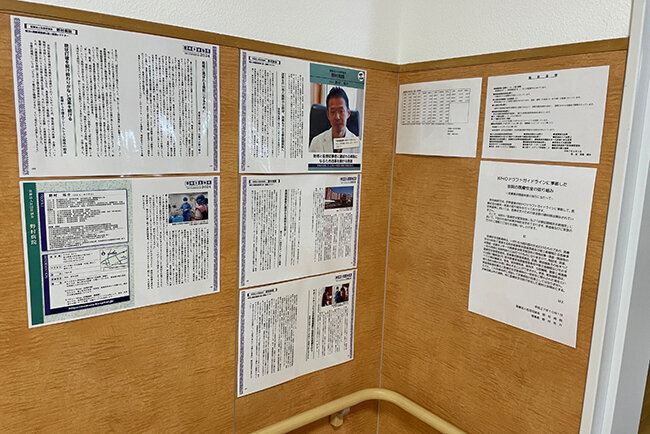
野村病院が「地域・医療従事者に選ばれる病院」となれたのは、積極的な情報発信が大きな力となったからだ。発信する情報量は圧倒的に多く、理事長の思いや理念、治療の内容、働く環境が明確に伝わる。その結果、他の病院で不満を感じている医療従事者や、理念に共感する医療従事者が積極的に応募するようになった。そのような職員はモチベーションが高く、入職すると病院のパフォーマンスはさらに上がり、その成果を情報発信することでさらに共感する医療従事者が応募してくれる。このようにプラスのスパイラルを描きながら野村病院は成長を続けている。野村病院のホームページは患者向けの情報を発信しているように見えながら、実は「医療従事者に向けた採用メッセージ」という側面も持っている。当然ながらそこで働く職員は、外部の評価を誇りとしながらも決して手を抜くことができない、いや手を抜かない心地よさを感じているようだ。
ICTの力で病院を進化させる—業務効率化と成長の実現

野村病院は「地域・医療従事者から選ばれる病院」として成長を続ける一方で、介護部門での見守り支援システムなどICT・最新デバイスの積極導入にも力を入れている。これにより、医療・介護の質向上と職員の業務効率化を同時に実現している。
最近導入した主なシステム
インカム導入→職場環境の改善、職員の物理的・心理的負担の軽減
•どこにいるかわからない職員の居場所の迅速な把握
•PHSの1対1の通話から、全スタッフへの瞬時の情報共有へ
•業務効率化と時間短縮、業務の質向上、新たな業務の実行で多大な成果
勤怠管理システムの導入→圧倒的な省力化を実現
•以前は200人の出勤職員のタイムカード打刻に20分かかり、確認にも手間がかかっていたが解消
•デジタル管理により、作業の大幅削減&人員削減に成功(データを見ればよいので3人の職員が不要になり他の仕事ができるようになった)
ホームページ簡易作成ツールの導入→情報発信の強化
•以前は理事長のみが操作可能だったが、スタッフも利用できるように改善
•医療従事者向けの情報発信に重点を置き、採用強化にも貢献
デジタル化で築く持続可能な病院運営
野村理事長はこれからの病院経営は、生産年齢人口の減少(職員不足)を見越した戦略が必要だという。ロボット化、RPA(業務自動化)、AI導入などにより業務の効率化・質の向上、職員の負担軽減、人手不足への対応が必要なのだ。そして、常に使えそうな技術情報をストックしながら、タイミングを見て即座に活用できる体制を整えている。このように、野村病院は「今だけでなく、未来を見据えた対策」を打ち続け、選ばれる病院としての地位を確立し続けている。
「人を尊重する」哲学が生んだ病院経営の成功
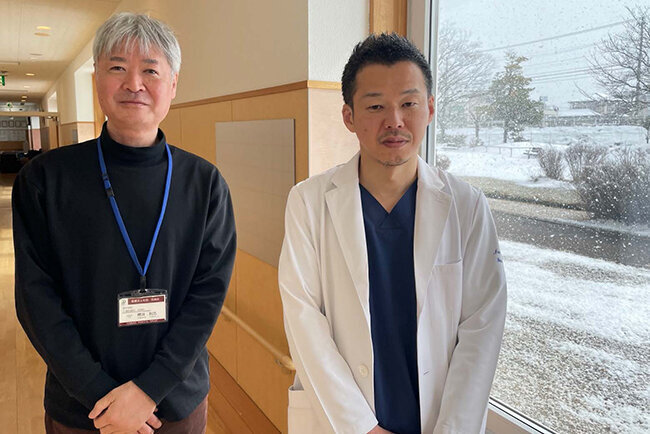
野村病院は明確な理念のもと、医療と組織を整え続けてきた。その根幹には「当院はなんのために存在するのか?」という問いがある。その答えの一つは「患者さんに良い医療を提供するため」。そのために「自分が患者だったらどうしてほしいか?」、そして「自分が職員だったらどういう職場であってほしいか?」を常に考え続けている。
野村理事長は、相手を尊重して、相手の立場に立って「自分ごと」として感じ、考え行動する。その結果、患者や職員たちからの共感が得られ、信頼関係が築かれ、選ばれ続ける病院になることができた。ICTやさまざまなデバイスなどを導入することは大切なことだが、組織が「共感と信頼」をベースに動けると予想以上の成果が得られると感じた取材だった。そこには、「人を尊重する」という哲学が根付いていた。野村病院の今後ますますの進化が楽しみだ。
企業概要
| 病院名 | 医療法人社団尽誠会 野村病院 |
|---|---|
| 所在地 | 富山県富山市水橋辻ヶ堂466-1 |
| 電話 | 076-478-0418 |
| HP | https://nomura-hospital.jp/ |
| 開業 | 1967年10月 |
| 従業員数 | 常勤医師7人含め約250人 |
| 事業内容 | 慢性期病院(医療療養病床200床)、介護医療院 (100室) |




















