
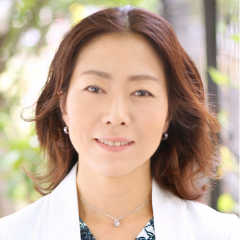
会社経営を開始して戸惑う税務処理のひとつに、「支払調書の提出」がある。特に、不動産取引についてはいくつか種類があり、区別もさることながら書き方にも迷うことが多いだろう。今回は、不動産取引で必要となる支払調書の種類や書き方について解説する。
目次
法人における不動産の支払調書の概要と手続き
不動産の支払調書とはどういうものなのだろうか。なぜ提出が義務付けられているのだろうか。具体的な手続きを含め、概要を解説していく。
法人が不動産取引を行うと支払調書を出さなくてはいけない
法人が不動産の購入や賃借を行うと、多くの場合は支払調書を提出しなくてはならない。この支払調書は、不動産取引以外にも「報酬・料金・契約金」や「利子等」「配当等」などさまざまなものがある。法人は個人以上に一定の事業目的で活動し、自社ビル購入や社宅・事務所用物件の賃借等で不動産取引にかかわることが多いため、支払調書の提出が義務付けられているのだ。
支払調書を提出すべき3つの不動産取引
法人が支払調書の提出を求められる不動産取引は、次の3つである。
・不動産の購入・交換・競売・公売・現物出資等
・不動産の賃借(使用料の支払)
・不動産の仲介料・あっせん料の支払
不動産取引で「お金を支払う側」になった場合、支払調書を出すことになる。それぞれの取引で求められる支払調書については後述する。
支払調書を提出しなければならない理由
費用を払っている側なのに、なぜ支払調書を提出しなくてはならないのだろうか。その理由は「提出する側の法人を監視するため」ではない。その逆で、「物件の購入や賃借の相手方となった個人・法人の申告を監視するため」である。
日本の税制は、原則として自主申告制度を採用している。つまり、個人・法人がそれぞれ正直に収入・費用・利益を正確に計算し、申告することを前提にしているのだ。ただ、それでも魔が差すのが人間だ。ふっと気が迷って「これくらいバレないだろう」と売上を一部隠したりすることがないとは言えない。
そういう事態に備えるために、取引の相手方である購入側や賃借側に取引の正確な内容を記入させた文書を「支払調書」として提出させているのだ。支払側の立場としては、過大に書いたら不正申告として扱われるし、取引の相手側にも迷惑がかかるためいい加減なことは書けない。つまり、正確な内容を書かざるを得ないというわけだ。こういった心理も上手に活用して、適正な自主申告制度をより確実にしているのである。
不動産取引の支払調書、提出先と時期は?
支払調書の提出自体は次のようになる。
1.提出時期
支払が確定した日の属する年の翌年1月31日。
つまり、2019年中に支払が確定したものについては、合計して支払調書に記載して提出することとなる。なお、通常は支払調書だけでなく「法定調書合計表」にも記入を行い、添付した上で提出することとなる。
2.提出先
提出先は各法人の所轄の税務署である。
3.提出方法
提出方法には次の3つがある
・書面で提出
・光ディスク(CD、DVD)に電子データを記録して提出
・e-taxで提出
ただし、紙の提出には制限がある。法定調書(源泉徴収票や支払調書)の枚数が1,000枚以上になった場合は、e-taxか光ディスクでの提出しか行えない。
不動産取引の支払調書を提出する際の注意点3つ
では支払調書を提出する際、どのような点に注意すればよいのだろうか。ここでは起こりやすいミスについて見ていこう。
1.マイナンバーの記載に要注意
2016年1月にマイナンバー制度が始まって以来、原則としてすべての支払調書に自社および取引先のマイナンバーの記載が必要になった。これは、不動産取引に関連する支払調書も例外ではない。支払調書には、自社分だけでなく、取引相手となった法人・個人のマイナンバーも必要となるので注意したい。
ただ、場合によってはマイナンバーを教えてもらえないこともあるだろう。法人のマイナンバーは法人番号検索サイトから検索できるが、個人の場合は相手の同意がないと入手できないのだ。
この場合、単に未記載のまま提出するのではなく、「『支払調書に記載が必要なので教えてください』とお願いしてがんばったけれど断られた事実」と「お願いした時期」を具体的にメモしておく必要がある。事後的に「やむを得なかった」ことを証明するためだ。
2.支払調書は取引の相手方への交付義務はない
支払調書は源泉徴収票と異なり、支払先への交付義務はない。求められているのは税務署への提出だけだ。たまに受け取ることもあるかもしれないが、それはあくまでも相手先の厚意にすぎない。
3.期限までに提出がない場合は罰則も
期限までに提出がない場合には、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」というペナルティが課される可能性がある。
不動産の支払調書の2つの種類
法人が不動産取引を行った場合、税務署に提出しなくてはならない支払調書には次のようなものがある。
1.不動産等の譲受の対価の支払調書
法人が不動産等を購入などにより譲り受けた場合、「不動産等の譲受の対価の支払調書」を作成しなくてはならない。この支払調書の作成にあたっては、次の点を注意したい。
1.対象不動産は建物や土地だけではない
「不動産」とあることから建物や土地だけと思いがちだが、実際には借地権等の不動産の上に存する権利や船舶・航空機をも含む。
2.同一人物への支払額が100万円以下なら提出不要
不動産購入といっても、すべて提出しなければいけないわけではない。同じ人や同じ会社からの購入額が年間100万円を超える場合に限られる。なお、この「100万円超か否か」の判定は、原則、消費税を含めて行うべしとされている。ただ、請求書などで本体価格と消費税が明確に区分されているならば、本体価格で判断して構わない。
3.固定資産税の精算金も含めて記載
通常の不動産取引では対価とともに固定資産税の精算金を買主が支払うことになるが、このときの精算金も対価の額に含めることとなる。
4.「譲受」には購入以外もある
「譲受」というと一般的には購入を指すが、交換・競売・公売・収用・現物出資も譲受に含まれることを念頭に置いていただきたい。特に、金銭のやりとりが生じない現物出資については、うっかりしやすいので注意が必要だ。
また、この譲受に伴い、不動産の対価以外に移転のための補償金が支払われる場合は、支払調書の摘要欄に補償金の種類と金額を記載しなくてはならない。
2.不動産の使用料等の支払調書
事務所やビル、土地の賃貸や社員用の社宅の借り上げなどで法人が不動産を利用している場合、「不動産の使用料等の支払調書」を提出しなくてはならない。こちらも不動産等の譲受の対価の支払調書と同様、注意点がいくつかある。
1.不動産の使用料等は賃借料だけではない
不動産の使用料等には家賃や賃借料だけでなく、次のものも含まれる。
・地上権、地役権の設定
・賃借に伴って支払われる権利金や礼金
・契約期間満了時や借地にある建物の増改築に伴って支払われる更新料や承諾料
・借地権・借家権を譲り受けた場合に支払われる名義書換料
2.年間の支払額が15万円以下なら提出不要
同一の法人や個人に対する支払額が年間15万円を超えた場合のみ、この支払調書の提出が必要となる。なお、判定については不動産の譲受の場合と同じく、原則は消費税込の金額で行う。ただし、契約書や領収書などで本体価格と消費税額が明確に区分されている場合には、本体価格でのみ判定して構わない。
ちなみに、この15万円の判定の仕方は、支払先が法人か個人かで変わる。これは次の2.で解説する。
3.支払う相手が法人か個人かで扱いが異なる
不動産の譲受の場合と異なるのが、支払相手により対処が変わる点だ。支払先が法人か個人かで次のように異なる
【法人の場合】
支払調書に記載するのは権利金と更新料のみだ。そのため、法人に支払う権利金や更新料等の金額が年間15万円以下であれば、支払調書を提出しなくてよいのである。
例えば、法人に支払う事務所の賃借料が年間600万円でも、権利金と更新料がないなら支払調書の記入を提出しなくてよいのだ。逆に、法人に支払う事務所の賃借料が10万円でも、権利金や更新料で30万円支払うなら支払調書の提出が必要になる。
【個人の場合】
個人に支払う使用料等については、家賃や賃借料等、権利金や更新料等すべての金額をもって判断する。家賃だけで年間15万円を超えていた場合は、支払調書を提出しなくてはならない。また、記載する内容も、これらすべての項目と金額になる。
4.イベント会場など一時的な賃借も支払調書提出の対象
「本項目の支払調書の対象は長期的かつ継続的な賃借のみ」と認識している人が多いが、実は一時的な賃貸借の合計額が年間15万円を超えた場合も、支払調書の提出対象となる。例えば、次のような場合だ。
・イベント会場の一時的な賃借
・陳列ケースの一時的な賃借
・広告などのための塀や壁などの一時的な賃借
・不動産等の売買または貸付けのあっせん手数料の支払調書
これらは、法人が不動産の仲介業者などに不動産売買や賃貸借に伴うあっせん料を支払った場合に提出が求められる支払調書だ。注意点は以下のようになる。
1.年間の支払額が15万円以下なら提出不要
同一の法人や個人に対する支払額が年間15万円を超えた場合のみ、この支払調書の提出が必要となる。なお、判定については不動産の譲受の場合と同じく、原則は消費税込の金額で行う。ただし、契約書や領収書などで本体価格と消費税額が明確に区分されている場合には、本体価格でのみ判定して構わない。
2.「譲受」・「使用料等」の支払調書に記載したなら作成不要
「不動産の譲受の対価の支払調書」「不動産の使用料等の支払調書」それぞれに、あっせん料の支払先や支払額を記載する欄(「あっせんをした者」という欄)がある。この欄に記載した場合、あっせん料の支払調書を別途提出しなくてよい。
支払調書の提出が必要な不動産取引は?記載内容や注意点も
以上が、法人の不動産取引に必要な3つの支払調書である。ここで、よくある不動産取引のパターン別に応じた支払調書の種類と記載内容について列挙していく。
1.社宅の借り上げ
社員の住まいとなる社宅を借り上げた場合、支払調書の提出が必要となる。
1.提出が必要な支払調書
社宅の借り上げについて提出が必要な支払調書は「不動産の使用料等の支払調書」である。
2.提出が必要になる場合
家賃や賃借料については、貸主が法人か個人かによって提出が必要となる条件が異なるので注意しよう。
(1)貸主が法人
年間に支払った更新料や権利金の総額が15万円を超える場合
(定期的に支払う家賃については考慮不要)
(2)貸主が個人
年間に支払った家賃・更新料・権利金等の総額が15万円を超える場合
3.記載内容
・支払を受ける者(貸主)の住所・氏名・マイナンバー
・物件の種類:「家賃」「地代」「更新料」「名義書換料」など支払内容に応じて記載
・所在地:物件の所在地を記載
・細目:「宅地」「鉄骨2階建社宅」など、土地の地目や建物の構造、用途等を記載
・数量:本年中の賃借期間、単位(月、週、日、㎡等)あたりの賃借料、戸数、面積等を記載
・摘要:賃借のときに支払った仲介料に関する詳細を「あっせんをした者」欄に記載する場合、本来支払調書に書くべき内容を記入する。
・支払者:不動産の使用料等を支払った人の氏名・住所・電話番号・マイナンバーを記載する
2.不動産の購入
社宅や自社ビルを購入した場合も、支払調書の提出が必要となる。
1.提出が必要な支払調書
不動産の購入は「不動産の譲受」に該当するため、「不動産の譲受の対価の支払調書」の提出が必要となる。
2.提出が必要になる場合
不動産を購入した場合、その購入金額が年間100万円を超えると支払調書の提出が必要となる。譲受については相手が個人か法人を問わない。
3.記載内容
・支払を受ける者(売主)の住所・氏名・マイナンバー
・物件の種類:「土地」「借地権」「建物」など譲り受けた不動産に応じて記載
・所在地:物件の所在地を記載
・細目:「宅地」「鉄骨3階建事務所」など土地の地目や建物の構造、用途等を記載
・数量:土地の面積、建物の戸数、建物の延べ面積を記載
・取得年月日:不動産の所有権が移転した年月日を記載
・支払金額:本年中に確定した支払金額を記載する。この支払金額には、本年中に支払われなかった未払額を含む。
・摘要:譲受の内容について「売買」と記載した上で、「代金の支払年月日」「支払い年月日ごとの支払方法(現金、振込、小切手など)と支払額」を記入する。また、購入のときに支払った仲介料に関する詳細を「あっせんをした者」欄に記載する場合、本来支払調書に書くべき内容を記入する。
・支払者:不動産を譲り受けた人の氏名・住所・電話番号・マイナンバーを記載する
・不動産の購入や賃貸に際し受け取った仲介料について支払調書を書く場合
不動産の売買や賃借に伴い仲介料を支払う場合、支払調書の提出が必要となる。譲受や使用料の支払いに伴う支払調書の「あっせんをした者」欄に書くなら提出を省略できるが、別途支払調書を作成して提出する場合は、以下の内容に注意したい。
1.提出が必要な支払調書
「不動産等の売買または貸付けのあっせん手数料の支払調書」を提出する
2.提出が必要になる場合
支払ったあっせん料が年間15万円を超えると、支払調書の提出が必要となる。譲受については相手が個人か法人を問わない。
3.記載内容
・支払を受ける者(仲介者・あっせん者)の住所・氏名・マイナンバー
・区分:「譲渡」「譲受」「貸付」「借受」など、仲介した取引について記載
・支払金額:本年中に確定した支払金額を区分ごとに記載する。この支払金額には、本年中に支払われなかった未払額を含む。
あっせんに係る不動産等:「譲受」や「使用料等」の支払調書と同じような内容を記載する。具体的には次のようになる。
・「物件の種類」:「土地」「建物」「借地権」などあっせんした不動産の種類を記載
・「数量」:土地面積や建物の戸数、延べ面積などを記載
・「取引金額」:売買や貸付の対価の額を記載。なお、賃借については、使用料の単位(㎡や週・月・日など)あたりの使用料を記載
・支払者:不動産売買や賃貸借契約に伴うあっせん料を支払った人の氏名・住所・電話番号・マイナンバーを記載
こんな場合はどうすべき?よくある3つのパターン
すべての不動産取引が分かりやすければよいが、中には「これはどの取引に該当するのか」「支払調書の提出が必要なのか」が分かりにくいものもある。以下で、具体例とその対処法を紹介する。なお、いずれのケースも「売主や貸主の立場になってみること」が考え方のヒントだ。
1.会社が賃貸借契約しているけど社員本人が家賃を支払っている場合
会社が賃貸借契約をしているからといって、全額を会社が負担するとは限らない。敷金は会社が負担するけれど、月々の家賃や更新料は社員が負担することもある。この場合、会社は更新料も家賃も負担していないため、一見支払調書の提出義務がないように見える。しかし、実は提出しなくてはならないのだ。なぜなら、契約当事者は社員ではなく会社だからである。
貸主にとっては、敷金・家賃・更新料を誰が払うかは関係ない。ただ、きちっと払われるべきものが払われればよいだけだ。もし、家賃や更新料の入金がない場合、請求先は社員ではなく契約の相手方である会社となる。契約の当事者ということは、いざというときの責任の所在は自分に来るということである。
なお、このケースにおける支払調書の提出の要否の判定は、すでにお伝えした通り契約先が個人か法人かで変わってくる。また、支払調書には原則通り、年間に支払った全額を区分ごとに記載する。
2.翌年1月分の家賃を本年中に支払っている場合
本年分の家賃・賃借料や更新料が、本年中にきちっと支払われることは稀だ。多くの場合は年をまたいで支払われる。本年10月から翌年1月の家賃がまとめて本年9月に支払われる、という支払パターンはよくあることだ。この場合、支払調書にはどのように金額を記載したらよいのだろうか。
支払調書には、翌年1月までの家賃を含めて記載する。なぜかというと、支払調書に記載すべき金額は「本年中に支払が確定した対価の額」となっているからだ。本年中に支払が確定したということは、「その金額については本年中に請求できる」ことを意味する。
法人の会計は企業会計原則にのっとり、家賃の支払は通常期間、経過に応じて計上する。このルールと若干外れた記載の仕方であるため一瞬戸惑うが、貸主の立場になって考えてみると分かりやすい。
3.家賃を不動産管理会社に支払っている場合
「個人から借りていても実際の支払は不動産管理会社」というのも、よくあるケースだ。近年は特に不動産投資ブームもあり、不動産管理会社を間に置いて個人の不動産投資家が貸し出すケースもよく目にする。この場合、相手方は法人と考え、権利金や更新料が年間15万円を超えなければ支払調書を提出しなくてよいのだろうか。
このケースでは、「個人に対する不動産の使用料等の支払」と考える。つまり、権利金や更新料だけでなく家賃も支払調書の提出の要否を判断する材料になるし、支払調書の記載内容ともなる。なぜなら、不動産管理会社はあくまでも収受の代行をしているにすぎず、最終的に家賃を収受しているのは個人だからだ。
なお、この場合、「支払を受ける者」には貸主である個人の氏名や住所等を、摘要欄には不動産管理会社の名称や住所等を記載する。
文・鈴木まゆ子(税理士・税務ライター)




















