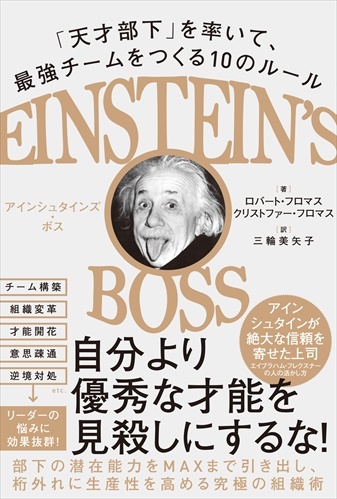
※画像をクリックするとAmazonに飛びます
アインシュタインの上司
アインシュタインの上司と聞いて、すぐにその名前が浮かぶ人は少ないかもしれない。仕事のためにアメリカへ渡ったアインシュタインの直属の上司は、エイブラハム・フレクスナーという人物だった。フレクスナーはすぐれた管理者だったが、天才ではない。もともとは高校の教師で、博士号も持っていなかった。物理学者でも数学者でもなかった。学術論文は一本も書いたことがなかったという。
アルベルト・アインシュタインは、そのフレクスナーが一九三〇年に立ち上げた高等研究所で、最初に雇った科学者のひとりである。アインシュタインの加入により、高等研究所はまたたくまに学術機関としての信頼を勝ち得た。
だが、フレクスナーがいなければアインシュタインは高等研究所に来なかっただろうし、アインシュタインがいなければ研究所の成功はなかったかもしれない。創立初期の一九三〇年代から四〇年代にかけて、アインシュタインが研究所の対外的な顔を務めていたからだ。まもなく、もう十数人の傑出した数学者と物理学者が加わり、フレクスナーはその科学者たちを結束の強いチームに仕立てた。
彼はアインシュタインほど賢くなかったが、天才部下を率いるときに大事なことはわきまえていた。みずから徹底した自己評価をおこなうことで、成功するチームを作ったのである。
高等研究所はノーベル賞受賞者を三三人、非凡な数学者に贈られるフィールズ賞(数学のノーベル賞と称される)受賞者を四二人、優秀な科学者を称えるウルフ賞とマッカーサー賞の受賞者を多数輩出している。
フレクスナーが集めた天才のチームは、二〇世紀最高の科学的進歩をいくつか成し遂げたことで有名だ。すぐれた科学者が自由な環境で存分に創造性を発揮できたからだが、そのためには所員に給料が払われているか、冬場に暖房が行き渡っているか、電気がつくか、個性豊かな天才たちがチームとして目標を達成できるかを、だれかが確かめる必要があった。その人物が、高等研究所の初代所長エイブラハム・フレクスナー、アインシュタインの上司だったのだ。
そんなフレクスナーの築いた高等研究所は、歴史上類を見ないほど優秀で生産性の高い科学者の集団になった。
思いやりと忍耐の人
フレクスナーは「器よりも中身が大事」だと主張し、ともに働く人々に助力を惜しまなかった。私財を投じて、当時のどこの大学よりも高い給料と、授業負担のない終身在職権(テニュア)を提供した。おかげで高等研究所の科学者は、自分の時間を好きなだけ研究に費やせた。
フレクスナーは多くのリスクも負って科学者たちを支えた。大恐慌時代としては異例の、所員の年金基金を作ったのだ。支給が始まるころには景気が上向いていると踏んだようだが、あいにく最初の支給時期が来ても、その基金では月々の支払いをまかなえなかった。資金不足を解消すべく、フレクスナーはあちこちの夕食会に出向き、慈善贈与(つまりカンパ)を集めてまわった。
フレクスナーは思いやりと忍耐の人でもあった。度が過ぎると言ってもいいほどに。彼がチーム作りをしていたのは、ヒトラーが権力を握ろうとしていた時代である。そのころフレクスナーは、ドイツの物理学者でユダヤ人の妻を持つヘルマン・ワイルに、高等研究所の教授のポストを申し出た。ワイルはその申し出を断り、祖国ドイツにとどまることを選んだ。
だが、ヒトラーがドイツでユダヤ人の組織的な虐殺を始めると、ワイルは取り返しのつかない間違いを犯したことに気づいた。そしてフレクスナーからの再度の申し出を受け、妻とドイツを逃れて、アインシュタインのいる高等研究所に加わった。フレクスナーは憔悴していたワイルに会い、一度は断わられながらも、ワイルが求めるものを差し出したのだった。
フレクスナーは天才それぞれのモチベーション[訳注:やる気を起こさせる心理的な誘因、または動機づけ]が違うと気づき、相手に応じてスカウトの仕方を変えた。たとえば、革新的な経済学者のエドワード・アーリーは結核を患っていたが、フレクスナーはアーリーの才能と人柄を高く買い、病気で仕事を失っていた彼に教授のポストを提供した。
数年後、快復してアインシュタインやワイルの同僚になったアーリーは、フレクスナーへの恩義から研究に励み、経済学で大きな業績を挙げた。さらにアーリーは、気難しく頭に血が上りがちな天才たちの仲介役も買って出た。健康が危ういときに親身になってもらえたことで、感謝と忠誠心を抱くようになったのである。
イノベーションの肝は「井戸を掘る」こと
高等研究所の創設にあたって、フレクスナーは数学と物理学をまず中核ミッションに選び、のちに経済学と歴史学を加えた。今日も高等研究所には、数学、歴史学、社会科学、自然科学の四部門しかない。多くのことで適度に秀でるよりも、少しのことで世界トップレベルになろうというもくろみだ。
こうした集中的なアプローチは、イノベーションの創出に欠かせない。進歩は万人の知るありふれた知識からではなく、極端に偏った知識から生まれるからだ。
イノベーションの肝は「井戸を掘る」ことであり、「畑を耕す」ことではない。以前、ある化学者に言われたことがある。「問題だらけの課題をどうにかしたければ、焦点を絞るべきですよ」と。
フレクスナーは才能ある人々をどんどん高等研究所に招き、教授たちと交流させたり、研究を評価してもらったりした。いつもと違う顔ぶれが出入りすれば、常任のメンバーがマンネリや自己満足に陥らずにすむだろうと考えたわけだ。そうして招かれた科学者には、ノーベル賞受賞者のニールス・ボーア、数学者のジョン・フォン・ノイマン、理論物理学者のポール・ディラックなどがいた。
古い問題に新しい手法で取り組むことも、フレクスナーは恐れず支持した。問いさえまだ立てられていない未知の分野への挑戦を勧めた。刺激を与え合ってすごいことが起きるかもしれないと、物理学者、経済学者、数学者、歴史学者、考古学者を積極的に交流させ、実際にそれを起こした。
たとえば招聘者から常任教授になったジョン・フォン・ノイマンは、初期のコンピュータに魅せられ、研究棟の地下室でコンピュータを自作した。
フレクスナーはノイマンに理論物理学者になれとも、真空管を扱う電気技師になれとも言っていない。ただノイマンの好きなようにさせたところ、記憶装置を有する最初のコンピュータが生まれたのである。
能力主義の文化
創立当初のフレクスナーはあらゆる重要な決定について、とりわけ採用について教授陣によく相談した。科学者でない彼はチームの意見を大事にしていた。教授会をたびたび開き、所の方向性や課題について話し合った。異なる意見に寛容だったし、相手の話を聞く耳も持っていた。
フレクスナーが望んで作り上げたのは、能力主義の文化だ。彼は教授のランクを、地位や立場ではなく業績によって決めた。多くの社会的障壁を破り、出自にかかわらず最もすぐれた人物を採用した。
アメリカの大学で反ユダヤ主義が横行していたときに、高等研究所の教授の多くがユダヤ人だったのはそのためだ。
高等研究所と密接な関係にあったプリンストン大学には、ユダヤ系の学生を一定以上受け入れないとする正式な規定があり、ユダヤ系の教員の数も内々に決められていた。
フレクスナーはその規定も性別の壁も無視した。終身在職権を持つ女性研究者がいなかった時代に、考古学者のへティ・ゴールドマンを終身地位で雇った。
フレクスナーがこのような規格外のチームを作ったのはなぜか。人種や性別などの先入観を介在させたくない、という思いがあったからだ。彼は慣習によらず、また偏見に惑わされることなく、最もすぐれた人物を採用した。能力主義の環境を作り、創造性を発揮できる自由を与えた。
10のルール
天才部下を率いるための私の手法は、高等研究所を創設して運営したフレクスナーの手法と重なる点が多い。それをここで紹介しよう。次の一〇のルールは、聡明な人々を率いるときにリーダーが何に気をつけ、どう対処すればいいかをまとめた私なりの処方箋だ。この一〇のルールで天才部下を率いれば、彼らはきっと常識を超える発見を成し遂げ、あなたを悩ます複雑な問題を解決してくれるだろう。
1 鏡と向き合う
2 邪魔をしない
3 黙って耳を傾ける
4 石をひっくり返す
5 化学よりも錬金術を使う
6 過去を未来の事実にしない
7 リスを無視する
8 心と頭を調和させる
9 問題で気を引く
10 危機とうまくやる


















