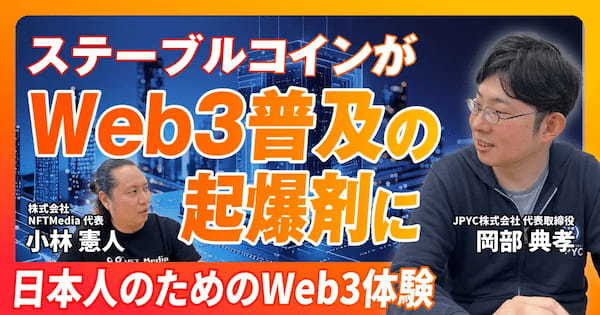
「とにかく世の中に対して意見を発信すべきです」
JPYC株式会社の岡部 典孝さんはそう語ります。ステーブルコインの事業では、法改正など予測不可能な変化に対応しなければなりません。このような環境下で、岡部さんは果たしてどのようなマインドでビジネスに向き合っているのでしょうか。
前編では、岡部さんの歩みやJPYC創業のきっかけ、「JPYC Prepaid」の特徴について伺いました。後編ではJPYCの事業戦略や岡部さんの起業家マインドについて深堀りします。
| 岡部 典孝(おかべ のりたか) JPYC株式会社 代表取締役 日本円ステーブルコイン「JPYC Prepaid」を発行するJPYC株式会社の創業者兼代表取締役。一般社団法人ブロックチェーン推進協会理事やブロックチェーン普及推進部会部会長を務める。大学在学中に有限会社リアルアンリアルを創業し、その後もリアルワールドゲームス株式会社を立ち上げるなど、起業家として20年以上のキャリアを持つ。 |
| 小林 憲人(こばやし けんと) 株式会社NFTMedia 代表取締役 2006年より会社経営。エンジェル投資を行いながら新規事業開発を行う株式会社トレジャーコンテンツを創業。2021年にNFT Mediaを新規事業として立ち上げる。「NFTビジネス活用事例100連発」著者。ジュンク堂池袋本店社会・ビジネス書週間ランキング1位獲得。 |
▶︎YouTubeでの視聴はこちら
目次
ステーブルコイン市場における日本の現在地

小林:前半では「JPYC Prepaid」について伺いましたので、ここでは業界全体に関してお聞きします。ステーブルコインについて、グローバル市場における現状をどのように捉えていますか。
岡部:ステーブルコインの市場は過去5年間で約50倍に成長しており、今後もさらに10倍程度の成長が予想されています。遅かれ早かれ、現実の法定通貨のマーケットを超える勢いで拡大していくはずです。
グローバルシェアでは、USDTとUSDCが大部分を占めていますね。市場規模は日本円換算で30兆円から34兆円ほどです。そして驚くべきことに、1ヶ月の取引高で見ると約500兆円ほどに達します。
小林:約500兆円とはとんでもない数字ですね。グローバルでは、それほど巨大な市場に成長しているのですね。一方で、日本のステーブルコイン市場はまだまだ発展途上という印象です。世界と比較すると、日本は遅れを取っているのでしょうか。
岡部:おっしゃる通りです。日本は規制の整備自体は比較的早かったのですが、実際に日本円のステーブルコインを発行するための許認可がまだどの発行体にも下りていない状況です。
そのため、現状は前払式支払手段としてのトークンに留まっており、本格的な日本円ステーブルコインはまだ市場に出ていません。
小林:法整備がされたにもかかわらず許認可が出ないのは、何か具体的な原因があるのでしょうか。
岡部:例えば過去に何らかの金融事故が起きると、セキュリティ基準が厳格化されて、審査に時間がかかる傾向にあります。
新設の許認可では、法律の施行後に政省令という細かい規則やガイドラインが作られるため、この作業に1年ほどを要します。つまり、法改正後にすぐ許認可が下りるわけではないのです。これは、ある程度仕方のない部分です。
そしてガイドラインが導入された後、実際に許認可を取得するのにも1年程度かかる場合があります。これも、新しく登場した複雑なライセンス制度であれば、想定内だと言えるでしょう。
小林:つまり、最低でも2年はかかるのですね。
岡部:はい。加えて、金融事件や事件が発生すると規制当局も慎重になるため、結果として許認可までの期間が延びていきます。JPYCも最速で進めているつもりですが、当初の想定よりは半年から1年ほど遅れているのが実情です。
ステーブルコインがWeb3普及の起爆剤に

小林:Web3やNFT領域について、マーケットのポテンシャルや将来性をどのようにお考えでしょうか。
岡部:世界のWeb3マーケットの将来性については、もはや疑いの余地はないはずです。トランプ大統領も積極的に推進していますしね。問題は日本です。正直に申し上げると、我々のような事業者の責任もあって、なかなか進んでいない状況を申し訳なく思っています。
小林:と言いますと?
岡部:日本円のステーブルコインがない状態でNFTを取引するというのは、率直に言って無理があるんです。
例えば、1ETHで買ったNFTを2ETHで売ったとして、ETHの日本円でのレートが変動していたら、利益額はいくらなのかが直感的に分かりにくいですよね。
小林:たしかに、価格計算の時点でつまずいてしまいそうです。
岡部:それが例えば、「1万JPYCで買ったNFTを2万JPYCで売ったら、利益は1万円」となれば、非常に分かりやすくなります。
そこがスタートラインだと考えていて、この「分かりにくさ」が日本のWeb3市場における最大の課題だと思っています。
もう一つの課題はウォレットにあるのですが、ウォレットが普及しない理由も、結局はこの分かりにくさに起因している部分が大きいのではないでしょうか。ウォレットに「何円」とか「何JPYC」と表示されれば、もっと身近になるはずです。
小林:ステーブルコイン普及の遅れが、日本全体のWeb3の遅れに繋がっているのですね。
岡部:事業者である我々も、その点で責任を感じています。
ただ逆に言えば、ここからの伸びしろは非常に大きいとも言えます。価格変動リスクや利益計算の煩雑さ、そしてウォレット自体の使いにくさが解消されれば、Web3の社会実装が大きく進むはずです。そのための鍵が、日本円ステーブルコインだと考えています。
不確実性の高い業界で起業家が持つべきマインド

小林:ステーブルコインを取り巻く関連法令は、刻々と変化しています。このように不確実性が高い事業領域において、起業家として気をつけるべきポイントはどのような点でしょうか。
岡部:重要なのは、規制当局とうまくコミュニケーションを取ることです。「ステルススタートアップ」ではいけないと実感しています。
小林:ステルスではいけない、とはどういう意図でしょうか。
岡部:技術開発系のスタートアップであれば、水面下で開発を進めるのも一つの戦略です。しかし法規制が絡む領域で隠れて事業を進めると、企業側にとって都合の悪い形で法規制が進んでしまうかもしれません。規制当局も、未知の技術やサービスに対してはどうしても慎重姿勢にならざるを得ないからです。
小林:たしかに、「見えないものに対してはとりあえず厳しくしておこう」となりがちですものね。
岡部:「技術的には素晴らしいが、法規制が追いついていない」という状況は、スタートアップにとって大きな足かせになります。よって、ルールメイキングと事業開発はセットで進めるべきです。
「責任あるイノベーション」という言葉がありますが、「何をやるのか」や「どういうことをやりたいのか」を社会に対して発信し続ける姿勢が非常に重要です。そのため、私はXで積極的に発信活動を続けています。
小林:改正資金決済法について、率直に「ここは良いな」と感じる部分や「ここはもう少し改善が必要だな」と感じる部分があれば、教えていただけますか。
岡部:「良いな」という部分で言うと、非常にバランスが取れていて、スタートアップから銀行まで、さまざまなプレイヤーが参入しやすい点です。世界でいち早くステーブルコインの規制を作ったわりには、とてもバランスの良い内容になっていると思います。
一方で大変だと感じる部分は、DeFiやセルフウォレットをどこまで許容するかが不明瞭となっている点です。事業者がライセンスを取得する前提の制度であるため、社会全体へと普及させていく上で残された宿題がまだまだ多いと感じています。
日本初の円連動型ステーブルコインとは

小林:2025年7月、JPYCから日本初の円連動型ステーブルコインがリリースされる見込みです。この円連動型ステーブルコインについて、既存のJPYC Prepaidとの違いを教えていただけますか。
岡部:円連動型ステーブルコインは、日本円の電子決済手段として皆さんの手元にお届けできる初のコインです。これを実現させるためには金融庁から資金移動業というライセンスを取得する必要があり、その登録に向けてチーム一丸で取り組んでいるところです。
小林:新しいステーブルコインは、具体的に何が大きく変わるのでしょうか。
岡部:プリペイド式支払い手段との大きな違いとして、電子決済手段という形になると日本円に戻せるようになります。例えば、100万JPYCを手に入れた方がそれを事業者に送金すると、100万円が銀行口座に振り込まれる、といった運用が可能になります。
これにより非常に使い勝手が良くなり、今まで以上に円と連動した形でご利用いただけるようになります。
小林:それは大きな変化ですね。
岡部:もう一つの違いは、本人確認(KYC)が必須になる点です。
トークンを日本円に戻したり、USDCなど他の銘柄に交換したりする際には、ライセンスを持つ事業者が厳格に本人確認を行います。ただ、マイナンバーカードのICチップ読み取りなどで、簡単に手続きできるようにしたいと考えています。
AIフレンドリーでどこでも使える決済手段

小林:円連動型ステーブルコインを普及させていく上での今後の戦略をお聞かせください。
岡部:初動について、実はあまり心配していません。グローバルではステーブルコインの巨大なマーケットが既に存在しており、日本円のステーブルコインが登場すれば初期段階で一定の流通量までは到達できると予測しているからです。
今はさらに先の展開を見据えており、将来的には「AIフレンドリーなステーブルコイン」を目指していきます。一方で、スーパーマーケットのような既存の店舗でも使える環境を整えていきます。
小林:AIとの連携が鍵になるのですね。
岡部:あとは、手数料をなるべく取らない点を頑張ろうと思っています。クレジットカードだと数パーセントの手数料が徴収されますが、JPYCは行けるところまで手数料ゼロで進めるつもりです。
小林:手数料ゼロですか!
岡部:はい。PayPayも、皆さんに広く使っていただくために初期は手数料0%で普及させましたよね。
JPYCが既存の金融機関のように高年収で莫大なコストをかけているようであれば、手数料ゼロは厳しいかもしれません。しかし、我々はスタートアップですから、無駄なお金を使わないことで実現できると考えています。
小林:それは素晴らしいですね。
DAO型の地方自治を求めて青ヶ島へ

小林:少し話は変わりますが、岡部さんが東京都青ヶ島村に移住された理由は何だったのでしょうか。
岡部:最初に興味を持ったきっかけは、青ヶ島への好奇心です。以前から八丈島までは行ったことがあり、その先に青ヶ島という島が存在すると知っていました。そこで、「一度行ってみたいな」と思っていたのです。
小林:なるほど。
岡部:加えて、私は大学の客員教授としてDAO(自律分散型組織)の研究もテーマにしているので、実際に自治体がDAO的に進化していくと面白いなと考えていました。
そこでDAO的な分散型の運営をしている自治体がないか探していたところ、当時日本で一番人口の少ない村が青ヶ島村(人口約160名)だったのです。「もしかしたらDAO的な暮らしをしているのではないか」と興味を持ち、仲間と共に実際に訪問してみたのです。
小林:実際に訪れてみていかがでしたか。
岡部:ワーケーションで1週間ほど滞在したところ、食事が美味しく、実際にDAO的な暮らしをされていて、しかもインターネットも速い。「これは天国だ!」と感じ、早速移住しようと決めました。当時はちょうどコロナ禍で地方移住の機運が高まった頃で、タイミングも良かったですね。
小林:コロナ禍だったとはいえ、行ってみて1週間で「よし、引っ越そう!」となる行動力がすごいですね。
黙っていては、ルールメイクに関与できない
小林:Web3領域で新規事業を立ち上げようとしている、あるいはスタートアップとして挑戦しようとしている事業者の方々に向けて、アドバイスをお願いします。
岡部:私が一番学んだ点は、「法律とか規制は思ったより簡単に変わる」という点です。
特に最先端領域であるほど、簡単に変わると実感しています。ですから、「規制が整ったらやろう」や「今の規制でここまではできそうだからやろう」といった発想ではなく、「今はまだ規制が定まっていないけれども、良い方向に規制を変えていけば、きっとビジネスチャンスがあるはずだ」くらいの前のめりな姿勢で取り組むべきです。
小林:なるほど。この他には、ありますでしょうか。
岡部:ルールメイキングの領域においては、黙っていて良いことは一つも基本的にはない、という点です。一般的には「沈黙は金」だと言われますが、先端領域の分野では別です。
小林:むしろ発信すべきだと。

岡部:ひたすら発信して、その代わりに批判にも謙虚に向き合う。そのような姿勢で発信し続けることは、絶対にやった方が良いです。たとえ批判をいただいたとしても、それを糧にしてより良い仕組みを考えるといった向き合い方が建設的です。
発信しないと、既得権益を持つ人の思うがままになってしまいます。早く商品を揃えて表に出られるようにし、とにかく発信して自分に有利なルールを作る。すると、ルールは思ったより簡単に変わるはずです。
ステーブルコインの分野では、「こんなサービスは金融庁が許すわけない」と取り組む前から諦めてしまった人もたくさんいました。しかし、このような状況は起業家にとってはむしろチャンスです。正攻法で進めて、規制当局のドアをノックすれば、意外と扉を開けて話を聞いてくれるものですよ。
小林:真正面から会いに行く姿勢が大切なのですね。
最後に
小林:最後に、読者へメッセージをお願いします。
岡部:JPYCではライセンス取得が近づいてきており、やるべき業務はまだまだ山積みです。そこで、多くの方のお力をお借りしたいと思っています。
社外から業務委託の形で参画いただくのもありがたいですし、単純にXでリツイートしていただくといった応援も嬉しいです。もし、現在募集中の求人に興味があれば、XやFacebookで気軽にご連絡いただければと思っています。
小林:どのような職種で募集されているのでしょうか。
岡部:ビジネスデベロップメント(事業開発)からエンジニア、セキュリティ、リーガル、広報、人事、経理など、あらゆる領域でこれから一気に求人を公表する予定です。まだ求人が出ていない場合でも、「将来こういうポジションで貢献できるかも」という方がいらっしゃれば、ぜひ先にお問い合わせいただきたいです。
最新の求人情報は、JPYCの公式サイトに掲載しています。
小林:JPYCのサービスを一緒に広めていこう、という仲間を募集しているということですね。今回は、株式会社JPYCの代表取締役である岡部典孝さんにお越しいただきました。
貴重なお話をいただき、ありがとうございました!
岡部:ありがとうございました!
▶︎YouTubeでの視聴はこちら
関連リンク
| ・公式HP:https://jpyc.co.jp/ JPYC株式会社 公式X:https://x.com/jcam_official 岡部 典孝氏 X:https://x.com/noritaka_okabe |




















