(本記事は、藤井 正徳氏の著書『はじめて「資金繰りに悩む社長」を担当したときに読む本 「経営改善計画」の活用による業績改善コンサルティングの実践手法』セルバ出版の中から一部を抜粋・編集しています)

1. 売上拡大だけでは会社は救われない!?
売上至上主義の弊害
中小企業の社長さんに対して「今、何が御社の課題ですか」と質問をすると、昨今ではかなりの確率で、「採用難で人手が不足している」あるいは「もっと売上を増やしたい」のいずれかの答えが返ってきます。人手不足対策も、より多くの注文に対応するためという側面がありますから、基本的な考え方として「売上規模を拡大しさえすれば会社はよくなる」という認識を持たれている方の数はかなりの数にのぼります。
しかし、経営改善の場面においては、この考え方はある意味リスクを伴うものであると考えます。
まず、売上拡大は自社の営業努力がベースではあるものの、最終的には「あくまでお客さまありき」です。アクションプランを遂行することは100%約束することができたとしても、そのことによっていくら売上が上がるのかは最終的にお客様次第であり、どこまでいっても不確定要素が含まれます。金融機関サイドからみても、売上拡大中心の改善計画書は、実現可能性という観点でシビアに見られる傾向があります。
また、売上拡大には一定程度の「先行投資」が必要となります。もし本当に、まったくお金をかけることなく、新規のお客さまが増えたり、注文が取れたりすることが可能なのであれば、それ以前の営業努力が足りなかったことになります。もちろん、今まで以上に努力する、あるいはやり方を改善することで売上が拡大するという可能性はあります。しかし、少なくとも第三者から見たときに、「抜本的に売上が伸びる見込みである」と納得できる合理的な根拠にはなりにくいものと考えます。
最も重要なことは、売上が上がったからといって、利益が上がるとは限らないことです。売上拡大を求めるあまりに、粗利益率の低い売上の比率が高くなった結果、本業が傾いて経営改善が必要になったというケースは数多くあります。
「少しでも粗利益が稼げるのであれば、ゼロよりはなんぼかでも売上になるほうがよい」という考え方も間違いではありません。しかし、粗利益率が低い売上の比率が高まれば、その分だけ、社長さんが思っている以上に金銭的あるいは時間的なコストを消費します。明らかに判別できる粗利益だけを見ればプラスかもしれませんが、販売員等の時間的コストや輸送費、通信費、諸々を勘案するとマイナスになる可能性もあります。また、低収益の売上のために生産や販売のリソースを使ってしまうと、高収益の売上を確保できる余力が失われてしまいます。
体質改善してから売上規模拡大を図る
売上高は、中小企業の社長さんにとって、最もタイムリーにわかりやすく把握できる経営指標であり、そこに目を奪われてしまいがちになることはやむを得ないことです。経営がある程度順調に推移しているのであれば、売上高だけを追いかけてもそれほど困ることはありません。
しかし、業績不振で資金繰りに窮している状況から経営改善を図る場合、重視すべきはキャッシュフローであり、その源泉となる利益です。
利益率が低い会社は、例えるならば「燃費の悪い旧型車」です。目的地までたどり着くためには、たくさんのガソリンと時間を必要とします。乗り心地も悪く、ガタガタと振動しながら、道を進んでいきますので、途中の道のりも落ち着かない状態を強いられます。途中で事故に遭うリスクも高まりますし、ガス欠になれば目的地にたどり着くことはできません。
これに対し、体質改善が進んで利益率が高い会社は、「高燃費のハイブリッド新型車」です。目的地には少ないガソリンと時間で到達できます。乗り心地もよく、スイスイと気持ちよく走ることができます。事故に遭うリスクやガス欠になるリスクも低く、無事に目的地に到達できる可能性は高まります。
どちらの車に乗っても、最終的に目的地に到達できれば問題ありません。しかし、いきなり走り始める前に、すぐに走り出せる「燃費の悪い旧型車」を選ぶか、少し時間がかかっても「高燃費のハイブリッド新型車」を選ぶかを選択することができます。
利益率を高めて、お金が残りやすい体質改善を図ったうえで、売上拡大に向けてアクセルを踏み込むことで、より確実に、効率よく、快適かつ安全に、目的である経営改善目標を達成することができます。
損益計算書は下からチェックする
一般的に、損益計算書は上から、売上高→売上原価→(売上高総利益)→販管費→(営業利益)という順で見られるといます。これに対し、経営改善計画策定の中で、体質改善、つまり営業利益が上がりやすい体質づくりに取り組む際には、販管費→売上原価→売上高の順に、損益計算書を下からチェックしていくと効率的かつ効果的に進めることができます。
まず、経営改善計画策定において重要な位置を占める販管費をチェックしていきます。販管費がなぜ重要かというと、「コストを削減したら削減した分だけ、同額の利益拡大につながるため」です。
例えば改善取組み前の利益率が5%の会社の場合、売上高を100万円増収させても5万円の利益改善にしかつながりません。
もしも同じ会社で100万円の販管費抑制ができたとしたら、100万円の利益改善につながります。社長さんの頭の中では同じ100万円という金額であっても、その利益に影響する重みは20倍違います。言い方を変えれば、100万円の販管費抑制の取組みは、2000万円の売上アップの取組みと同じなのです。「100万円の販管費抑制の取組みと、2000万円の売上アップの取組み、果たしてどちらが取組みやすく、達成可能性が高いでしょうか」という質問を社長さんに投げかけることで、販管費抑制の重要性をご理解いただけやすくなると思います。
次に、売上原価を見ていきます。製造業の例でいえば、原材料費・労務費・外注加工費・その他経費の内訳費目ごとに無駄がないかをチェックしていきます。多くの場合、売上原価は、変動費(売上が上がれば増える経費)と固定費(売上が上がっても一定の経費)に分かれます。このうち固定費については、販管費と同じ目線で、「削減額=利益増加額」という観点で、抑制できるものがないかを重点的に見ていきます。
金額で見ていく固定費に対して、変動費についてはパーセント、つまり「売上高との比率」という効率性の観点を重視します。同じ注文に対して、より少人数で、より安コストで、より短時間で対応することができれば、その分だけ利益が残りやすい体質になることができます。なお、売上原価はその企業の付加価値の創出に直接関わっているため、販管費と比較してより慎重に進める必要があります。効率性を追求するあまりに、品質の高さを始めとするその企業のかけがえのない強みを失ってしまっては元も子もありません。
最後にチェックするのが売上高です。コンサルティングの世界では、売上高=顧客数×購買単価×購買頻度という方程式がよく使われますが、体質改善を行う際にはとくに「購買単価」や「商品別・顧客別等のカテゴリごとの売上高」が重要になります。売上高は、それだけでは「単なる規模の大小」に過ぎませんが、粗利益率と組み合わせて、「利益率の高い売上が増えているか」をチェックすることで、儲かりやすい体質づくりに役立てることができます。
このように、体質改善のために損益計算書をチェックするには、優先順位は販管費→売上原価→売上高の順で見ていきますが、これは「利益へのインパクトの大きさ」の順であると同時に、「取組み実行の確実性」の順でもあります。
【損益計算書をチェックするときの優先順位】

前述のとおり、売上はあくまで「お客様ありき」ですから、確実性は比較的低くなります。売上原価には、自社で取り組めることもありますが、外注先や品質への期待度等の社外の要素も含まれています。販管費については、基本的に自社が取り組もうと決めさえすれば、確実に実行して効果をあげることができます。効果が大きく、確実に効果を出せるところから優先的にチェックを進めていくことで、効率的かつ効果的に体質改善を図ることができます。
⒉ 管理会計を経営判断に活用せよ!

課題を明らかにして意思決定につなげる管理会計
企業会計は、その目的に応じて「財務会計」と「管理会計」という2つに区分することができます。
まず「財務会計」とは、企業外部の利害関係者に、企業の財務状態や経営成績などに関する経済的情報を提供するためのもので、わかりやすく言えば決算書をつくるための会計です。
これに対して「管理会計」とは、主として企業の内部において、企業自身の情報を分析活用する目的で行われるものです。具体的には、社内において各業務プロセスからデータを集計・加工し、直接費や間接費の原価分析、収益性分析のレポートを作成し、それを基に現状把握や経営判断に活かしていきます。例えば、月次売上金額、部門別損益、商品の損益分岐点など、社内で使用される数字はすべて管理会計に含まれます。とくに法的なルールはなく、レポートの形式などについても制限はありません。
管理会計のメリットとしては、「数値に基づく意思決定ができるようになること」と「数値に基づく業績評価」などの経営者側のメリットが挙げられますが、管理職や現場レベルに経営者感覚を身につけてもらいやすくなることも利点となります。一般的な会計ソフトにも、財務会計をすることで管理会計に反映させる機能がついています。少なくとも使って損になることはありませんので、具体的には税理士事務所と相談のうえで進めていただくよう推奨します。
「部門別会計」でセグメントごとの収益性を把握する
経営改善における基礎データは、まずは決算書になります。ただし、決算書は全体の合計しか表示されません。1つの事業所で1つの事業しか行っていない小規模事業者であれば、この決算書を見るだけで充分です。しかし、多角化で複数の事業を運営している、あるいは多店舗展開で複数の事業所がある場合などでは、現状分析や課題の抽出、計画策定において十分な精査ができないケースがあります。
例えば、麺を製造してスーパーマーケットに卸している食料品加工会社が、自社の麺を使ったラーメン店も運営している場合、この会社には「製造業」と、「料理飲食店」という2つの側面があります。製造業の顧客は小売店等の事業者ですが、料理飲食店の顧客は地元住民であり、ターゲット顧客もビジネスモデルも利益の構造もまったく異なります。この2つの異なる事業がまとめて合算されてしまう決算書では、不振原因の核心に迫る分析はできません。
また、営業エリアや取扱商品が異なる5店舗を経営している小売業の場合、業績不振になったとしてもすべての店舗が同時並行的に不振になるわけではなく、特定の店舗が大きく足を引っ張っている可能性があります。しかし、5店舗がまとめて合算されてしまう決算書では、どの店舗が不振なのかということすら把握することができません。
このようなケースで活用したいのが、管理会計の手法の1つである「部門別会計」です。部門別会計とは、1つの企業が複数の事業や店舗を運営している場合に、それぞれの事業別・店舗別に損益を算出する会計手法です。
経営改善計画策定においては「事業分析」と「財務分析」を組み合わせて現状分析や課題抽出を行います。事業内容が異なれば、照らし合わせる財務内容もそれに応じたものでなければ意味がありません。1つの会社で2つの事業を運営している場合は、「2つの会社を分析する」のと同じレベルで実施します。また、計画策定後のモニタリングについても、全体の結果はもちろん、事業別・店舗別の業績を把握してこそ意味があります。
複数事業あるいは複数店舗を運営している会社の経営改善計画策定支援を行う場合は、部門別会計は必須です。もしも現時点で部門別会計を導入していないようであれば、社長さんと経理担当者と顧問税理士を説得して何が何でも導入していただきます。この場合は、「部門別会計を導入する」こと自体を、アクションプランとして織り込みます(今から部門別会計を新規で導入しても、その結果を確認できるのは1年後の決算以降となります)。
不採算部門・不採算事業を冷静に見極めよ
部門別会計によって、事業別や店舗別に収益状況を分析していくと、どう考えても収益が取れていない不採算事業・不採算部門の存在が明らかになることがあります。現時点で不採算であったとしても、しっかりと戦略を練って対策を打つことで改善できる可能性はあります。
しかし、万策を尽くしたとしても、将来的に収益改善できる見通しが立たない(可能性が低い)場合には、「撤退」が最も合理的な選択肢となります。不採算セグメントから撤退する決断ができれば、そのセグメントで生じている赤字額はゼロになりますので、その分だけ確実に利益改善効果を得ることができます。
もっとも、明らかに撤退することが合理的な判断と考えられる場合でも、社長さんがなかなか決断できないことがあります。赤字を解消できずに撤退するとなれば、その事業を始めたときの苦労や、今まで投じてきた費用や時間はすべて無駄になります。撤退の決断ができない理由は、「あの苦労やお金を無駄にしたくない」、「ここまで頑張ってきたのに諦めるわけにはいかない」、「せめてマイナスだけでも回収したい」という社長さんの心の叫びです。
ここで考慮すべきなのが、サンクコスト(埋没費用)という概念です。サンクコストとは、事業や行為に投下した資金・労力のうち、事業や行為の撤退・縮小・中止をしても戻って来ない資金や労力のことを指します。既に過去に投入して戻ってこない費用を「もったいない」と思うあまりに、「損する可能性が高くても後には引けない」と合理的ではない判断に陥る心理現象を、サンクコスト効果(行動心理学ではコンコルド効果)と呼びます。学問的に定義づけられるということは、我々を含めて誰もがこの心理現象に陥る可能性があるということであり、社長さんが判断を誤りがちになるのはある意味当然のことと言えます。
判断を誤ったとしても、全体として吸収できる程度であれば、目くじらを立てる必要はないかもしれません。しかし、業績不振で資金繰り難に陥り、事業の存続にかかわるような重大場面においては、この誤りは致命傷になります。我々支援者は、ある意味では冷静な第三者であるからこそ、社長さんが判断を誤らないよう適正なアドバイスを提供することが期待されています。
支援者の基本スタンスとして、「過去の経緯は考慮しない」、「現時点からゼロベースで考える」、「現在から未来にかけて最も合理的な判断を促す」という信念をもって社長さんと対峙する必要があります。具体的には、部門別会計を活用した「財務分析」と「事業分析」をもとに今後の見通しを説明し、「もしも過去の話はなかったことにしたら、今から新たにこの事業を始めようと思いますか」という質問を投げかけるのが有効な対策となります。
社長さんの心情には理解を示しつつ、撤退が最も合理的な経営判断であることを、誠意をもって丁寧に説明していきます。最初は強い抵抗をしていた社長さんが最終的には、「実は薄々自分でも間違っていることには気づいていましたが、今回、はっきりと助言していただいて決心がつきました。ありがとうございます」と感謝されることも多くあります。
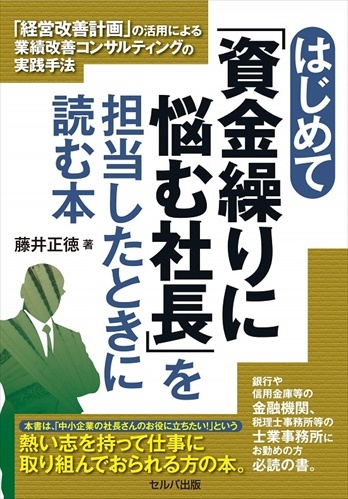
※画像をクリックするとAmazonに飛びます



















