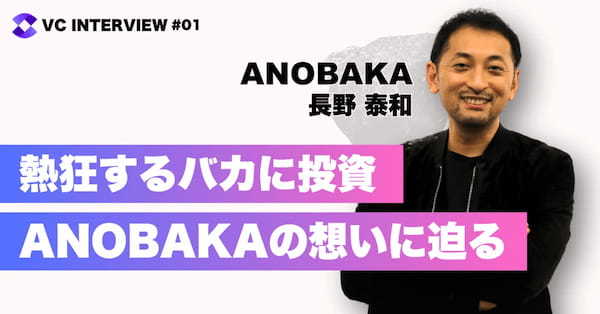
“チャレンジを至高の概念とする”
何よりも至高な概念を「チャレンジ」とし、シード/アーリーステージの起業家を支援するベンチャーキャピタル(以下、VC)、株式会社ANOBAKA。今回のVCインタビューは、ANOBAKA 代表取締役社長の長野 泰和さんにお越しいただきました!
シード・アーリーステージ特化型VCとして業界内外で高い評価を得るANOBAKA社。その裏には「挑戦する熱狂的なバカ」を支援し、彼・彼女らの可能性に賭けるANOBAKA社ならではの戦略がありました。
全3部構成でお届けする1部目の【前編】では、ANOBAKA社設立の背景や、特徴的な社名に込められた想い、「バカ」という言葉が持つ深い意味についてお話を伺いました!
| STARTUP LOGでは、VC・投資家のみなさまの活動紹介を行い、スタートアップ関係者にとって有益な情報提供をさらに拡充していきます。 ご興味を持っていただけたら、フォローやシェアをお願いします! |
ANOBAKA 代表取締役社長 長野 泰和さんの経歴

ーまずは長野さんの経歴ついて教えてください。
長野氏:もともとITが好きで、ITの企画者になりたいと思い、新卒でKLab株式会社というモバイルインターネットに特化した会社に入社しました。プロデューサー業務などを担当した後、上場を機にKLab社がCVC(コーポレートベンチャーキャピタル)の事業に参入した際、CVCの社長に就任しました。その後、もっと発展していきたいという思いでMBO(マネジメント・バイアウト)を実施し、4年前にANOBAKAという社名にして独立系のVCとして活動しています。
ー数あるIT業界の中で、なぜKLab社を選ばれたのですか?
長野氏:当時、KLab社はモバイルインターネットに注力している新進気鋭の会社で、それが魅力的に映ったのが一番の理由です。学生時代に1年間ほどインターンを経験し、そのまま新卒として入社しました。
KLabでは主にプロジェクトマネジメント系をしていました。 クライアントのモバイルサイトの構築や、自社の新規事業企画・立ち上げ・管理などの経験を積みました。
ーそこから新規のCVC事業の責任者に抜擢いただいたというお話しでしたが、抜擢の理由は何だったのでしょうか。
長野氏:後々、当時のKLab社長だった真田さんから聞いた話ですが、僕が新規事業の企画者として、アメリカの最新テクノロジーやビジネスモデルに関して、社内で一番情報収集をし、面白いアイデアをどんどん社内で発信していたそうです。
その結果、新しいビジネスに対する興味関心が社内で一番高いと評価され、適正があるだろうと判断されたようです。それまでの仕事で築いてきた信頼残高も大きかったと思いますが、それが理由だったのかなと感じています。
プロジェクトマネージャーを続けたかった気持ちもありましたが、キャリアの中で色々な仕事に挑戦したいなと思っていました。そのため、自分の仕事の幅を広げるという意味でも、魅力的なチャンスだと思って、すぐに「やります!」と回答しました。
CVCからの独立(MBO)当時を振り返って

ーCVCで実績を残された後、MBOの決断に至ったかと思うのですが、MBOで一番苦労されたのはどういった部分でしたか?
長野氏:資金面ももちろん苦労しましたが、それ以上に孤独な作業が辛かったですね。当然ですが、MBOに関しては他のメンバーにも、家族にも話すことができませんので、すべて自分一人で対応する必要があり、1年間ほどその状態が続きました。土日も含め毎日夜まで働き続け、やるべきタスクが常に300件以上リストアップされているような状況でした。
ーそのような苦労も乗り越えられたのは、やはりその裏に強い想いがあったからでしょうか?
長野氏:強い想いもありましたが、Amazonの創業者であるジェフ・ベゾスが提唱している「Regret Minimization Framework」という有名な思考法も、当時の意思決定に大きく影響しました。
このフレームワークは、人生の重要な場面で「将来自分が死ぬときに後悔しない選択肢はどちらか」を考えるというもので、後悔を最小化するための考え方です。僕自身もまさにこの方法を参考にしていて、「あのとき挑戦しなかった」と将来後悔するより、「挑戦して後悔するほうがずっといい」と思ったんです。
ーある意味、長野さんの死生観に基づいての意思決定だったんですね
長野氏:そうですね。だからこそ、この決断自体はそこまで難しいものではありませんでした。
ANOBAKA という社名の由来〜投資判断について
ーでは、ここからは会社についてお伺いさせてください。まずはなぜ社名を「ANOBAKA」にされたのでしょうか

長野氏:2つの意味があります。1つ目は僕が大学時代に読んだ本『ネット起業!あのバカにやらせてみよう』が大きな影響を与えています。そもそもこの本を読んだことでスタートアップ業界に興味を持ち、その主人公がKLab社の真田さんだったことからKLab社に入社するきっかけにもなりました。会社を立ち上げる際に社名をどうしようかと考えたときも、真っ先にこの本が思い浮かびました。
ー長野さんにとって運命の一冊だったんですね。もう1つの意味は何でしょうか。
長野氏:もう1つは、VCとしてシード期に特化している僕らのスタンスと密接に関係しています。当時CVCとして約80社ほど投資していましたが、その経験から事業プランやアイデア以上に、創業者が持つ「信じる力」や「熱狂」が重要だと強く感じていました。その「熱狂」を象徴するものとして、「バカ」という言葉がしっくりきたんです。
僕らの信念は「無名で反骨精神を持つ若者たちを、戦いの舞台に立たせるために投資をしていく」なので、そうした信念を体現する社名として、この名前が最適だと思いました。
ー投資判断をする上で起業家の方が「そうした反骨精神を持つ、バカかどうか」という部分も判断軸の1つになるということですね。
長野氏:そうですね、「バカ」という言葉は、その人がどれだけその事業に熱狂しているかを示す指標になると思っています。例えば、うちには毎月60〜70社ほどの企業から「投資してください」という依頼が来ますが、その中でいろいろ質問していくと、調査が不十分だったり、考えきれていない人が出てくるんです。そういう人たちは、正直言って「バカ」ではないんです。熱狂していないから細部まで調べていないし、深く考えることもしていないわけです。
本当に熱狂している人というのは、まさに「バカ」みたいにその事業について徹底的に調べ尽くしていて、どんな質問にも自分の仮説や考えをしっかり答えられる状態になっています。なので私たちはその熱狂を見極めるために丁寧にフィルタリングすることを意識しています。
ーその他、投資判断のうえで重要視されている部分はどういったところでしょうか?
長野氏:シード期において事業仮説がうまくいくかどうかなんて、正直誰にもわからないんですよ。それを「わかる」と思い込むのは、いわゆる傲慢であり、失敗の原因になることが多いと思います。だからこそ、そうした傲慢な判断を避けるのが重要だと考えています。
事業仮説の正しさそのものは判断できなくても、その仮説を実行しようとする創業者がどれだけ本気なのかは見極めることができます。そのために、競争優位性や顧客獲得戦略、サービス設計まで、さまざまな角度から「何を、どのように利用し、どう検証・判断していくのか」細部まで質問を投げかけるようにしています。
そうした質問に対して明確に答えられる場合、事業に本気で取り組んでいると判断できますので、これらが私たちの判断基準になっています。
ANOBAKAのベンチャーキャピタリストについて

ー起業家さんの見極めをするキャピタリストの方々も、鋭い洞察力やキャッチアップしていく力が求められますね
長野氏:もちろんです。スキルがないとそもそも適切な質問をすることすらできません。事業を見極めるためには、キャピタリスト自身が幅広い分野で知識を網羅的に持っている必要があります。それがないと、事業のフィルタリングそのものが成り立たないんです。だからこそ、うちのメンバーには常にキャッチアップし続けてもらうようにしています。
ー社内でのキャピタリストの研修にも力を入れているのでしょうか?
長野氏:研修は一切やっていません。なぜかと言うと、育成でどうにかなるものじゃないと思っているからです。たとえば、営業やマーケターを育てる場合であれば研修や育成は有効だと思ってます。なぜなら、学ばなければいけない知識の範囲が限定されているからです。しかし、キャピタリストという職種はそう簡単にはいきません。投資業務だけを覚えれば良いわけではなく、経営戦略や会社法、契約業務、さらにはテクノロジーやマーケティングといった、非常に幅広い知識が必要になります。
ー際限なく知識の拡充・スキルの向上をし続けなければいけない訳ですね。
長野氏:こうした広い範囲をカバーする内容を研修で補うのは、正直不可能です。だからこそ、知的好奇心がある人でないとキャピタリストとして成り立たないと考えています。逆に知的好奇心があれば、ベンチャーキャピタルという環境の中で、さまざまな出来事やイベントを通じてキャッチアップし、将来的に必ず一人前のキャピタリストになれると考えています。そのため、学びたいという意欲を支えるインフラはしっかり提供していますが、体系的な研修は一切行っていません。
ーとなると、尚更ベンチャーキャピタリストの採用は難易度が高いですよね。
長野氏:そうですね。選考の段階で知的好奇心の高さを基準に見極めていますが、それがどれだけ本質的なものなのか、表面的に取り繕った「お化粧」のような答えなのかを見抜くのは、正直なところ簡単ではありません。それでもANOBAKAのメンバーを見ていると、みんな活躍してくれていますし、素晴らしい仲間集めができていると思っています。
ー数々の起業家さんを見極めているANOBAKAさんだからこそ、ハイレベルな人材採用も実現できているのですね。
(前編はここまで)
ANOBAKA社では、共に起業家を支援する仲間を募集しています!少しでも興味を持った方は、以下のリンクから採用情報をご覧ください。
▼ANOABAKA 採用情報サイト
https://productive-gorgonzola-d02.notion.site/ANOBAKA-e52efe48e104445a906805a12bbfbfeb

productive-gorgonzola-d02.notion.site
次回の中編では、ANOBAKA社の特徴や強み、話題の生成AI特化ファンド「Generative AI Fund」についても探っていきます!
中編はこちら:https://startuplog.com/n/ne4c38a1a8cb3?sub_rt=share_pb





















